トライアル雇用はやめたほうがいい?導入前に知りたいメリット・デメリット

トライアル雇用を始めるかどうか、悩むところですよね。
採用した人が職場に合わなかったらどうしようとか、短期間で辞められたら困る、という気持ち、よくわかります。
できることなら、最初から会社に適合する優秀な人材を見極めたいですよね。
実は、トライアル雇用のメリットとデメリットをしっかり理解するだけで、適切な判断ができるようになります。
トライアル雇用が正しく活用されれば、採用リスクを最小限に抑えつつ、本採用につなげられるのです。
そこで今回は、「トライアル雇用のメリット・デメリット」をご紹介します。
トライアル雇用の特徴を認識し、自信を持って判断できるようにしましょう。
トライアル雇用とは

トライアル雇用とは、企業が求職者を一定期間試験的に雇用し、業務の適性や実力を見極める制度です。
通常、トライアル雇用は最長3か月の期間で行われ、その後、正式な採用の有無が決まります。
トライアル期間中は、労働条件や仕事内容については本採用と同様に取り決めがなされ、給与や福利厚生の面でも基本的に本採用と同じように設定されます。
採用後の労働契約を結ぶ前に実力やフィット感を確認できるため、企業側には大きなメリットがあるのです。
トライアル雇用により、長期的な雇用リスクを避けることができ、適切な人材選びが可能となるでしょう。
トライアル雇用のメリット

トライアル雇用には、企業にとって有益な効果が多く含まれています。
これを適切に活用することで、採用活動の効率化や人材管理の質を向上させることが可能です。
まずは、トライアル雇用のメリットについて見ていきましょう。
採用前に実力を確認できる
トライアル雇用では、実際の業務を通じて求職者のスキルや実力を見極めることができます。
実際の業務に従事してもらうことで、履歴書や面接だけでは分からない能力を判断できるためです。
営業職の候補者には実際に顧客対応をしてもらい、コミュニケーション力や課題解決能力を確認できます。
採用前に能力を確認することで、より確実な雇用判断ができるでしょう。
短期間で雇用判断ができる
トライアル雇用は、限られた期間内で採用の可否を決定する仕組みです。
一定の期間だけ雇用契約を結ぶことで、長期間の試用期間を設ける必要がなくなるためです。
たとえば、3か月のトライアル期間中にパフォーマンスを評価し、適性を見極めることができます。
短期間で効率的な雇用判断が求められる場合には、有効な手段といえるでしょう。
柔軟な人材活用が可能
トライアル雇用により、企業は新たな人材を柔軟に活用できます。
期間限定の雇用契約であるため、繁忙期やプロジェクト単位で人材を確保しやすくなるためです。
たとえば、急な人手不足が発生した場合に、トライアル雇用で短期的に補充することができます。
トライアル雇用を活用することで、状況に応じた柔軟な人材運用が可能になるでしょう。
業務への適応度がわかる
トライアル雇用では、求職者が企業文化や業務内容に適応できるかを判断できます。
実際の現場で働くことで、求職者の適応力や働き方が明確になるためです。
具体的には、チームワークが重要な職場でのコミュニケーション能力や協調性を観察できます。
採用後のミスマッチを防ぐために、事前に適応度を確認することが重要です。
早期の改善が可能
トライアル雇用は、問題点が早期に発見でき、改善に繋げられる仕組みです。
期間中に発見された課題に対し、対策を講じる時間が確保されるためです。
たとえば、業務スキルが不足している場合に、適切な研修や指導を実施できます。
早めに課題を明確にすることで、雇用の成功率を高められるでしょう。
トライアル雇用のデメリット

トライアル雇用には多くの利点がありますが、同時に企業が注意すべき課題も存在します。
これらを理解し、採用活動を慎重に進める必要があります。
ここからは、トライアル雇用のデメリットについて解説します。
採用後のミスマッチ
トライアル雇用では、採用後にミスマッチが発生する可能性があります。
短期間の評価では、求職者の真の能力や適性を完全には見極められないからです。
たとえば、一定期間内では見えにくい問題や、長期間で初めて現れる課題が残る場合があります。
こうしたミスマッチが発生する背景には、短期評価の限界があるといえるでしょう。
短期的な労力がかかる
トライアル雇用では、企業側に短期的な負担が増える場合があります。
候補者の指導や評価に多くの時間とリソースを割く必要があるためです。
たとえば、新しい候補者への研修や、実務に慣れるまでのサポートに時間が取られることがあります。
短期間で求職者を戦力化するのは、容易ではないのが現状です。
社員の不安定感を招く
トライアル雇用の導入によって、既存の社員に不安を与える可能性があります。
候補者が本採用になるかが明確ではない場合、職場の安定感が揺らぐためです。
たとえば、候補者と既存社員との関係性が構築される前に、トライアルが終了するケースがあります。
こうした状況が生まれる原因は、雇用の一時性に起因しているといえるでしょう。
採用決定まで時間がかかる
トライアル雇用では、採用の意思決定までに時間を要することがあります。
一定期間の評価を行うことで、判断が遅れる場合があるためです。
たとえば、トライアル終了後に適性の再確認や条件の再調整が必要になることがあります。
採用プロセスが長期化するのは、この評価制度の特性の一つといえるでしょう。
解雇リスクが伴う
トライアル雇用は、解雇リスクを伴う可能性があります。
期待した成果が得られなかった際に、契約終了がトラブルになる場合があるためです。
たとえば、求職者が契約終了を不服として、解雇に関する法的措置を取るケースが考えられます。
このリスクの背景には、労使間の認識の違いがあると考えられます。
トライアル雇用を導入する方法

トライアル雇用を成功させるためには、適切な準備と計画が必要です。
それぞれのプロセスを慎重に進めることで、効果的な活用が期待できます。
目的を明確にする
トライアル雇用の導入において、まずは目的を明確にする必要があります。
企業が求める成果や人材像を具体的に設定しなければ、採用活動が曖昧になるためです。
たとえば、新規プロジェクトの立ち上げに伴う人材の一時的な確保や、特定のスキルを持つ人材の検証などが挙げられます。
目的を明確にすることで、採用活動の方向性を確実に定めることができるでしょう。
採用基準を設定する
トライアル雇用では、適切な採用基準を設定することが重要です。
基準が明確でないと、候補者の選考に一貫性がなくなり、ミスマッチの原因となるためです。
たとえば、必要なスキルや経験、性格面での適性をリストアップし、それを基に選考を行う方法があります。
明確な基準があれば、採用プロセスが効率化されるでしょう。
契約内容を明確にする
トライアル雇用では、契約内容を事前に明確にしておくことが不可欠です。
労使間での認識の違いを防ぐため、条件を詳細に文書化する必要があるためです。
たとえば、雇用期間、賃金、業務内容、評価方法などを具体的に記載した契約書を作成することが挙げられます。
契約内容を明確にすることで、後のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
サポート体制を整える
トライアル雇用では、求職者を支えるサポート体制の整備が求められます。
十分な支援がなければ、候補者が業務に適応できず、成果を発揮できない可能性があるためです。
たとえば、業務の指導担当者を決めたり、初期段階で必要な研修を提供する仕組みを設けたりすることが考えられます。
サポート体制が整えば、求職者の能力を最大限に引き出すことができるでしょう。
終了後の評価基準を決める
トライアル雇用終了後の評価基準を事前に決めておくことが重要です。
評価基準が曖昧だと、採用の最終判断が不透明になり、不公平感が生じるためです。
たとえば、業績目標の達成度や職場への適応度を評価項目として設定し、具体的な基準を明示することが効果的になります。
終了後の評価基準を定めることで、採用判断がスムーズに行えるでしょう。
トライアル雇用実施の主な流れ

トライアル雇用を実施する際には、いくつかのステップを経る必要があります。
各ステップを適切に進めることで、採用プロセスを円滑に進めることが可能です。
トライアル雇用求人の提出
まず、トライアル雇用の求人情報を正式に提出する必要があります。
適切な求人内容を記載しなければ、対象となる求職者を集めるのが難しくなるためです。
たとえば、職業安定所や求人サイトを活用し、求職条件や募集背景を詳しく記載した求人情報を公開することが考えられます。
正確な求人情報を提供することで、求職者とのマッチングがスムーズに進むでしょう。
求職者との面接・選考
次に、応募してきた求職者との面接や選考を行います。
候補者の適性を見極める重要なプロセスであり、採用の質に直結するためです。
たとえば、履歴書や職務経歴書を確認した上で、スキルや性格、業務への適応度を測る面接を実施することが一般的です。
慎重な選考を行うことで、自社に最適な人材を見つけることが可能です。
トライアル雇用の締結
採用が決定したら、トライアル雇用契約を締結します。
契約内容を明確にしないと、後にトラブルを招く可能性があるためです。
たとえば、労働期間、賃金、勤務時間、業務内容などを詳細に記載した契約書を作成し、双方が合意の上で署名を行います。
明確な契約締結によって、安心してトライアル雇用をスタートできるでしょう。
トライアル雇用の実施
契約締結後は、実際にトライアル雇用を開始します。
企業と求職者の双方が、業務内容や職場環境に適応していく必要があるためです。
たとえば、入社初日に業務の説明を行い、現場での業務を通じてスキルや適応力を確認していきます。
トライアル期間中の実施内容は、その後の評価に大きく影響するポイントといえるでしょう。
トライアル雇用助成金の申請
最後に、条件を満たしている場合は、トライアル雇用助成金の申請を行います。
助成金を申請することで、採用コストを軽減できる可能性があるためです。
たとえば、所定の申請書類を揃えて労働局へ提出し、必要な手続きを行うことが一般的です。
助成金を適切に活用することで、企業の採用活動をより効率的に進められるでしょう。
トライアル雇用を導入する際の注意点
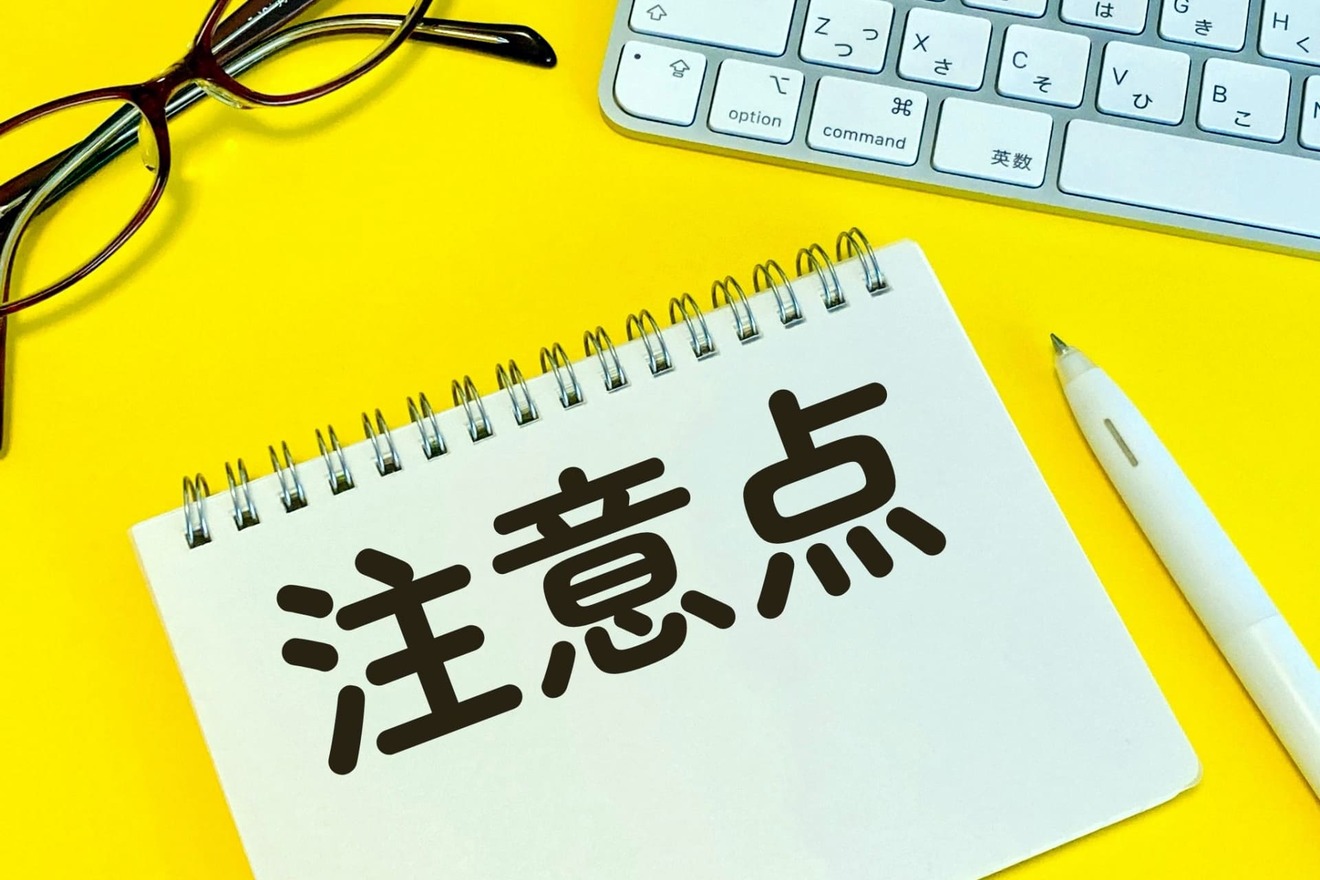
トライアル雇用を円滑に進めるためには、いくつかの注意点に気を配る必要があります。
これらを徹底することで、労使間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
契約内容を明確にする
トライアル雇用では、契約内容を明確にすることが最も重要です。
労使間の認識にズレがあると、後にトラブルや不信感を招く原因となります。
たとえば、労働期間、賃金、勤務条件、雇用形態などを文書で明確に記載し、事前に双方で確認することが大切です。
契約内容を明確にすることで、企業と求職者の信頼関係を築きやすくなるでしょう。
業務内容を具体的に伝える
トライアル雇用を実施する際には、業務内容を具体的に伝えることが大切です。
求職者が業務内容を正確に理解していないと、適応に時間がかかったり、意図しないミスマッチが生じたりするためです。
たとえば、担当する業務の範囲や具体的な業務手順、期待される成果などを説明会や書面で伝えることが効果的です。
業務内容を具体的に伝えることで、求職者が安心して業務に取り組むことができるでしょう。
フォローアップを怠らない
トライアル雇用期間中は、求職者に対するフォローアップを怠らないようにしてください。
適切なサポートがないと、求職者が不安を抱きやすく、成果を発揮しにくくなるためです。
たとえば、定期的に面談を実施して、業務上の課題やストレスをヒアリングし、適切なアドバイスを提供することが有効です。
フォローアップを怠らないことで、求職者の成長をサポートしやすくなるでしょう。
社員の不安に配慮する
トライアル雇用を導入する際には、既存社員の不安に配慮することも必要です。
新たな雇用形態が導入されることで、既存社員が職場環境の変化を懸念する可能性があります。
たとえば、トライアル雇用の目的や候補者の役割を説明し、社員が安心できるようなコミュニケーションを図ることが重要です。
社員の不安に配慮することで、職場全体の円滑な運営が期待できるでしょう。
労働関係法令の遵守
トライアル雇用を実施する際には、労働関係法令を厳守することが不可欠です。
法令違反が発覚すると、企業の信用が失墜し、法律上の問題が発生する可能性があります。
たとえば、労働基準法や雇用契約に関する規定を確認し、必要に応じて専門家に相談することが有効です。
労働関係法令を遵守することで、適正な運営と信頼の確保につながるでしょう。
トライアル雇用を成功に導くシステム活用法

トライアル雇用を成功させるためには、効率的なシステムを活用することが重要です。
適切なシステムを導入することで、業務の効率化と情報の透明性を向上させることができます。
応募者情報を一元管理する
採用管理システムを活用することで、応募者情報を一元管理できます。
バラバラに管理された情報は確認作業に時間がかかり、ミスや漏れを招きやすいためです。
たとえば、応募者の履歴書やスキル情報、面接結果などをデジタルツールに集約することで、担当者が必要な情報をすぐに確認できるようになります。
応募者情報を一元管理することで、採用活動を効率的に進めることができるでしょう。
フィードバックを簡単に共有
トライアル雇用中のフィードバックを簡単に共有できるシステムも役立ちます。
情報共有がスムーズでない場合、関係者間での連携不足が発生する可能性があるからです。
たとえば、システム上で評価内容をリアルタイムに共有し、求職者の進捗や課題について全員が把握できる環境を作ることが挙げられます。
フィードバックを簡単に共有することで、採用の精度を高めることができるでしょう。
面接・試用期間を進捗管理
面接や試用期間の進捗を管理できるシステムも重要です。
進捗状況が見えないと、採用プロセス全体の把握が難しくなるためです。
たとえば、面接の日程調整や試用期間中のタスク完了状況を管理するツールを使用することで、採用活動の全体像を把握しやすくなります。
進捗管理ができるシステムを活用することで、採用プロセスを滞りなく進めることができるでしょう。
自動通知で迅速な連絡
自動通知機能を活用することで、迅速な連絡が可能になります。
連絡の遅れは求職者の不安や不信感を生む原因となるためです。
たとえば、面接の日程や書類の提出期限を自動で通知するシステムを導入することで、適切なタイミングで必要な情報を伝えることができます。
自動通知を利用することで、コミュニケーションの円滑化が期待できるでしょう。
パフォーマンスをデータで可視化
トライアル雇用期間中のパフォーマンスをデータで可視化するシステムも有効です。
直感や主観に頼った評価では、適切な判断が難しくなるからです。
たとえば、求職者の業務遂行状況や達成した目標をデータで記録し、数値化されたレポートを作成することが考えられます。
パフォーマンスをデータで可視化することで、公平で納得感のある評価が実現するでしょう。
トライアル雇用に関するよくある質問

トライアル雇用を検討する際、多くの経営者が共通して抱く疑問があります。
以下では、それぞれの疑問に対して明確な回答を提供します。
Q.トライアル雇用と試用期間の違いは何?
トライアル雇用は雇用契約を結ぶ前の段階でお互いに適性を確認する制度で、試用期間は本採用後の評価期間としての位置付けです。
トライアル雇用は、求職者のスキルや業務適応度を短期間で見極めるための雇用形態であるのに対し、試用期間は正式雇用後に適性を判断するための制度になります。
たとえば、トライアル雇用では助成金の活用が可能で、求職者に対して一定期間の短期雇用契約を締結しますが、試用期間は通常の雇用契約に含まれます。
目的と適用範囲が異なるため、それぞれの違いを理解することが重要になるでしょう。
Q.トライアル雇用の期間はどのくらいが適切?
トライアル雇用の期間は、1か月~3か月程度が一般的です。
求職者の業務適応度を判断するには、短すぎず長すぎない期間を設定する必要があるためです。
具体的には、1か月間で日常業務に慣れるかを確認し、さらに必要に応じて延長して深掘りする方法が適切です。
自社の業務内容や求めるスキルに応じて、柔軟に設定することが重要となるでしょう。
Q.トライアル雇用中の賃金はどのように設定する?
トライアル雇用中の賃金は、最低賃金以上で設定する必要があります。
トライアル雇用も正式な雇用契約に基づくため、賃金に関しては法令を遵守する義務があるためです。
具体的には、地域ごとの最低賃金を基準にしつつ、求職者のスキルや職務内容に応じた適正な賃金を提示する方法が推奨されます。
適切な賃金設定により、求職者のモチベーション向上が期待できるでしょう。
Q.トライアル雇用でも社会保険に加入させる必要はある?
トライアル雇用でも、一定の条件を満たす場合には社会保険への加入が必要です。
労働時間や雇用形態に応じて、健康保険や厚生年金保険などの加入義務が発生するためです。
たとえば、週30時間以上勤務する場合は社会保険の対象となるため、契約時に確認が求められます。
労働条件に基づき、必要な対応を取ることが求められるでしょう。
Q.トライアル雇用で問題があったら解雇できる?
トライアル雇用中に問題が発生した場合でも、正当な理由がなければ解雇は難しいです。
雇用契約期間中の解雇には、法的に正当な理由が必要とされるためです。
仮に、重大な規律違反や業務能力の著しい不足がある場合にのみ解雇が正当化されるケースがあります。
法的トラブルを避けるためにも、解雇は慎重に判断するようにしてください。
Q.トライアル期間終了後に本採用を辞退できる?
トライアル雇用終了後、企業側も求職者側も本採用を辞退することが可能です。
トライアル雇用の目的が双方の適性確認であるため、継続を強制するものではないためです。
たとえば、トライアル期間中の評価結果を基に、企業が採用を見送る決定を下す場合があるし、求職者側が辞退することも考えられます。
採用に関しては、お互いに合意の上で進めることが大切です。
Q.トライアル雇用に関する相談窓口はどこ?
トライアル雇用に関する相談は、ハローワークや労働局などの公的機関で受け付けています。
トライアル雇用制度は国が推進する制度であるため、専門の相談窓口が設置されているためです。
たとえば、最寄りのハローワークに問い合わせれば、制度の利用方法や助成金申請に関する詳細な説明を受けることができます。
適切な相談窓口を活用することで、円滑にトライアル雇用を進めることができるでしょう。
まとめ
トライアル雇用は、採用前に実力を確認したり、短期間で雇用判断を行ったりできる便利な制度です。
一方で、採用後のミスマッチや解雇リスクなどのデメリットも存在するため、導入には慎重な準備が求められます。
トライアル雇用を成功させるためには、目的や採用基準、契約内容を明確にし、サポート体制を整えることが重要です。
また、トライアル雇用求人の提出から終了後の評価基準の設定まで、一連の流れをしっかり把握することで、よりスムーズな運用が可能となります。
さらに、業務内容の具体的な説明やフォローアップの徹底、社員の不安に配慮することがトラブル回避に役立ちます。
採用管理システムを活用して応募者情報を一元管理し、フィードバックや進捗を見える化することも大切です。
トライアル雇用は正しく理解し活用することで、採用の可能性を広げ、企業の成長につながる選択肢になります。
本記事を参考に、御社にとって最適な判断を行いましょう。
関連記事
-
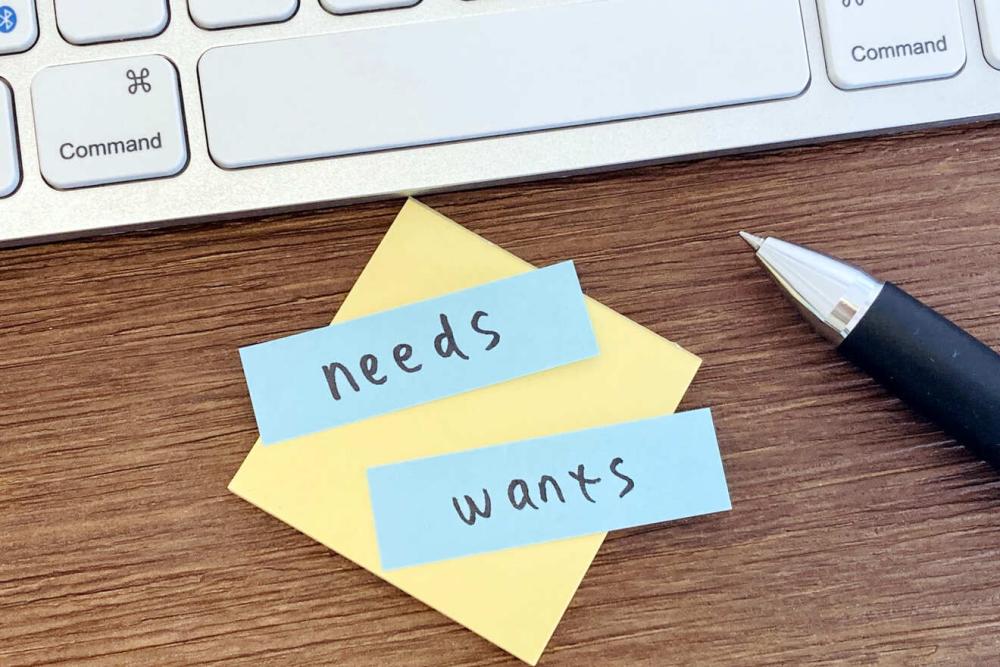
ウォンツとニーズの違いとは?採用活動で成果を出す実践ガイド
ウォンツとニーズの違いは、分かっているようで曖昧になりがちですよね。目の前のニーズとウォンツをしっかり見極めて、長期的な関係づくりをするにはどうすればいいのでし...
-

建設業で従業員を増やす方法!求人に応募が来ない時の採用戦略
建設業も、人手不足が深刻な課題になっています。従業員が足りなくなったら仕事を回しきれないし、納期を全うできません。そこで今回は、「建設業で従業員を増やすための具...
-
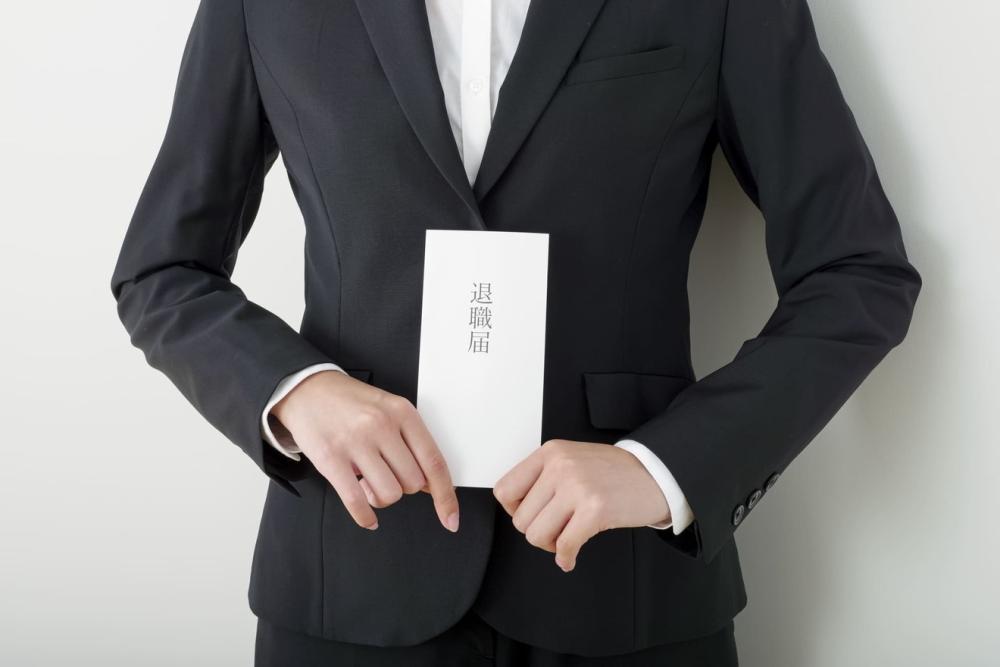
リベンジ退職とは?急増する理由と企業が取るべき対策を詳細解説
「リベンジ退職」という言葉が話題になっていますが、企業の経営者にとって最も避けたい事態です。優秀な人材が突然辞めてしまったら事業に大きな影響が出てしまうし、連鎖...
-

メンバー シップ型雇用とは?メリット・デメリットを徹底解説
メンバーシップ型雇用は、時代遅れだと言われることがありますよね。従来の方法を続けるべきか、他の雇用形態にシフトすべきかで、迷っている経営者の方も多いのではないで...
-

ハローワークとインディードどっちがいい?共通点と求人掲載の判断基準
求人を出すときに、ハローワークとインディード、どちらを選ぶか迷いますよね。採用活動を進める中で、本当に効果が出るのか不安になる気持ち、よくわかります。そこで、「...





