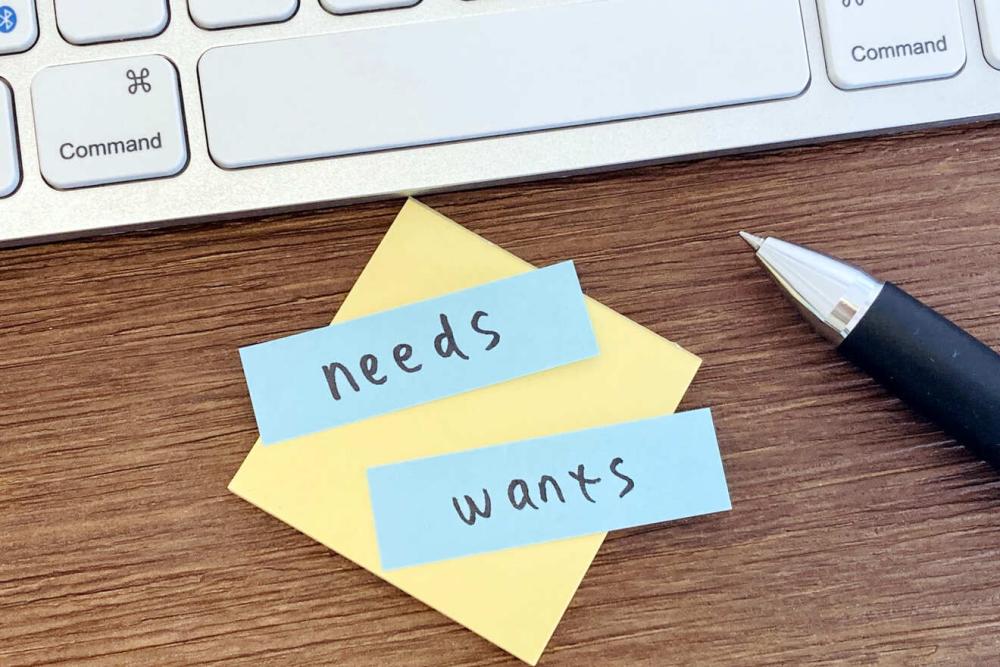退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略

これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。
突然の連絡に動揺してしまうし、「なぜ直接相談してくれなかったのか」と相手を責めたくなる気持ちわかります。
できることなら、最後まで信頼関係のある形で送り出したかったですよね。
実は、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。
職場環境を見直すことができれば、退職代行に頼るような事態にはなりません。
そこで今回は、「退職代行を使われたショックをチャンスに変える方法」をご紹介します。
社員との関係性を強化するためにも、採用戦略から見直していきましょう。
退職代行を使われた原因とは

退職代行を利用される背景には、職場環境や人間関係に起因するさまざまな要因が潜んでいます。
経営者側が気づきにくい問題も多いため、根本的な原因を丁寧に見つめ直すことが重要です。
まずは、どのような理由で退職代行を使われるのか見ていきましょう。
直接話す勇気が持てなかった
退職を伝える際に、本人が強い不安やプレッシャーを感じていた可能性があります。
対面での退職願いに対して、拒絶や叱責を受けるのではないかという恐れがあるためです。
たとえば、日常的に上司が強い口調で指導をしていたり、失敗に対して厳しい態度を取る風土がある職場では、退職を切り出すこと自体に大きなハードルが生まれます。
退職代行を使われたのは、心理的安全性に欠けていたことが影響しているでしょう。
退職を止められたくない
自分の意思を曲げられることなく、退職したいと考えていた可能性があります。
引き留めに合うと退職の決意が揺らいでしまうからです。
具体的には、「今辞めたら迷惑がかかる」「もう少し頑張ってみたら?」といった言葉で気持ちが揺れてしまいやすため、直接話す選択肢を避けているのかもしれません。
引き止められる前に確実に辞める方法として、退職代行を選んだのでしょう。
相談できない環境だった
職場で気軽に相談できる雰囲気がなかったことも、退職代行を使われた一因です。
相談しても理解されない、あるいは評価が下がると感じる風土があると、上司に相談できません。
具体的には、悩みを話しても「甘え」や「根性が足りない」と受け取られたり、上司との距離が遠く心情を共有しづらい組織では、問題が深刻化しても声を上げづらくなります。
結果として、誰にも相談できないまま退職代行という手段に至ったと考えられます。
同僚が揉めて辞めていた
過去に同僚が会社と揉めて辞めていた場合、退職代行を使われやすいです。
前例を見て「自分も同じようになるのでは」という不安があるからです。
仮に、以前辞めた社員が上司と口論になった、退職を巡って社内がギスギスした、といった状況を目の当たりにすると、自分はあのようにはなりたくないと感じて退職代行に頼ります。
過去の職場の対応が、現在の社員の判断に影響を与えたのでしょう。
精神的に限界だった
精神的な疲弊が進み、正常な判断が困難な状態に陥っていたことが考えられます。
心身ともに追い詰められた結果、通常の退職手続きができる余力がなかったのです。
たとえば、長時間労働や人間関係のストレスによりうつ状態になっていたり、出勤自体が困難になっていたケースでは、第三者の介入が唯一の解決策となることがあります。
精神的に限界の状態では、もはや自分で伝える手段を選ぶことができなかったのでしょう。
退職代行を使われた後のベストな対応

退職代行を利用された事実に直面した際、感情的にならずに的確な対応を取ることが、組織全体の安定につながります。
残された社員や今後の会社運営を見据えた行動が求められます。
そこで、退職代行を使われた後のベストな対応を考えてみましょう。
冷静に状況を受け止める
まずは感情を抑え、現実を受け止める姿勢が大切です。
感情的な反応は、社内の空気を悪化させる原因になるためです。
たとえば、「なぜ直接言ってくれなかったのか」と怒りをあらわにしたり、「裏切られた」と嘆くような姿勢は、他の社員にも不安を与える可能性があります。
退職代行を使われても、状況を正しく理解し、落ち着いた対応を意識するようにしてください。
残った社員に声をかける
退職者だけでなく、残った社員へのフォローも忘れてはいけません。
退職代行という出来事が社内に不安や動揺をもたらすことがあるためです。
例として、「今回の件で不安に思っていることはないか」「何か相談したいことがあれば話してほしい」といった声かけをすることで、安心感を与え、信頼関係を再構築するきっかけになります。
連鎖退職を招かないためにも、社員とのコミュニケーションを意識的に取るようにしてください。
退職処理を淡々と進める
事務的な手続きは感情に左右されず、粛々と進めることが求められます。
対応に時間がかかったり感情を交えると、社内外の信頼を損なう恐れがあるためです。
たとえば、退職書類の送付や業務引き継ぎの整理などを滞りなく行うことで、他の社員に「きちんと対応できている」と安心感を与えることができます。
退職に関する一連の処理は、どんな辞め方でも公平かつ迅速に進めましょう。
社内の雰囲気を立て直す
退職代行が発生した後は、組織の空気を整えることが重要です。
緊張感や不安が蔓延することで、他の社員のモチベーションにも悪影響が出るためです。
具体的には、朝礼やチームミーティングで前向きなメッセージを発信したり、全体の目標を再確認する場を設けると、社員同士の連携やモチベーションが向上します。
社内の雰囲気を立て直し、職場の空気を前向きに戻す工夫を取り入れてください。
今後に向けた改善を始める
一連の出来事を教訓に、職場環境の見直しを図ることが有効です。
再発を防ぐには、根本的な問題に向き合う姿勢が求められるためです。
たとえば、定期的な1on1面談を導入したり、匿名で意見を出せる仕組みを整えることで、社員の本音に耳を傾ける体制を作ることができます。
今後同じような事態が起きないよう、改善に向けた行動を起こしましょう。
退職代行を使われたときの注意点

退職代行を使われた場面では、冷静さを欠いた対応がさらなるトラブルを招くことがあります。
経営者や人事担当として、取るべき態度や言動には細心の注意が必要です。
辞めた人の悪口を言わない
退職者について否定的な発言をするのは避けるべきです。
悪口や批判は、残っている社員の信頼を損なう原因になるためです。
例として、「あいつは無責任だ」「自分の口から言えない弱虫だ」といった発言をすると、聞いている社員は「自分も将来そう言われるのでは…」と不安になります。
感情的な言葉は慎み、建設的な対応に努めてください。
感情に任せて対応しない
退職代行を使われても、怒りやショックをそのまま行動に移さないようにしてください。
感情的な判断は、事態を悪化させるリスクが高まるからです。
すぐにSNSに投稿したり、他の社員に怒りをぶつけるような行動は、会社の評判を損なうばかりか、組織の信頼関係にも傷を残します。
冷静な対応こそが、経営者や上司に求められる資質といえるでしょう。
退職理由を詮索しすぎない
必要以上に退職理由を詮索しようとするのは避けるべきです。
詮索されること自体が、職場への不信感を生む原因になるためです。
たとえば、退職者の知人や同僚に「なんで辞めたか聞いてない?」と執拗に尋ねると、周囲にも居心地の悪さを与え、無用な噂や誤解を生むことにつながります。
理由の解明よりも、職場の改善に意識を向けましょう。
退職者に報復しない
退職代行を使った社員に対して、報復的な対応をするのは厳禁です。
法的・倫理的に問題があるだけでなく、企業の信頼を大きく損なうからです。
たとえば、在職中の情報を外部に漏らしたり、今後の転職先にネガティブな連絡を入れるなどの行為は、明確なハラスメントと見なされ、逆に訴訟リスクが発生することもあります。
退職代行を使われても、冷静かつ公正な姿勢を保つことが求められるでしょう。
必要以上にショックを受けない
退職代行を使われるとショックですが、業務に支障をきたすことは避けるべきです。
経営者の動揺はそのまま社内全体の不安に直結するからです。
具体的には、退職の事実を引きずって経営判断が鈍ったり、他の社員への対応が消極的になると、組織のパフォーマンス全体に悪影響が及びます。
気持ちの整理は必要ですが、過度な感情に引きずられないようにしてください。
退職代行を使われた会社の採用戦略

退職代行の利用が発生した背景には、採用段階でのミスマッチも潜んでいます。
今後の人材定着を目指すためには、採用戦略そのものの見直しが重要です。
ターゲットを明確にする
自社に合った人材像を具体的に定めることが採用の第一歩です。
抽象的な条件では、ミスマッチを招きやすくなります。
たとえば、「やる気がある人」ではなく、「変化の多い現場でも柔軟に対応できる人」「少人数のチームで主体的に動ける人」など、具体的な業務内容や組織文化に合致する人物像を明確にします。
欲しい人物像を具体的に描くことで、採用の精度が高まるでしょう。
募集要項を見直す
求人票や募集要項の内容を、実態に即したものに更新することが大切です。
誇張された表現や実情との乖離があると、入社後のギャップにつながるためです。
仮に、「風通しの良い職場」と記載しているにもかかわらず、上司に意見を言いづらい空気がある場合、早期離職や退職代行のリスクを高める要因になります。
求人する際は、誠実かつ正確な情報発信を心がけてください。
社員の意見を取り入れる
現場の社員の声を反映することで、リアルな職場像を伝えられます。
社員の意見を取り入れることで、ミスマッチを防ぎやすくなるのです。
現役社員に「実際に働いていて大変な点」「やりがいを感じる瞬間」などをヒアリングし、それを採用資料や説明会に活用することで、応募者に正しい期待値を持たせることができます。
社員の声は採用戦略を見直す、貴重なヒントにもなるでしょう。
採用プロセスを透明にする
選考の流れや評価基準を明示し、納得感あるプロセスを設けてください。
採用段階で不信感が生まれると、入社後の定着にも悪影響が出るためです。
たとえば、面接で何を見て評価しているのか、合否の基準や選考ステップを事前に明らかにすることで、候補者は安心して応募できます。
フェアで開かれた採用活動を行うことで、候補者との信頼関係が生まれるでしょう。
リファラル採用を活用
既存社員からの紹介による採用は、ミスマッチのリスクを減らせます。
紹介者が会社の実情を理解した上で候補者を選ぶためです。
たとえば、「この人ならうちの社風に合う」と社員が推薦する人材は、入社後のギャップが少なく、定着率も高まる傾向にあります。
また、紹介者自身の責任感も高まり、職場への愛着も強くなるのです。
リファラル採用を活用することで、辞める際も退職代行に繋がりにくくなるでしょう。
退職代行を使われた側のよくある疑問

退職代行を使われてしまうと、制度や対応方法に関して多くの不安や疑問が生まれるものです。
ここでは経営者が感じやすい代表的な疑問に答えていきます。
Q.退職代行後の引き継ぎや業務整理はどうなる?
退職代行を通じて辞めた社員が、引き継ぎを行わずに退職するケースは少なくありません。
退職代行業者は法的な代理人ではないため、業務内容や社内対応に関する指示を直接行えないためです。
たとえば、書類やデータの整理が一切行われず、急遽社内で対応を分担せざるを得ない事態も考えられます。
事前に業務マニュアルを整備するなど、平時からリスクに備える体制をつくっておくことが大切です。
Q.退職代行を使われた企業は評判が悪くなる?
退職代行の利用が企業の評判に直結するとは限りませんが、背景によってはネガティブな印象を与える可能性はあります。
「辞めにくい職場なのでは」「パワハラやブラック体質があるのでは」と受け取られることもあるためです。
具体的には、SNSで元社員が実名で体験談を投稿した場合、それが拡散され企業イメージに影響を及ぼすこともあります。
自社の評判を守るには、普段から健全な職場づくりに努める必要があるでしょう。
Q.退職代行を使われた上司は評価が下がる?
部下に退職代行を使われても、必ずしも上司の評価に直結するわけではありません。
退職の原因が個人にあるとは限らず、職場環境や企業文化など複合的な要因が影響しているためです。
たとえば、部下とのコミュニケーション不足や支援体制の弱さが指摘されるケースもあれば、本人の私的事情による退職という場合もあります。
事実を丁寧に把握し、一人で責任を背負いこむ必要はないでしょう。
Q.退職代行を使った社員に法的対応をするべき?
法的対応は原則として慎重に検討する必要があります。
民事的な問題が発生していない限り、裁判などで争うことは得策ではないです。
仮に、業務に著しい損害を与えたり、機密情報を持ち出された場合は別ですが、私的の退職であれば、法的手段に訴える必要はありません。
感情ではなく、法的根拠とリスクを天秤にかけて判断してください。
Q.退職代行後の給与はどのように支払えば良い?
退職代行を使われても、労働の対価としての給与は正当に支払う必要があります。
未払いがあると、法的なトラブルに発展する可能性があり、必ず支払わなければいけません。
最終出勤日までの賃金、未消化の有給休暇の買い取り、社会保険の手続きなどは、通常の退職と同様に進めてください。
退職代行を理由に支払いを遅らせることのないよう、事務手続きは確実に行いましょう。
まとめ
社員に退職代行を使われたことは、経営者にとって大きなショックです。
しかしその背景には、「相談できない環境」や「精神的な限界」といったサインが隠れていた可能性があります。
まずは冷静に状況を受け止め、残った社員への声かけや社内の雰囲気の立て直しに取り組みましょう。
また、辞めた人の悪口を言わない・感情的に動かないといった基本的な注意点も、信頼を守るうえで重要です。
今後は、採用戦略を見直し、「ターゲットを明確にする」「募集要項の見直し」などでミスマッチを防ぎましょう。
退職代行をきっかけに職場環境を見つめ直すことで、社員にとっても経営者にとっても、より良い職場づくりにつながります。
過去の出来事を教訓とし、前向きな職場改善を進めてください。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...
-

歯科衛生士の採用は難しい?成功する医院の採用戦略を深堀り解説
歯科衛生士の採用は、年々難しくなっていますよね。募集してもなかなか集まらないと、どうしたらいいか悩んでしまう気持ちわかります。そこで今回は、「歯科衛生士の採用が...