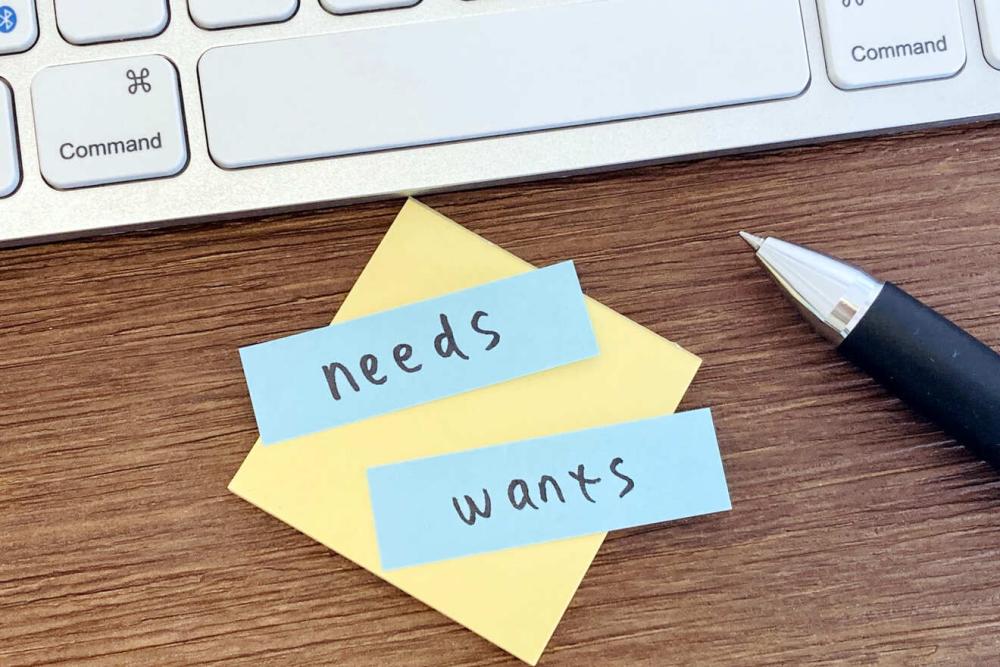歯科衛生士の採用は難しい?成功する医院の採用戦略を深堀り解説

歯科衛生士の採用は、年々難しくなっていますよね。
募集してもなかなか集まらないと、どうしたらいいか悩んでしまう気持ちわかります。
できることなら、優秀な歯科衛生士に長く働いてもらいたいですよね。
実は、採用のポイントを押さえることで、より多くの求職者に興味を持ってもらい、定着率を上げることができます。
採用の課題を解決できれば、スタッフの負担が軽減され、医院の経営も安定するでしょう。
そこで今回は、「歯科衛生士の採用が難しい理由と成功する採用戦略」をご紹介します。
歯科衛生士の採用に困っている方は、ぜひ参考にしてください。
歯科衛生士の採用が難しい理由

歯科医院で歯科衛生士を採用するのは年々難しくなっています。
人材不足や業界の競争激化により、多くの医院が優秀な人材を確保するのに苦戦しているのです。
本記事では、採用が難しい具体的な理由を明らかにし、課題解決のヒントを探ります。
求職者が少ない
歯科衛生士の求職者数は年々減少傾向にあります。
歯科衛生士の資格取得者は一定数いますが、離職率の高さや他職種への転職により、採用市場に出る人材が少ないためです。
たとえば、新卒の歯科衛生士は就職先がほぼ決まっており、転職市場には経験者しか出てこないケースが多いです。
そのため、採用活動を行う際は、求職者の少なさを前提とした戦略が必要になるでしょう。
競合が多い
歯科医院の数が多く、優秀な歯科衛生士の確保が困難になっています。
歯科医院の数は年々増加しており、各医院が限られた人材を奪い合う状況になっているためです。
具体的には、都市部では駅近の人気クリニックが好条件で募集をかけるため、中小規模の医院は応募を集めにくい傾向があります。
競合の多い市場では、他院と差別化できる採用戦略が求められるでしょう。
働き方の変化
歯科衛生士の働き方に対する意識が変化し、従来の採用方法が通用しにくくなっています。
近年はワークライフバランスを重視する求職者が増え、長時間労働や厳しい勤務条件を避ける傾向が強まっているためです。
たとえば、時短勤務や週休3日制を導入する医院が増え、それに対応できない職場は応募者が減る可能性があります。
このため、採用活動では現代の働き方のニーズに適応することが重要です。
採用プロセスの未整備
採用の流れが明確でないと、求職者の応募意欲を下げる原因になります。
選考基準や面接対応が不十分だと、求職者にとって不安要素が多くなり、他院への応募を優先してしまうためです。
そのため、応募から採用決定までに時間がかかる医院では、途中で他の医院に決まってしまうケースが多く見られます。
スムーズな採用プロセスを整えることが、求職者を確保する鍵となるでしょう。
地域による人材不足
地域によっては、そもそも歯科衛生士が十分にいないことがあります。
特に地方では、都市部に比べて歯科衛生士の養成校が少なく、供給が追いついていないためです。
地方では歯科衛生士の求人を出しても応募がほとんどなく、都市部の人材を確保する工夫が必要になります。
地域ごとの人材状況を把握し、それに応じた採用施策を考えることが重要です。
歯科衛生士を採用できない医院の末路

歯科衛生士の採用に苦戦すると、医院全体の運営に深刻な影響を及ぼします。
人手不足が続けば、スタッフの負担増加やサービスの質の低下を招き、最終的には経営の悪化につながることもあります。
ここでは、歯科衛生士を採用できない医院が直面するリスクについて解説します。
スタッフの負担が増大
人手不足により、既存のスタッフに過度な負担がかかります。
歯科衛生士が不足すると、他のスタッフが業務をカバーする必要があり、業務量の増加につながるためです。
たとえば、歯科助手や受付スタッフが本来の業務に加えて診療補助を行うことで、負担が増し、ミスや疲労の蓄積が起こりやすくなります。
適切な人員配置ができなければ、スタッフの負担は増え続け、職場環境の悪化を招くでしょう。
サービスの質が低下
歯科衛生士が不足すると、医院全体のサービスの質が落ちる可能性があります。
業務の効率が悪化し、十分なケアが提供できなくなるためです。
具体的には、歯科衛生士が足りないことで患者一人あたりのケア時間が短くなり、定期メンテナンスの質が低下することがあります。
サービスの質が低下すると、患者の満足度も下がり、医院の信頼性が損なわれるでしょう。
患者数の減少
サービスの質が落ちると、患者が離れてしまうリスクが高まります。
満足度の低下や待ち時間の増加が、リピーター離れを引き起こすためです。
たとえば、予約が取りづらくなったり、治療の待ち時間が長くなったりすると、患者は他の医院へ移ってしまいます。
患者数が減少すれば、医院の収益にも大きな影響を及ぼすでしょう。
医療スタッフの離職
スタッフの負担増加が続くと、職場環境が悪化し、離職につながる可能性があります。
過度な労働負担やストレスが蓄積すると、スタッフのモチベーションが低下し、転職を考える人が増えるためです。
具体的には、残業が常態化し、休憩時間も取れない状況が続くと、スタッフの精神的・肉体的負担が限界に達しやすくなります。
離職が続けば、さらに人手不足が深刻化し、悪循環に陥るでしょう。
経営の悪化
患者数の減少やスタッフの離職が続くと、医院の経営が厳しくなります。
収益が減少し、運営コストを賄うのが難しくなるためです。
仮に、新規患者の獲得が難しくなり、既存患者の離脱も増えると、売上が低迷し、経営の安定性が損なわれます。
歯科医院の存続を考えるなら、早い段階で人材確保の対策を講じることが必要です。
成功する歯科衛生士の採用戦略

歯科衛生士の採用を成功させるためには、他院と差別化できる戦略が必要です。
求人の魅力を高め、働きやすい環境を整え、効果的な採用手法を取り入れることで、優秀な人材を確保しやすくなります。
ここでは、採用成功につながる具体的な施策について解説します。
魅力的な求人内容を作成
求職者にとって魅力的な求人情報を作ることが、応募数を増やす鍵となります。
求人の内容が曖昧だったり、条件が不明確だったりすると、求職者が不安を感じて応募を避けるためです。
たとえば、「昇給制度あり」ではなく「年1回の昇給、実績に応じて最大〇万円アップ」と明記すると、求職者にとって分かりやすくなります。
明確で魅力的な求人内容を作成し、求職者に安心感を与えましょう。
柔軟な働き方を提案
現代の求職者は、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。
固定のフルタイム勤務だけでなく、多様な働き方を用意することで、より多くの求職者を引きつけることができるのです。
たとえば、週休3日制や時短勤務制度を導入すると、家庭と仕事を両立したい求職者にも魅力的な職場として認識されやすくなります。
柔軟な勤務形態を提案することで、応募者の幅を広げることができるでしょう。
面接環境を整える
面接の雰囲気や対応次第で、求職者の印象は大きく変わります。
不慣れな面接官や緊張感の強い環境では、求職者が本来の力を発揮しづらくなるためです。
面接前に医院の雰囲気やスタッフの紹介を行い、リラックスできる環境を作ることで、求職者の本音を引き出しやすくなります。
求職者が安心して話せる面接環境を整えることが、採用成功のカギとなるでしょう。
職場環境をアピール
働きやすい環境が整っていることを積極的にアピールすることが重要です。
実際の職場の雰囲気や設備が伝わると、求職者が自分の働く姿をイメージしやすくなるためです。
例として、スタッフ同士の関係が良好であることを伝えるために、院内イベントの様子を写真付きで掲載すると、職場の魅力が伝わりやすくなります。
職場環境の良さを具体的に伝えることで、応募意欲を高めることができるでしょう。
SNSや求人サイトを活用
多くの求職者に情報を届けるためには、SNSや求人サイトの活用が欠かせません。
紙媒体の求人広告だけではリーチできる範囲が限られるため、オンラインの採用手法を取り入れる必要があります。
たとえば、Instagramで医院の日常風景を発信したり、求人サイトで動画付きの求人広告を掲載したりすると、より多くの求職者にアプローチできます。
SNSや求人サイトを活用し、効率的な採用活動を行いましょう。
歯科衛生士を集める採用サイト活用術

採用サイトを効果的に活用することで、求職者に医院の魅力を伝え、応募意欲を高めることができます。
特に、写真や動画、具体的な待遇情報を掲載することで、より多くの求職者の興味を引くことが可能です。
ここでは、歯科衛生士の採用につながる採用サイトの活用方法を解説します。
写真や動画で院内を紹介
視覚的な情報を取り入れることで、求職者が職場の雰囲気をイメージしやすくなります。
テキストだけの求人情報では伝わりにくい職場環境や雰囲気を、写真や動画を通じて具体的に示すことができるのです。
たとえば、院内の設備やスタッフの仕事風景を撮影した動画を掲載すると、求職者が「ここで働きたい」と感じやすくなります。
リアルな職場の様子を伝えることで、より多くの求職者に興味を持ってもらえるでしょう。
給与や待遇の明確化
給与や待遇の情報を分かりやすく記載することで、求職者の不安を減らすことができます。
条件が曖昧だと応募をためらう人が多いため、具体的な数字や制度を明記することが重要です。
具体的には、「月給25万円~」ではなく「基本給25万円+資格手当1万円+賞与年2回」と記載すると、求職者が実際の収入をイメージしやすくなります。
待遇を明確にすることで、安心して応募してもらいやすくなるでしょう。
スタッフの声・インタビュー
実際に働くスタッフの声を掲載することで、求職者の共感を得やすくなります。
求職者は職場のリアルな情報を知りたいと考えているため、現場のスタッフの意見が参考になるためです。
たとえば、「未経験から入職して、先輩のサポートで成長できた」などのインタビュー記事を掲載すると、求職者が働くイメージを持ちやすくなります。
スタッフのリアルな声を伝えることで、安心して応募できる環境を整えましょう。
患者様の声を掲載
患者からの感謝の声を掲載することで、医院の魅力を高めることができます。
求職者は「この医院で働くことで、どのように社会貢献できるのか」を気にするため、患者からの評価は大きな影響を与えるのです。
例として、「歯科衛生士さんが親切で、定期検診が楽しみになりました」といった声を掲載すると、働くやりがいを感じやすくなります。
患者様の声を通じて、医院の良さを伝えましょう。
応募プロセスの簡略化
応募までの手順が複雑だと、求職者のモチベーションが下がってしまいます。
簡単な手続きで応募できる仕組みを整えることで、より多くの人が応募しやすくなるためです。
たとえば、「履歴書不要・スマホで簡単応募」といった仕組みを導入すると、気軽に応募できるようになります。
応募のハードルを下げることで、より多くの求職者を集められるでしょう。
魅力的な歯科医院の採用サイト事例

優秀な歯科衛生士を採用するためには、採用サイトの作り込みが重要です。
実際に成功している歯科医院の事例を参考にすることで、自院の採用活動にも活かせるポイントが見えてきます。
ここでは、魅力的な採用サイトを運営している歯科医院の事例を紹介します。
あゆみ歯科クリニック
あゆみ歯科クリニックの採用サイトは、職場環境や教育制度の充実度が明確に伝わる構成になっています。
求職者が不安を感じるポイントを丁寧に解消し、働く魅力を具体的に示しているためです。
たとえば、どんな福利厚生があるのか番号と写真で説明しているため、視覚的にわかりやすいです。
「採用相談窓口」として、チャットボットを用意しているのも、サポートが充実している印象を与えるでしょう。
アスカル歯科
アスカル歯科の採用サイトは、院内の雰囲気やチームワークの良さが伝わる作りになっています。
求職者が「どんな職場なのか?」を知りたいと考える中で、実際のスタッフの姿を前面に出すことで安心感を与えているためです。
たとえば、スタッフ同士が協力し合う様子を写真や動画で紹介し、職場の温かみを感じられるコンテンツを充実させています。
職場の雰囲気が伝わる採用サイトは、応募意欲を高める上で有効な手段となるでしょう。
雅心会グループ
雅心会グループの採用サイトは、キャリアパスや働き方の多様性に重点を置いています。
歯科衛生士が長く働ける環境を提供していることを、具体的な制度やサポート内容を通じて明確に伝えているためです。
たとえば、復職支援や時短勤務制度について詳しく説明し、ライフステージに合わせた働き方ができる点を強調しています。
たとえば、歯科衛生士の1年目はこれ、2年目はこれと、どんなステップでキャリアを気づいていくのかが分かります。
成長を実感できる環境をアピールすることで、求職者に安心感を与えられるでしょう。
宮本歯科医院
宮本歯科医院の採用サイトは、医院の理念やビジョンがしっかりと伝わる構成になっています。
単なる待遇や福利厚生の説明ではなく、「なぜこの医院で働くべきか?」という点に重点を置いているためです。
たとえば、医院の価値観や診療方針を動画で紹介し、「ライフスタイルを大事にしたゆとりある働きかた」というメッセージを強く打ち出しています。
医院の理念に共感した求職者が集まることで、採用後の定着率向上にもつながるでしょう。
たけち歯科
たけち歯科の採用サイトは、スタッフのリアルな声や働きがいにフォーカスした作りになっています。
実際に働くスタッフを動画で掲載し、働く環境がわかりやすい作りになっているからです。
たとえば、「スタッフが語る」というインタビューコンテンツでは、先輩がなぜその医院を選んだのかがわかりやすく紹介されています。
実際のスタッフの声を前面に出すことで、求職者の不安を解消し、応募のハードルを下げる効果が期待できるでしょう。
歯科衛生士の採用に関する疑問

歯科衛生士の採用を進める中で、さまざまな疑問や課題に直面することがあります。
ここでは、採用担当者がよく抱く疑問に対して具体的な解決策を解説します。
Q.採用活動の時間がない場合はどう対処すべき?
採用活動に割ける時間がない場合は、効率的な採用手法を活用することが重要です。
採用プロセスを簡略化し、時間をかけずに候補者とマッチングできる仕組みを整えるためです。
例として、求人サイトの自動応募管理機能を活用したり、オンライン面談を導入することで、採用担当者の負担を軽減できます。
忙しい中でも効果的な採用活動を行うために、デジタルツールを積極的に活用しましょう。
Q. 歯科衛生士の業務内容をどこまで伝えるべき?
求人情報では、業務内容を具体的かつ明確に伝えることが大切です。
業務の詳細が不透明だと、求職者が不安を感じ、応募をためらう原因になるためです。
たとえば、「スケーリングやTBI(ブラッシング指導)だけでなく、アシスタント業務や受付対応もお願いする場合があります」といった具体的な説明を記載すると、入職後のギャップを減らせます。
採用後のミスマッチを防ぐためにも、業務範囲を正確に伝えましょう。
Q. 採用担当者は誰が適任か?
採用担当者には、医院の方針を理解し、求職者と円滑にコミュニケーションが取れる人が適任です。
求職者が安心して応募できるよう、医院の雰囲気や業務内容を正しく伝える役割が求められるためです。
たとえば、院長や人事担当者だけでなく、実際に働く歯科衛生士が採用担当を兼任することで、現場のリアルな声を伝えやすくなります。
求職者との相性を見極めるためにも、適任者を選びましょう。
Q. 面接で重要視すべきポイントは?
面接では、求職者の技術力だけでなく、医院との相性や人柄も重視することが大切です。
技術面は研修で補えることが多いため、長期的に活躍できる人物かどうかを見極めることが重要だからです。
具体的には、「チームワークを大切にできるか」「患者さんとのコミュニケーションを意識しているか」といった点を質問すると、医院に合う人材を選びやすくなります。
スキルだけでなく、医院の雰囲気に合う人材を見極めましょう。
Q. 採用後の定着率を高める方法は?
採用後の定着率を高めるには、働きやすい環境を整え、適切なフォローを行うことが重要です。
職場に馴染めなかったり、仕事に対する不安が解消されないと、早期退職につながるためです。
具体的には、入職後1~3ヶ月の間に定期的な面談を実施し、悩みや課題を相談できる場を設けることで、定着率が向上します。
安心して働ける環境を整えることで、スタッフの定着率を上げることができるでしょう。
Q. 地方ではネットよりアナログの方が効果的か?
地方では、ネットだけでなく、アナログな採用手法も有効です。
地方の求職者は、地域の口コミや紹介を重視する傾向があるため、ネット求人だけではリーチしきれない層がいるためです。
たとえば、歯科衛生士学校との連携や、地域の求人情報誌への掲載、知人・スタッフからの紹介制度を活用することで、より多くの求職者にアプローチできます。
地域に応じた採用手法を組み合わせることで、より効果的な採用活動が可能になるでしょう。
Q. 新しい人材が入った際の給与調整はどうするべき?
新しい人材の給与調整は、既存スタッフとのバランスを考慮しながら、公平な基準で決定することが重要です。
新規採用者の給与が既存スタッフより高いと、不満が生じ、職場のモチベーションが低下する可能性があるためです。
たとえば、「経験3年以上は基本給25万円以上」「未経験者は試用期間中23万円」といった基準を設け、既存スタッフにも納得感のある形で調整すると、トラブルを防げます。
給与体系を明確にし、公平な評価制度を導入しましょう。
まとめ
歯科衛生士の採用は、求職者の減少や競争の激化、働き方の変化などの要因によって年々難しくなっています。
採用がうまくいかないと、スタッフの負担が増し、サービスの質の低下や経営の悪化につながるリスクもあります。
しかし、適切な採用戦略を実施することで、優秀な歯科衛生士を確保し、医院を安定させることが可能です。
魅力的な求人内容の作成や柔軟な働き方の提案、面接環境の整備などを行い、求職者に選ばれる医院を目指しましょう。
また、採用サイトを活用し、写真や動画を用いた院内の紹介、給与や待遇の明確化、スタッフの声の掲載などを工夫することで、求職者の安心感を高めることができます。
採用活動は継続的な取り組みが必要ですが、適切な施策を実施すれば、安定した人材確保が可能になります。
自院に合った方法を取り入れながら、より良い採用を実現していきましょう。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...