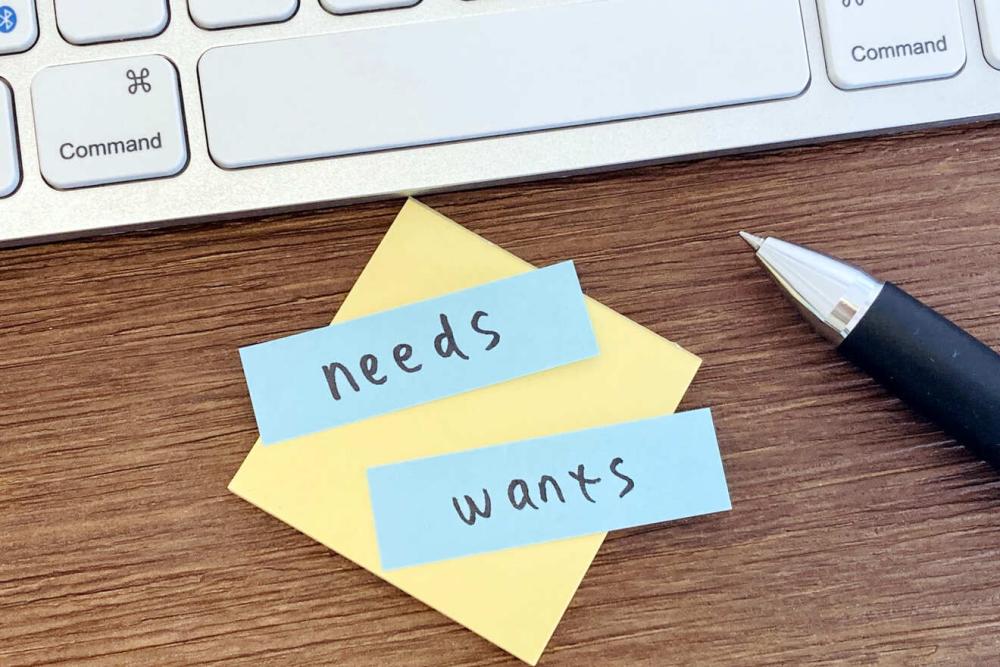採用力が変わる!共感を生む事業紹介の作り方

採用サイトに掲載する事業紹介は、何を書けばいいのか悩ましいですよね。
伝え方を間違えると応募者に響かないし、かといって抽象的すぎても「結局何の会社?」と思われてしまいます。
できることなら、自社の強みや魅力がしっかり伝わるようにしたいですよね。
実は、いくつかのポイントを押さえるだけで、事業内容を効果的に伝えることができます。
事業紹介が明確になれば、意図しない応募者が来ることもありません。
そこで今回は、「採用サイトにおける効果的な事業紹介の作り方」をご紹介します。
魅了的な事業紹介をし、採用活動の成果にもつながるようにしましょう。
採用活動における事業紹介の役割

採用活動において事業紹介は、企業と求職者をつなぐ重要なコンテンツです。
自社が社会の中でどのような存在であるかを伝えることで、共感や興味を引き出すことができます。
採用の成果を左右する要素として、事業紹介は単なる説明を超えて、企業の「顔」としての役割を果たします。
何をしている会社か伝わる
自社の事業内容を紹介することで、求職者にとって「どんな会社か」を具体的に理解してもらえます。
採用サイトを訪れた人が最も知りたいのは、自分がどんな仕事に携わることになるのかをイメージできる情報だからです。
たとえば、「IT企業です」とだけ書かれていても、システム開発なのかアプリ制作なのかは分かりません。
一方、「中小企業向けに業務効率化アプリを開発しています」と記載すれば、一気に理解が深まります。
自社の活動をシンプルに伝えることで、関心を持たれるきっかけになるでしょう。
志望動機を引き出す材料になる
事業内容を丁寧に伝えることで、求職者が自身の価値観や経験と照らし合わせた志望動機を持ちやすくなります。
企業が何を目指しているのかを知ることで、自分がその中でどう貢献できるかを考える材料になるためです。
具体的には、「地方の雇用創出に貢献する事業を展開しています」と記載すれば、「地元に貢献したい」という動機を持つ人の心に響きやすくなります。
求職者が自然に自分の想いと結びつけられるような情報があると、採用の質にもつながりやすくなるでしょう。
誤解やミスマッチを防ぐ
事業紹介を通じて、業務内容や方向性を明確にすることで、入社後のミスマッチを減らす効果があります。
情報があいまいなままだと、求職者が勝手なイメージで応募する可能性があるからです。
例として、「安定企業」とだけ紹介されていても、実際にはベンチャー気質の成長企業だった場合、ギャップにより早期離職を招くリスクが高まります。
事前に現実とのズレを防ぐことで、より良いマッチングにつながるはずです。
企業の信頼性を高める
しっかりとした事業紹介は、企業の透明性や信頼性を高める効果があります。
外部に向けて自社の取り組みや社会的役割を丁寧に説明する姿勢が、誠実さとして伝わるためです。
たとえば、実績や数字を交えて事業内容を紹介していれば、「この会社は本当に事業をしっかり運営している」と感じてもらいやすくなります。
信頼されることで、応募のハードルも下がりやすくなるでしょう。
他社との差別化につながる
自社独自の事業や取り組みを紹介することは、他社との差別化に直結します。
求職者が複数の企業を比較する中で、どこに個性や魅力を感じるかが選択の基準になるためです。
たとえば、「業界で唯一、○○に特化したサービスを展開」といった情報があると、記憶にも残りやすくなります。
他社とは違う視点を提示することで、選ばれる理由を明確にできるでしょう。
採用サイトにおける事業紹介の基本構成

採用サイトで効果的に事業紹介を行うには、一定の構成に沿って情報を整理することが重要です。
求職者が理解しやすく、共感しやすい形で事業の全体像を伝えることで、応募意欲を高めることができます。
各項目を段階的に伝えることで、企業の魅力がより立体的に伝わるでしょう。
事業の概要
事業の概要は、自社がどのような分野でどんなサービスや製品を提供しているかを簡潔に伝える役割があります。
最初に全体像を示すことで、求職者がその企業の「主軸」を理解できるようになるのです。
たとえば、「飲食業界向けにPOSレジシステムを提供するSaaS企業」といった紹介があれば、業種と事業内容が一目で把握できます。
まずは端的に自社の事業を表現することで、関心の入口をつくるようにしましょう。
事業の目的・背景
事業の目的や立ち上げの背景を明示することで、企業の理念や価値観を伝えることができます。
単なる営利活動ではなく、社会課題や市場ニーズに応えるための取り組みであることを示すことで、共感を得やすくなるためです。
具体的には、「地方の医療格差を解消したいという想いから、遠隔診療アプリを開発」といった背景を語れば、志のある求職者の心を打ちやすくなります。
事業の原点を示すことで、企業の信念や文化が伝わりやすくなるでしょう。
ターゲットと提供価値
どのような顧客層に向けて、どんな価値を提供しているのかを明確にすることで、事業の意義がより深く理解されます。
顧客視点での価値が整理されていれば、求職者は自分の仕事が社会にどう貢献するかをイメージしやすくなるためです。
たとえば、「中小製造業の在庫管理課題を解決するクラウドシステムを提供」といった説明があれば、課題と解決策がはっきりと伝わります。
提供価値を明確にすることで、応募者の納得感も高まりやすくなるのです。
他社との違い
他社と比較して、どこに強みや独自性があるのかを伝えることで、自社を選ぶ理由を与えることができます。
求職者が他社との違いを知ることで、「自分はなぜこの会社を選ぶのか」を言語化しやすくなるためです。
たとえば、「業界最短の導入期間で提供できるサポート体制がある」など、具体的な差別化ポイントを示すことで、印象に残りやすくなります。
自社の特徴を際立たせることで、競合との比較の中でも魅力を感じてもらえるでしょう。
今後の展望
将来的な事業の方向性や成長戦略を伝えることで、企業の可能性やビジョンを共有できます。
企業の未来に共感した人材ほど、長期的に貢献しようという意識を持ちやすくなるためです。
具体的には、「今後は東南アジア市場への進出を計画しており、グローバル展開を見据えた採用を強化中」といった情報があれば、前向きな企業イメージを持ってもらえます。
成長に意欲的な姿勢を示すことで、挑戦を歓迎する人材を惹きつけやすくなるでしょう。
魅力的な事業紹介を作る5つのコツ

採用サイトにおける事業紹介は、ただ情報を並べるだけでは求職者の心に響きません。
読み手が「ここで働きたい」と感じるためには、内容の見せ方や伝え方に工夫が必要です。
以下の5つのポイントを意識することで、伝わる・記憶に残る事業紹介に仕上げることができるでしょう。
ストーリー性を持たせる
事業紹介にストーリー性を加えることで、読んだ人の記憶に残りやすくなります。
物語としての流れがあると、読み手が感情的につながりを感じやすくなるためです。
たとえば、「創業時の課題→挑戦→現在の成果」という流れで紹介すれば、企業の成長や信念がリアルに伝わります。
一貫したストーリーを意識して構成することで、企業の魅力を印象づけやすくなるでしょう。
誰にでも伝わる表現にする
事業紹介では専門用語を避け、誰でも理解できる言葉で表現することが重要です。
採用サイトを見るすべての人が、業界知識を持っているとは限らないためです。
具体的には、「API連携による業務効率化」ではなく、「複数のシステムを自動でつなぐことで、仕事をスムーズに進められる仕組み」といった説明の方が伝わりやすくなります。
幅広い読者に理解される表現を使うことが、共感と納得につながります。
写真や動画を活用する
事業の現場や雰囲気をビジュアルで伝えることで、文字情報だけでは伝わらない魅力を補うことができます。
視覚的な情報が感情に訴える効果を持ち、理解や印象に残りやすくなるためです。
たとえば、実際に商品を開発している様子や、社員が働いているシーンの写真や動画を掲載することで、事業のリアリティが伝わります。
言葉だけでなく視覚要素を組み合わせることで、理解と信頼を得られやすくなるでしょう。
顧客や社員の声を取り入れる
第三者の視点を加えることで、事業の信頼性や説得力が高まります。
実際に関わっている人の声は、企業が自ら発信する情報よりも客観性があると受け取られるためです。
具体的には、「このサービスのおかげで業務が楽になった」「この事業に誇りを持っている」といった顧客や社員の声を載せることで、事業の価値が伝わります。
リアルな体験談があることで、読み手の共感を引き出しやすくなるでしょう。
短くまとめて要点を絞る
情報を詰め込みすぎず、要点を絞って簡潔に伝えることが読みやすさにつながります。
情報が多すぎると読み手が混乱したり、途中で離脱してしまう可能性があるためです。
たとえば、1つの事業紹介を500字以内で要点だけまとめることで、すぐに全体像をつかんでもらえます。
短く・わかりやすくまとめることが、読んでもらえるコンテンツ作成の基本と言えるでしょう。
採用サイトで事業紹介する際の注意点

採用サイトにおける事業紹介では、魅力を伝えることに加えて「読みやすさ」や「誤解のなさ」も重要です。
伝えたい情報を正しく届けるためには、読み手の視点に立って内容を整理し、表現方法に気を配る必要があります。
以下に注意すべきポイントを紹介します。
専門用語は控えめにする
専門用語の多用は、読み手の理解を妨げる原因になります。
業界経験のない求職者にとっては、知らない言葉が続くと読む意欲が下がってしまうためです。
たとえば、「SaaS」「API」「UI/UX」といった言葉を使う場合は、「ソフトウェアを貸し出す仕組み」「システム同士をつなぐ仕組み」「使いやすさと見た目のデザイン」といった説明を添えることが効果的です。
誰にとっても理解しやすい言葉を選ぶことを意識してください。
長文や抽象的な表現は避ける
読み手にとって負担となる長文や、意味があいまいな表現は、事業の魅力を伝える妨げになります。
文章が長すぎたり抽象的すぎたりすると、情報の要点がつかみにくくなるためです。
具体的には、「我々は社会に貢献する企業です」といった抽象表現よりも、「地域の小学校に学習支援を提供しています」のように、行動レベルで表現したほうが伝わりやすくなります。
端的かつ具体的な表現を心がけて、読み手に負担をかけないようにしましょう。
実績ばかり並べすぎない
事業紹介で実績を紹介することは大切ですが、数値や実績だけを並べすぎると、読み手の関心を引きにくくなります。
求職者は「すごい会社」よりも「自分が関われる会社」に興味を持つからです。
たとえば、「導入社数2,000社突破」「売上前年比150%」といった数字に加えて、「今後さらにチームを拡大し、顧客サポートを強化予定」といった情報を加えることで、より身近な印象を与えることができます。
数字とストーリーのバランスを意識するとよいでしょう。
現在だけでなく未来も語る
現状の説明に終始してしまうと、企業の可能性や発展性が伝わらず、求職者の興味を引きにくくなります。
多くの求職者が「この会社で自分がどんな未来を描けるか」を重視しているためです。
たとえば、「今は国内での導入を拡大中ですが、今後は海外展開も視野に入れています」といった未来志向の情報を含めると、前向きな印象を与えることができます。
将来のビジョンを語ることで、共に成長したいと感じる応募者を引きつけやすくなるでしょう。
ビジュアル表現も意識する
文章だけで情報を伝えようとすると、読み手の集中力が続かず、離脱を招く恐れがあります。
視覚情報のほうが瞬時に理解でき、興味を惹きやすいためです。
たとえば、「開発の様子を写真で紹介」「チャートでサービスの仕組みを図解する」といった工夫により、複雑な内容もわかりやすくなります。
適切なビジュアル表現を加えることで、コンテンツの魅力と伝達力が一段と高まるでしょう。
事業紹介コンテンツに関するよくある疑問

採用サイトで事業紹介を作成する際、多くの企業が悩みがちなポイントがあります。
どこまで詳しく書くべきか、複数の事業がある場合の構成、新規事業の扱いなど、判断に迷うことも多いでしょう。
ここでは、よくある疑問に対して実践的なヒントをお伝えします。
Q.事業紹介はどこまで詳しく書くべき?
事業紹介は理解しやすい範囲で要点を押さえ、求職者に必要な情報を届ける程度の詳細さが求められます。
すべてを詳しく説明しすぎると冗長になり、逆に読み手の関心を失ってしまうためです。
たとえば、「何をしている事業か」「誰の役に立っているか」「今後どうなるか」を簡潔にまとめ、詳細は別ページやリンクで補足する方法が有効です。
読み手が必要な情報を無理なく受け取れるようなボリューム感を意識しましょう。
Q.事業内容が複数ある場合はどうする?
事業が複数ある場合は、それぞれの特徴を簡潔に分けて紹介し、全体像が伝わる構成にするのが望ましいです。
なぜなら、ひとつにまとめすぎると読み手にとって混乱を招くおそれがあるためです。
たとえば、「●●事業:中小企業向けのITサポート」「▲▲事業:自治体向けのデジタル支援」など、見出し付きで分けて整理すると、読み手がスムーズに理解できます。
事業ごとの違いがはっきり伝わる構成を心がけてください。
Q.新規事業や成長中のサービスも紹介すべき?
新規事業や成長中のサービスも、積極的に紹介することで企業の挑戦姿勢や将来性を示せます。
求職者の多くが「成長企業かどうか」「変化を楽しめるか」といった視点を重視しているためです。
たとえば、「今年立ち上げた●●事業は現在準備段階ですが、今後注力分野として育てていきます」といった形で紹介すれば、現時点での進捗と意気込みが伝わります。
未完成であっても方向性を示すことで、共感を得やすくなるでしょう。
Q.既存の営業資料や会社案内を流用してもいい?
営業資料や会社案内をそのまま流用するのは避け、採用目線で再構成する必要があります。
それらの資料は取引先向けの内容であり、求職者には伝わりにくい表現や重点が含まれているからです。
たとえば、「売上実績」「市場シェア」などの情報に偏っている資料は、「誰の役に立ち、どんな価値を提供しているか」といった観点で言い換えると効果的です。
資料を用意する際は、求職者に届く言葉で再編集する意識が大切です。
Q.応募者が本当に読んでくれているのか不安
求職者が事業紹介を読んでいるかどうか不安になるのは当然ですが、内容次第で閲覧率は大きく変わります。
求職者は応募の判断材料として、企業の事業内容を重視している傾向があるからです。
たとえば、スマートフォンでも見やすいデザインや、見出しで内容が整理された構成、要点を押さえた簡潔な文章を心がけることで、読まれる可能性が高まります。
読みやすさを重視した設計にすることで、自然と目を通してもらえるようになるでしょう。
REACH-PLUSなら事業紹介も作りやすい
当サイトで提供している採用管理システム「REACH-PLUS」には、簡単に事業紹介をする機能が実装されています。
「ビジネス」という機能名で、タイトルや本文をブログ感覚で入力することができます。
たとえば、「地域密着型の配送サービス」「サブスク型の清掃事業」など、事業ごとにページを分けて紹介できるため、複数の事業を展開している企業にも最適です。
「REACH-PLUS」で作成した事業紹介は採用ページ内に自動で反映され、応募者が他の情報と一緒にスムーズに閲覧できる設計になっています。
他の採用ツールでは見落とされがちな「事業の見せ方」に特化しているのが、REACH-PLUSの大きな特長です。
自社の事業をわかりやすく発信したいという企業様は、ぜひ導入をご検討ください。
まとめ
採用サイトにおける事業紹介は、単なる説明ではなく、自社の魅力を伝える重要なコンテンツです。
「何をしている会社か」「どんな価値を届けているのか」「今後どこを目指すのか」を明確にすることで、志望動機を引き出し、ミスマッチを防ぎ、信頼性や他社との差別化にもつながります。
ストーリー性や視覚表現、分かりやすい言葉選びも意識しながら、求職者にとって理解しやすく魅力的な内容を目指してください。
複数事業や新規事業がある場合も、適切に構成すれば、自社の多様性や成長性を伝えるチャンスになります。
採用活動をより効果的に進めるためにも、事業紹介を丁寧に見直し、未来を共に創る仲間との出会いを後押しできるコンテンツにしていきましょう。
関連記事
-

採用サイトの社長メッセージはどう作る?作り方と例文を徹底解説
採用サイトに載せる社長メッセージは、何を書けば良いのか悩みますよね。内容が抽象的すぎたり、他社と似たり寄ったりになってしまいます。そこで今回は、「採用サイトに載...
-

採用サイトで1日のスケジュールを掲載するメリット・デメリット
社員の働き方を紹介する「1日のスケジュール」というコンテンツ。企業文化が伝わりやすくなる一方で、何を掲載すればよいか悩む気持ちわかります。そこで、「採用サイトに...
-

採用ウェビナーとは?メリット・デメリットと注意点を解説
-

採用イベントとは?メリット・デメリットと成功のポイントを紹介
優秀な人材を確保するためには、採用イベントの実施がおすすめです。採用イベントでは、企業が求めるスキルや経験を持つ候補者と直接会い、交流することができます。
-

採用サイトのエントリーフォームとは?作り方と成功の秘訣を紹介
採用活動において、採用サイトのエントリーフォームは非常に重要なコンテンツです。エントリーフォームがあることで、応募者のデータを効率的に集めることができ、採用のミ...