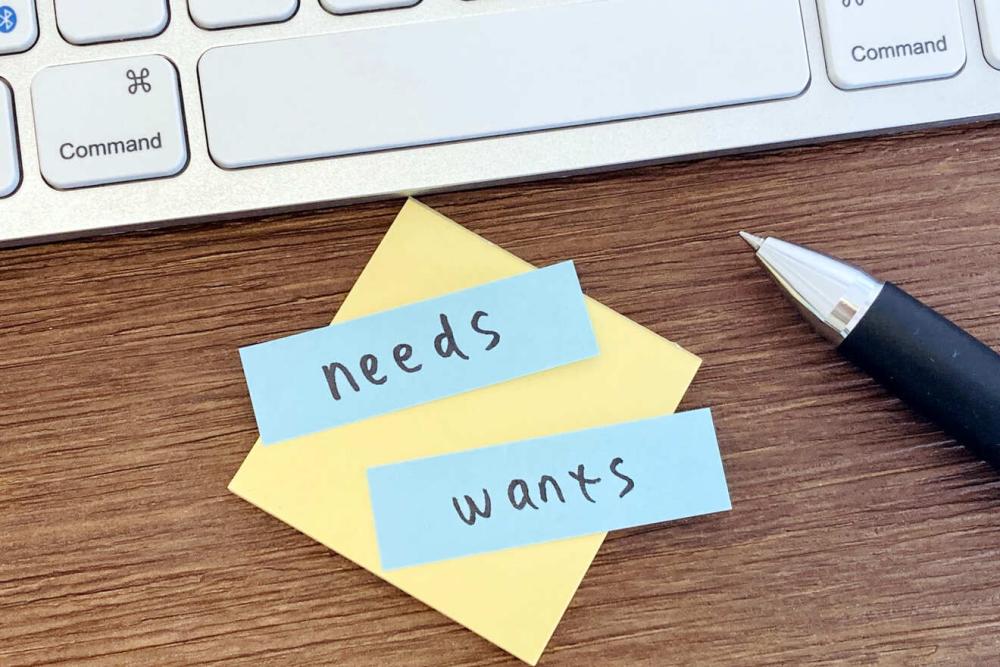求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例

採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。
抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。
できることなら、応募者に「この会社に合いそうだ」と思ってもらえるような表現にしたいですよね。
実は、いくつかのポイントを押さえることで、自社の「求める人物像」をスムーズに言語化できます。
人物像の打ち出し方が明確になれば、採用のミスマッチにはなりません。
そこで今回は、「採用サイトに適した『求める人物像』の書き方」をご紹介します。
人物像の伝え方が具体的かつ魅力的なら、応募者の質も採用の精度も大きく変わってくるでしょう。
採用サイトに「求める人物像」が必要な理由

自社の採用活動を効果的に進めるためには、「求める人物像」を明確にしてサイトに掲載することが重要です。
人材とのミスマッチを防ぎ、理想の応募者を引き寄せる第一歩となるからです。
まずは、採用サイトに「求める人物像」が必要な理由を見ていきましょう。
採用活動に一貫性が出る
採用サイトに「求める人物像」を明記することで、採用活動全体に統一感が生まれます。
求める人物像を掲載することで、企業が必要な人材の基準が明確になるためです。
たとえば、採用ページで「主体性のある人材」を求めていると打ち出すことで、求人広告や面接の質問内容もそれに沿った内容に調整されます。
採用活動の方針がブレず、組織としての採用力を高められるでしょう。
応募者の関心を引きつける
求める人物像があることで、応募者は自分との相性を判断しやすくなります。
求める人物像を見て、その企業で働く姿を想像しやすくなるためです。
例として、「チャレンジ精神を歓迎する職場です」と記載すれば、自発的に行動するタイプの人の関心を集めやすくなります。
自分に合う職場だと感じた応募者だと、応募意欲が高まるでしょう。
選考基準を明確にできる
求める人物像を定義することで、選考の判断基準を明確にできます。
何をもって“良い人材”とするかの基準が、社内で共有できるためです。
具体的には、「協調性を重視する」とあらかじめ示しておけば、面接官もその要素を意識して質問や評価を行うことができます。
曖昧な評価を避け、公平な採用につながるでしょう。
自社の価値観を伝えられる
求める人物像は、企業の価値観や文化を反映する重要なコンテンツです。
どのような人物を評価するかは、その企業が何を大切にしているかを表すからです。
たとえば、「お客様第一で考えられる人」といった表現には、顧客志向の文化がにじみ出ます。
求める人物像は、企業の姿勢を応募者に伝える有効な手段といえるでしょう。
採用のミスマッチを防げる
求める人物像を提示することで、入社後のミスマッチを減らすことが可能です。
求める人物像があることで、応募者が事前に企業との相性を確認できるためです。
たとえば、「スピード感を持って仕事を進められる人」と明記すれば、ゆったりした環境を求める人は応募を控えるかもしれません。
結果的に、入社後の早期離職リスクを抑えられるでしょう。
求める人物像を伝える際のポイント

求める人物像はただ掲載するだけでなく、「どのように伝えるか」が重要です。
伝え方ひとつで、企業の魅力や信頼感が大きく変わってきます。
具体的な希望を伝える
抽象的な表現ではなく、具体的な資質や行動を示すことで、応募者の理解度が深まります。
明確なイメージを持たせることで、応募の判断材料になるためです。
たとえば、「リーダーシップがある人」ではなく「小さなチームをまとめて成果を出した経験がある人」と書くことで、応募者は自分の経験と照らし合わせやすくなります。
具体的な希望を伝えることで、誰に向けての採用かが伝わりやすくなるでしょう。
実際の社員とつなげる
実際に働いている社員の紹介と「求める人物像」をリンクさせることで、説得力が増します。
なぜなら、現場で活躍する社員が具体例になるためです。
例として、「柔軟な対応力がある人」と求めるなら、その特徴を持つ社員のインタビューや一日の業務内容を紹介するとイメージが明確になります。
リアルな情報を届けることで、応募者の納得感を得られるでしょう。
経営者の想いとリンクさせる
企業が掲げるビジョンや経営者の考えと「求める人物像」をつなげると、企業の方向性が伝わりやすくなります。
経営者の想いとリンクさせることで、企業の将来が想像できるからです。
たとえば、「新しい価値を創造できる人材が必要」と記載する際に、経営者が語る「変化に挑戦する企業文化」とセットで伝えると、説得力が強まります。
企業の理念に共感する人材を惹きつけやすくなるでしょう。
あえて合わない人も伝える
自社に合わないタイプをあえて明示することで、採用のミスマッチを防げます。
誰にでも合う職場は存在しない、明確に線引することは大切です。
仮に、「決まった業務だけをしたい人には向かないかもしれません」と伝えることで、受け身な姿勢の人の応募を抑制できます。
ネガティブに見える情報も、結果的には企業と応募者の双方にとってプラスになるでしょう。
採用ページ全体で一貫させる
「求める人物像」は採用ページ全体のメッセージとして、一貫性を持たせる必要があります。
異なるメッセージが混在すると、応募者に混乱を与えるためです。
たとえば、人物像では「主体性」を求めているのに、社員紹介では「指示に従う力」が強調されていると矛盾が生まれます。
採用サイトでは、コンテンツ全体の方向性をそろえて発信することが大切です。
採用サイトに適した求める人物像の作り方

求める人物像を効果的に伝えるためには、感覚的ではなく、戦略的に設計することが求められます。
構築のプロセスを明確にすることで、伝わりやすさが格段に高まります。
ペルソナを作って人物像を言語化
理想の応募者像を「ペルソナ」として設定することで、具体的な人物像を言葉で明確にできます。
ターゲットとなる人材の特徴を細かくイメージすることで、抽象的な表現に陥るのを防ぐためです。
例として、「25歳、前職では小売店で副店長を経験。チームマネジメントと顧客対応に強みがある」などの詳細なプロフィールを作ることで、文章にリアリティが生まれます。
ペルソナがあれば、採用ターゲットに近い人物像を正確に伝えやすくなるでしょう。
求める人物像に近い社員を紹介
実在する社員の紹介を通じて、求める人物像をよりリアルに伝えられます。
抽象的な言葉だけでは伝わりにくい内容も、実例を通じて共感を得られるためです。
たとえば、「人との信頼関係を大切にできる人」を求めている企業が、社内で信頼を集めている社員のインタビューを掲載すると、その人物像がより具体的になります。
応募者は自分が活躍できるかどうかをイメージしやすくなるでしょう。
動画で社内の雰囲気を伝える
動画を活用すれば、職場の空気感や社員の人柄を視覚と聴覚で直感的に伝えられます。
テキストだけでは伝えきれない雰囲気をリアルに届けられるためです。
たとえば、実際の業務風景や座談会の様子を映した動画は、社内の価値観や人間関係のあり方を自然に伝えてくれます。
応募者の企業理解が深まり、ミスマッチ防止にもつながるでしょう。
イラストや図解で視覚的に見せる
イラストや図解を使うことで、「求める人物像」の要素をわかりやすく伝えられます。
文章では伝わりにくい情報も、視覚的に整理されることで印象に残りやすくなるためです。
たとえば、「行動力・協調性・論理的思考力」といった3つの要素をピラミッド型に配置した図を使うと、重要度の違いやバランスが一目で伝わります。
イラストや図解は、読み手の理解を助ける手段として効果的です。
OK・NGの行動例で具体化する
求める人物像を明確にするには、具体的な「OK・NG行動例」を示す方法が有効です。
どのような振る舞いが評価されるのかが、具体的に伝わるためです。
例として、「OK:顧客からの要望に即対応し、社内で情報共有を徹底する」「NG:一人で抱え込み、問題を報告しない」といった例を挙げることで、応募者は自分の行動傾向と照らし合わせて判断できます。
具体例を示せば、行動レベルでの理解が深まりやすくなるでしょう。
求める人物像を伝える際のよくある失敗例

求める人物像を伝える際には、よくある誤りに注意する必要があります。
伝え方を間違えると、応募者との認識にズレが生じ、採用の精度が低下する恐れがあります。
抽象的すぎて伝わらない
「明るい人」「やる気のある人」など、抽象的な表現だけでは人物像が曖昧になります。
応募者が自分をその人物像に当てはめることが難しくなるためです。
たとえば、「明るい人」ではなく「笑顔でお客様と積極的に会話ができる人」と具体的に表現すれば、どのような行動が期待されているかが伝わります。
人物像の紹介は、求める姿を具体的に描写することが大切です。
実際の職場とかけ離れている
理想ばかりを追求し、実際の職場環境と合致していない人物像を掲げるのは問題です。
入社後に「話が違った」と感じさせる原因になるためです。
たとえば、チームで協力する文化が根付いていないのに「チームワークを大切にできる人」と記載すると、入社後にミスマッチが起こりやすくなります。
求める人物像を描くのであれば、現場の実情と乖離しないよう注意が必要です。
同じような言葉の繰り返し
似た表現ばかりを並べると、人物像の多様性や魅力が薄れてしまいます。
内容が重複することで、応募者にとって印象に残りにくくなるためです。
例として、「積極的に行動できる人」「主体的に動ける人」「自ら動ける人」といった表現は、言い回しが違うだけで本質的には同じ意味です。
同じような言葉は避け、各項目に明確な違いと意図を持たせるようにしましょう。
良いことしか書かない
求める人物像を美化しすぎると、応募者にとって現実味のない内容になりがちです。
自分には当てはまらないと感じて、応募をためらう原因になるためです。
たとえば、「前向きで行動力があり、リーダーシップがある人」など理想ばかりを並べると、かえって遠ざかってしまう可能性があります。
求める人物像では、バランスの取れた記述を心がけることが重要です。
実例やエピソードがない
実際の社員や業務のエピソードがないと、人物像に具体性が欠けてしまいます。
読み手がイメージを持ちにくく、印象に残らないためです。
たとえば、「成長意欲が高い人」と書くだけでは抽象的ですが、「毎月の勉強会に欠かさず参加し、資格取得を目指す社員が多い」といった実例を添えると説得力が増します。
実例やエピソードを入れ、人物像にリアルな輪郭を持たせる工夫が求められます。
業種別:求める人物像の書き方・例文

業界ごとに求められる人物像は大きく異なります。
業種の特性や職場環境に合った表現で伝えることで、的確な人材の応募を促すことができます。
IT・Web業界
IT・Web業界では、変化の早い環境に適応できる柔軟性や、自ら学び続ける姿勢が重視されます。
技術力だけでなく、チームでの開発に必要なコミュニケーション能力も重要な要素となるためです。
たとえば、新しいフレームワークに関心を持ち、自ら検証や提案ができる人材は、現場でも即戦力として期待されます。
IT・Web業界に適した人物を明確にすることで、意欲の高い人材からの応募を期待できるでしょう。
例文)
「変化を恐れず、技術への好奇心と探求心を持ち続ける方を求めています。チームワークを尊重し、互いに協力しながら新しい価値創造に情熱を注げる方、自ら課題を発見し解決に向けて主体的に行動できる方を歓迎します。共に成長し、未来を切り拓きましょう。」
介護・福祉業界
介護・福祉業界では、思いやりや傾聴力といった人間性が最も重視されます。
専門知識やスキルよりも、人に寄り添う姿勢や誠実さが信頼関係を築く鍵になるためです。
たとえば、高齢者の話に丁寧に耳を傾け、気持ちに共感できる人材は、現場での安心感にもつながります。
現場で求められる価値観に基づいて人物像を設計することが重要です。
例文)
「利用者一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、相手の立場に立って行動できる方を歓迎します。心のこもったコミュニケーションを大切にし、チームで支え合いながら利用者の安心と笑顔を守る姿勢を持った方と一緒に働きたいと考えています。」
飲食・サービス業
飲食・サービス業では、接客力や気配り、状況判断力が求められます。
お客様の満足度を高めるためには、常に相手の立場で考え、柔軟に対応できることが必要なためです。
たとえば、混雑時でも冷静に笑顔で対応できるスタッフは、お店の印象を大きく左右します。
実際の接客現場で活躍できる人物像を意識して表現しましょう。
例文)
「お客様の気持ちを先回りして考え、笑顔で丁寧な対応ができる方を求めています。状況に応じて臨機応変に行動し、仲間と協力して店舗運営を円滑に進められる方、そしてサービスを通じて人を喜ばせることにやりがいを感じられる方を歓迎します。」
建設・設備業
建設・設備業では、安全意識と責任感、そしてチームでの連携力が重要視されます。
現場の作業は常に危険と隣り合わせであるため、丁寧で確実な行動が求められるためです。
たとえば、安全確認を徹底し、周囲と連携して作業を進められる人物は、事故のない現場づくりに貢献します。
業務特性に合った堅実な人物像を提示することが大切です。
例文)
「安全を最優先に考え、仲間との報連相をしっかり行える方を歓迎します。現場では小さな確認を怠らず、丁寧な作業を積み重ねる姿勢が求められます。責任感を持って仕事に取り組み、協力し合いながら質の高い施工を目指せる方と共に成長したいと考えています。」
小売・販売業
小売・販売業では、コミュニケーション能力と観察力、そして提案力がカギとなります。
お客様のニーズをいち早く察知し、最適な商品を提案できる力が成果に直結するためです。
たとえば、お客様の服装や表情から好みを読み取り、適切な提案ができるスタッフは売上にも貢献できます。
現場に即した実践的な人物像を描くようにしましょう。
例文)
「お客様一人ひとりのニーズをくみ取り、最適な商品を提案できる方を求めています。明るく前向きな接客ができる方、商品の魅力を自分の言葉で伝えられる方、そしてチームで協力しながら売場づくりに参加できる方と働きたいと考えています。」
参考になる「求める人物像」のサイト事例
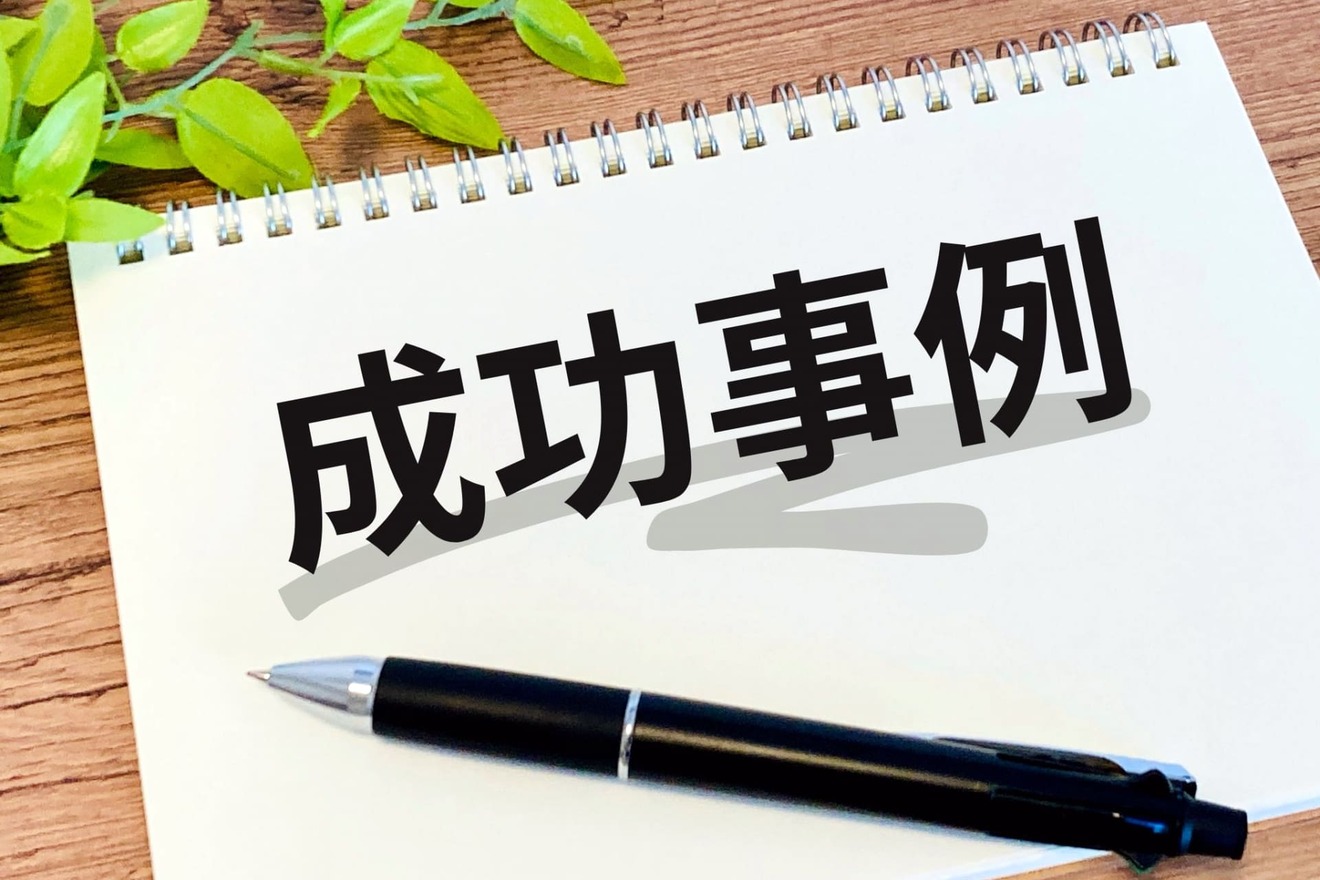
採用サイトにおける「求める人物像」の記載は、企業の価値観や文化を反映し、応募者とのマッチングを図る重要な要素です。
そこで、各企業がどのような人物像を掲げているかを紹介します。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車は「モノづくりは人づくりから」という理念のもと、実務力を活かし、自ら課題を見つけ解決策を提案できる人物を求めています。
変化を恐れず挑戦し続ける姿勢が重要視され、関係者との協力を通じて業務改善を推進できる人材が必要とされています。
特に、自らの考えを具現化する能力と周囲を巻き込む力が評価されます。
高い実務能力と変化に柔軟に対応できる姿勢が求められ、周囲との協力で大きな変革を成し遂げる力が重要です。
参考:人材育成|トヨタの環境|新卒採用情報|トヨタ自動車株式会社
コクヨ株式会社
コクヨは「こだわる・工夫する」「楽しむ・面白がる」「誠実である・チームで協業していく」の3つのキーワードを基に、個性豊かなアイデアを実現し、前向きに挑戦し続ける人物像を描いています。
新しい取り組みに積極的に取り組み、チームで協力しながら仕事を進める姿勢が求められます。
また、個人の成長に対して自分の可能性を広げていく姿勢も重要です。
新しいアイデアを提案し、実行する意欲と、それをチームで協力して実現する力が求められます。
参考:求める人物像|KOKUYO RECRUITING SITE
株式会社ニコン
ニコンは「信頼と創造」を重要な価値として掲げ、新しい挑戦に対して好奇心を持ち、常に学び続ける姿勢を重視しています。
多様な価値観を受け入れ、他者と協力しながら共に成長していける人物が求められます。
特に、自分の考えを他者と共有し、チームとして成果を上げる力が重要視されています。
好奇心を持ち続け、チームワークを大切にしながら新しい発想を生み出し、共に成長する姿勢が求められます。
日本ガイシ株式会社
日本ガイシは「聡明」「誠実」「柔軟」「快活」といった資質を備えた人物を求めています。
特に「一度やってみよう」というチャレンジ精神を持ち、失敗を恐れずに行動する姿勢が大切です。
自分の頭で考え、周囲を巻き込んで行動する力が評価されます。
チャレンジ精神を持ち、積極的に行動し、周囲と協力して成果を上げる力が求められます。
参考:求める人物像 | 新卒採用(大学生・大学院生向け)| 日本ガイシ株式会社
スターバックス
スターバックスは、自己成長を追求しながらも、ブランドの価値を仲間と共に育てていける情熱と行動力を求めています。
お客様や同僚の感情や価値観に興味を持ち、理解しようと努める姿勢が大切です。
「I(私)」からスタートし、「We(私たち)」で物事を実践できる人物が求められています。
自分自身を成長させるだけでなく、チーム全体を牽引し、共に目標を達成する力を必要としているようです。
求める人物像に関するよくある疑問

求める人物像を策定する際、採用担当者が直面しやすい疑問点について解説します。
迷いやすいポイントをあらかじめ理解しておくことで、より納得感のある採用戦略を立てやすくなります。
Q.求める人物像がわからない場合はどうする?
まずは現場の社員や上司へのヒアリングを行い、実際に活躍している人物の共通点を探るのが有効です。
人物像は業務内容や企業文化と密接に関係しているためです。
たとえば、チームで動く業務が中心の部署では「協調性」「柔軟な対応力」を持った社員が活躍しているケースが多いです。
無理に理想像を作ろうとせず、まずは社内にすでに存在する“理想に近い人”を観察するところから始めましょう。
Q.1つの職種に複数の人物像を設定してもいい?
職種によっては役割が多様なため、複数の人物像を設定するのは有効です。
同じ職種内でも担当する業務によって必要な資質が異なるためです。
たとえば、営業職でも新規開拓を担う人には積極性が、既存顧客を対応する人には丁寧さや信頼感が求められるケースがあります。
応募者が自分の適性と照らし合わせやすくなり、ミスマッチの防止にもつながるでしょう。
Q.未経験者と経験者で人物像を分けるべき?
未経験者と経験者では重視すべきポイントが異なるため、人物像を分けて考えるべきです。
経験者には即戦力性が期待される一方、未経験者には将来性や吸収力が求められるからです。
例として、経験者には「特定業務の実績」や「リーダー経験」などを重視し、未経験者には「学ぶ意欲」や「協調性」が評価されることが一般的です。
職種ごとのニーズに応じて、段階的な人物像を設計してください。
Q.自社の強みや文化と人物像をどう繋げる?
自社の価値観や文化を反映した人物像を設定するには、企業理念や日々の行動指針を振り返ることが大切です。
企業文化に合わない人材は、スキルがあっても定着しづらいためです。
たとえば、「挑戦を歓迎する文化」がある企業では、「失敗を恐れずチャレンジする姿勢」が求められます。
まずは自社の特徴を言語化し、それを体現している社員像から逆算して人物像を構築してください。
Q.人物像はどれくらいの頻度で見直すべき?
年に1回程度、定期的に見直すことをおすすめします。
市場環境や組織の方針が変わると、求められる人物像も変化するためです。
以前は現場重視だったが、今は戦略性やマネジメント力を求めるようになった場合、人物像をそのままにしておくと採用ミスマッチが起きやすくなります。
定期的に見直すことで、常に現場ニーズと一致した採用活動が行えるでしょう。
まとめ
採用サイトに「求める人物像」を明確に記載することは、応募者との相互理解を深め、採用活動全体に一貫性を持たせるために欠かせません。
具体的な希望や経営者の想いといった要素を盛り込みつつ、自社の文化や価値観とリンクさせて表現することが重要です。
また、ペルソナの作成や社員紹介、動画・図解などの工夫を加えることで、視覚的にも共感を呼びやすくなります。
一方で、抽象的な表現や美辞麗句ばかりでは、逆にミスマッチの原因になりかねません。
業種に応じた書き方や、他社の成功事例も参考にしながら、定期的な見直しも忘れずに行いましょう。
自社に合う人材を惹きつけ、長く活躍してもらうためにも、採用サイトでの「求める人物像」の伝え方を見直してみてください。
関連記事
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...
-

歯科衛生士の採用は難しい?成功する医院の採用戦略を深堀り解説
歯科衛生士の採用は、年々難しくなっていますよね。募集してもなかなか集まらないと、どうしたらいいか悩んでしまう気持ちわかります。そこで今回は、「歯科衛生士の採用が...