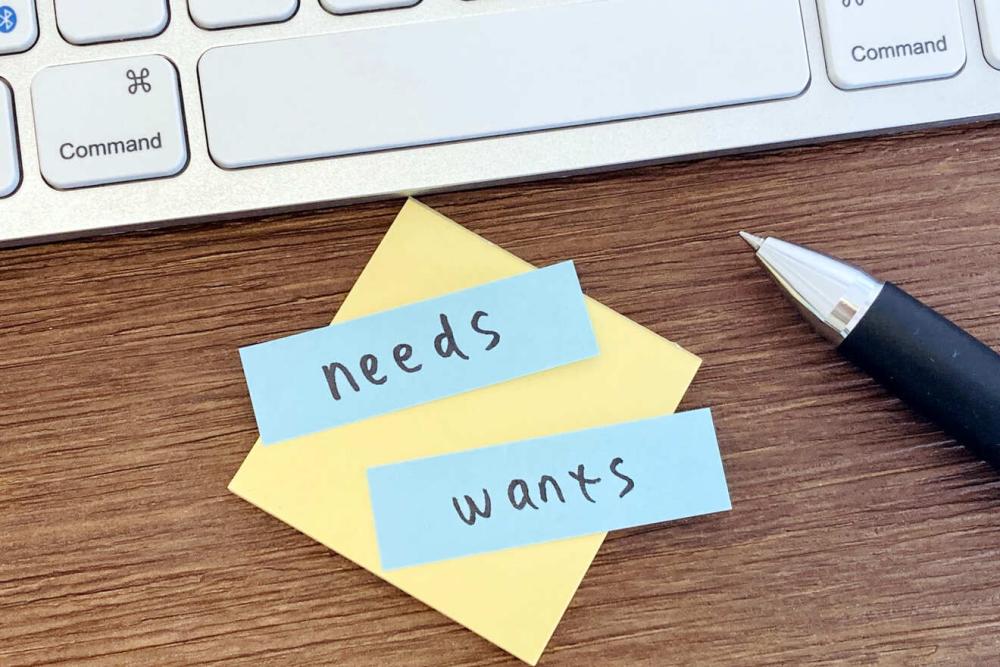若者が定着しない会社を変える7つの具体策・採用コストを削減し成長する方法

若者が定着しない会社は、経営者にとって頭の痛い問題ですよね。
「どうすれば若者が長く働いてくれるのだろう……」と悩む気持ちわかります。
できることなら、優秀な若手社員が定着し、会社の成長を支えてほしいですよね。
実は、職場環境や制度を見直すことで、若者が辞めにくい会社にすることが可能です。
若者が働きやすい環境になれば、社員が離職せず、採用や育成のコストを大幅に削減できるでしょう。
そこで今回は、「若者が定着しない会社の特徴と解決策」をご紹介します。
若者がすぐ辞めるとお悩みな方は、今すぐ定着率を向上させる取り組みを始めてください。
若者が定着しない理由

若者が定着しない背景には、企業側が気づきにくい問題が隠されています。
まずは、どうして若者が定着しないのか、理由を探っていきましょう。
給料が低い
若者が会社に定着しない一因は、給料の低さです。
給料は社員の生活を支える重要な要素であり、特に若者にとって生活基盤を築くための大きな支えとなります。
給料が低いと生活が不安定になり、会社に長く勤めたいという意欲を失います。
たとえば、同業他社と比較して給料が10%以上低い場合、社員は「努力が報われない」と感じやすくなるのです。
給料が低いことで、より良い条件を求めて転職を選ぶケースが増えるでしょう。
やりがいがない
仕事にやりがいを感じられないことも、若者が離職を理由の一つです。
若者は成長や充実感を重視する傾向があり、単調な業務や達成感を得にくい仕事内容に不満を感じやすいです。
具体的には、ルーチンワークばかりで、目標や成果が見えにくい状況が挙げられます。
やりがいがないことで、成長を実感できる職場を求めて転職を検討するようになるでしょう。
人間関係が悪い
職場の人間関係は、若者の定着に大きく影響します。
良好な人間関係が築けない環境では心理的な負担が増し、働く意欲が低下するからです。
特に、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑でない場合、孤立感を感じやすくなります。
例として、上司が指示するだけでフィードバックを与えない場合や、同僚間で頻繁に対立が起きる職場が挙げられます。
このような環境では、ストレスを感じ、早期退職に至ることが多いです。
企業文化と合わない
企業文化のミスマッチも、若者が早期離職する要因です。
会社の方針や価値観が自分の考えと合わないと、働くモチベーションが低下し、自分の居場所を感じにくくなります。
仮に、新しい意見を受け入れない企業の場合、若者は「この会社では成長できない」と感じ、転職を考えるでしょう。
柔軟な文化を醸成し、若者が意見を発信しやすい環境を作ることが重要です。
キャリアアップできない
キャリアの展望が見えない環境では、若者の定着は難しくなります。
スキルを磨き、昇進の機会を得たいと考える人にとって、成長できない環境は魅力を失いやすいです。
たとえば、研修制度が整備されていなかったり、明確な昇進基準がなかったりする場合、社員は自分の未来を描けず、退職を検討する可能性が高まります。
キャリアアップできないことで、成長意欲が削がれ、長期的に働く理由を見出せなくなるでしょう。
若者が定着しない会社の特徴

若者が定着しない会社には共通する特徴があります。
ここからは、どのような点が若者の離職につながるのかを解説します。
低い待遇
低い待遇は、若者が会社に魅力を感じない主な原因です。
給与や福利厚生が充実していないと、生活の安定や働く意欲を得にくくなります。
たとえば、基本給が業界平均を下回る場合、若者は「他の会社のほうが良い条件を得られる」と感じて転職を検討します。
定着率を向上させるには、待遇を見直し、業界水準に合わせることが必要です。
成長機会が少ない
若者がスキルを磨けない環境では、成長意欲が削がれます。
仕事を通じて自己成長を望む若者にとって、挑戦や学びがない職場は魅力に欠けるからです。
具体的には、新しい業務を任されない、または研修や勉強会がない職場が挙げられます。
成長機会が少ないことで、その会社で働く意義を見失うでしょう。
教育体制が整っていない
教育体制が不十分な会社では、若者が適応できずに離職するリスクが高まります。
新入社員が必要なスキルや知識を習得できないと、業務への不安が募るからです。
例として、OJTが形だけのものになっている職場だと、社員が成長することはありません。
教育体制が整っていないことで、早期退職に繋がるでしょう。
評価基準が曖昧
明確な評価基準がないと、若者は努力が報われているか分からず、不満を抱きやすくなります。
公正な評価がなされない環境では、モチベーションが低下し、離職に繋がるのです。
たとえば、基準が不明確なまま「感覚的に評価される」と感じた場合、会社を信用できなくなります。
透明性のある評価システムを導入しない限り、離職率は改善されないでしょう。
職場環境が悪い
働きやすい職場環境が整備されていないと、不満が高まります。
過度な残業や設備の不備などは、体力的・精神的な負担を引き起こすからです。
仮に、劣悪な環境で働き続ける場合、健康を損ねるリスクもあり、転職を決意する原因になりかねません。
職場環境が悪いと、長く働くことはできないでしょう。
若者が定着しない会社のリスク

若者が定着しない会社は、採用や事業運営において多くのリスクを抱えています。
ここでは、それらの影響を具体的に解説します。
採用の手間と費用が増える
若者が定着しないと、頻繁に人材を補充する必要が生じ、採用にかかるコストが増大します。
求人広告費や採用活動の時間的コストが大幅に増え、負担が重くなるのです。
たとえば、年間で数名が退職し、そのたびに採用を行う場合、1人あたりの採用費用が何十万円にもなります。
採用の手間と費用が増えることで、経営を圧迫させてしまうでしょう。
仕事の質が下がる
頻繁な人材の入れ替わりは、業務の継続性を損ない、仕事の質の低下を招きます。
新しい社員が業務に慣れるまで時間がかかり、その間にミスや作業効率の低下が起こりやるくなるからです。
具体的には、新人教育が間に合わず、プロジェクトの進行に支障をきたすケースが挙げられます。
安定した人員を確保しない限り、仕事の質は下がり続けるでしょう。
職場の士気が下がる
離職者が続く職場では、残った社員の士気も低下します。
仲間が次々と退職する状況は、職場全体に不安や焦りをもたらすからです。
たとえば、頻繁に退職者が出る職場では、「次は自分も辞めるべきか」と考える社員が増える傾向があります。
退職者の業務をカバーしなければいけないことで、既存社員の不満が蓄積するでしょう。
会社の評判が悪化する
若者が定着しない会社は、求職者や取引先からの評価が低下するリスクがあります。
離職率の高さが外部に伝わると、「働きにくい会社」としてネガティブなイメージが広がるからです。
具体的には、口コミサイトやSNSで「ブラック企業」と批判されるケースがあります。
会社の評判が悪化することで、企業ブランドにも影響を与えるでしょう。
事業の成長が阻害される
人材の流出は、会社の持続的な成長を妨げます。
若手社員が早期に辞めることで、将来的なリーダー候補が育たず、組織の成長力が失われるからです。
仮に、ベンチャー企業で有望な若手が離職し続ける場合、事業拡大のスピードが大幅に遅れます。
事業の成長が阻害されることで、目標達成が困難になるでしょう。
若者が定着しない会社の対策

若者が定着しない課題に対処するためには、効果的な対策を講じる必要があります。
ここからは、どのようにして若者の定着率を上げるかについて解説します。
給与・待遇の改善
適切な給与と充実した福利厚生は、若者の定着を促す基本的な条件です。
業界水準を下回る給与体系や不十分な福利厚生では、社員の満足度を維持することはできません。
たとえば、基本給の見直しや住宅手当の導入、健康支援プログラムの提供などが有効です。
若者のニーズを反映した待遇を整えることで、定着率が改善されるでしょう。
仕事のやりがい向上
やりがいを提供することで、若者のモチベーションを高めることができます。
自己成長を実感できる業務を任せることで、社員は仕事への意欲を持ち続けるからです。
具体的には、新しいプロジェクトへの参加や、目標達成を称賛する制度を導入する方法があります。
活き活きと働いてもらうためにも、達成感を与える仕組みを整えましょう。
キャリアパスの明確化
社員が将来の成長を描ける環境は、定着率を高める要因となります。
キャリアパスが明確になることで、自身の未来を想像しやすくなるからです。
たとえば、昇進基準や必要スキルを明確化したガイドラインを用意すること、将来の見通しが透明化されます。
社員に成長の道筋を示すことで、安心して働けるようになるでしょう。
職場環境の改善
働きやすい職場環境は、若者の満足度に直結します。
良い職場環境だとストレスが溜まりにくくなり、長く定着してくれるようになるからです。
仮に、設備の老朽化や長時間労働が常態化している場合、社員の健康や生産性に悪影響を及ぼします。
既存の職場環境を見直し、快適で安全な労働環境を整備してください。
コミュニケーション活性化
円滑なコミュニケーションは、職場の一体感を高めます。
社員同士が意思疎通を取れることで、チームワークが強化されるからです。
具体的には、定期的な1on1ミーティングやチームビルディングイベントを実施する方法が効果的です。
相互理解を深められる場ができれば、社員同士の絆も深まるでしょう。
多様な働き方の導入
柔軟な働き方を提供することで、社員のワークライフバランスを向上させることができます。
固定的な勤務形態だけでは、多様なライフスタイルを持つ若者に対応しきれません。
たとえば、リモートワークやフレックスタイム制度の導入が挙げられます。
社員のニーズに応じた働き方を用意することで、早期退職を防げるでしょう。
ITツールの活用
ITツールを活用することで、業務効率を向上させ、社員の負担を軽減できます。
非効率な業務プロセスは、社員のストレスを増加させる原因となるからです。
仮に、勤怠管理やタスク管理に手作業が必要な場合、ITツールを導入することで効率化が図れます。
適切なツールを選定し、社員の働きやすさをサポートしてください。
若者を定着させる採用戦略

若者を採用し、定着させるには、採用活動の段階から適切な戦略を講じることが重要です。
本セクションでは、その具体的な方法を解説します。
リアルな職場環境の発信
実際の職場環境を正直に発信することで、若者に安心感を与えられます。
採用時に理想化した情報ばかり提供すると、入社後のギャップが原因で離職につながりやすくなるからです。
たとえば、職場の写真や動画、社員の一日を紹介するコンテンツを公開する方法があります。
会社の雰囲気や実情を知ってもらい、相性の良い人材を引き寄せましょう。
SNSや動画の活用
若者の情報収集手段として、SNSや動画プラットフォームを活用することは非常に効果的です。
これらの媒体を通じて、会社の魅力をダイレクトに伝えることができます。
具体的には、InstagramやYouTubeで、社員インタビューやオフィスツアーの動画を投稿する方法があります。
SNSや動画を活用することで、若者が親しみを持ってくれるでしょう。
選考プロセスの透明化
選考過程が透明であることは、若者に対する信頼感を高めます。
曖昧な基準やプロセスでは、候補者に不安や疑念を抱かせてしまう可能性があるからです。
たとえば、選考フローや評価基準を事前に説明し、各ステップの意図を明確化する方法があります。
選考プロセスが透明化されていれば、安心して応募できるようになるでしょう。
インターンシップの実施
インターンシップは、若者に会社を理解してもらう絶好の機会です。
実際に働く体験を提供することで、入社後のミスマッチを減らすことができます。
たとえば、短期間でプロジェクトに参加する形式のインターンシップを行う方法があります。
実務体験を通じて、会社の魅力を直接感じてもらいましょう。
若者向けのイベント開催
若者が会社に興味を持つきっかけとして、イベント開催は有効な手段です。
カジュアルな場で社員と交流することで、会社の文化や価値観を伝えることができます。
具体的には、キャリア相談会や体験型ワークショップを実施する例があります。
リラックスした雰囲気で、若者とのつながりを深めてください。
若者を定着させた会社の成功事例

若者を定着させる取り組みを実践し、成果を上げている企業の事例を紹介します。
それぞれの業界で独自の施策を展開している点が特徴です。
未来工業(製造業)
未来工業は、「残業ゼロ」「年間休日140日以上」など、社員の働きやすさを重視した制度を導入しています。
独創的な福利厚生と効率的な業務体制が、若者の定着率向上に寄与しています。
たとえば、アイデア提案に対する報奨制度や、全社員へのiPad支給による業務効率化がその一例です。
社員の満足度を高める工夫が成功の鍵となっています。
出典:社長 山田雅裕さんに問う ―ノルマ・残業ゼロで高収益を生む未来工業のしくみ
サイボウズ(IT業)
サイボウズは、柔軟な働き方を推進することで若者の離職を防いでいます。
同社は「100人いれば100通りの働き方」を理念とし、多様な勤務形態を選択できる制度を設けています。
具体的には、リモートワークや短時間勤務を可能にする取り組みが挙げられます。
個々のニーズに応える柔軟性が、社員の満足度を高めています。
出典:100人いれば100通りの働き方 サイボウズのワークスタイル変革(PDF)
伊藤園(飲料メーカー)
伊藤園は、若手社員の育成に注力し、定着率向上を実現しています。
同社は「社員のやる気を引き出す」ために評価制度を見直し、成果を正当に評価する仕組みを整えています。
たとえば、営業成績に基づくインセンティブ制度や、定期的なキャリア相談を行っています。
努力が報われる環境が、若者に支持されています。
クックパッド(IT業)
クックパッドは、社員のやりがいを重視した働き方を提供しています。
同社は「好きなことを追求できる環境」を整えるため、社員の自主性を尊重したプロジェクト運営を行っています。
具体的には、社内での「食」に関するイベントや、アイデアを形にできる社内プログラムが挙げられます。
自己成長を促す文化が若者の支持を集めています。
出典:クックパッド「起業家優先、中卒OK」型破り採用で利益4倍!
星野リゾート(観光業)
星野リゾートは、社員が成長できる環境づくりで若者の定着率を向上させています。
同社は「現場主導」を重視し、社員が主体的に企画・運営に携われる仕組みを構築しています。
たとえば、新しい観光プランの提案や実施を社員が自由に行える制度があります。
挑戦を歓迎する文化が、若者にとって魅力的な要因となっています。
出典:CAREER PATH SYSTEM | 星野リゾート 採用サイト【公式】
まとめ
若者が定着しない会社は、給料や待遇の問題、成長機会の不足、職場環境の悪化など、多くの課題が絡み合っています。
こうした特徴を放置すると、採用コストの増加や職場の士気低下、さらには事業成長の停滞といった深刻なリスクを招きます。
しかし、給与や待遇を改善し、やりがいを提供し、キャリアパスを明確化することで、若者が働き続けたいと思える環境を作ることが可能です。
また、採用活動においては、リアルな職場環境の発信やSNSの活用、透明性のある選考プロセスを通じて、若者に企業の魅力を効果的に伝えることが重要です。
課題を改善し、若者が安心して長く働ける環境を作ることは、会社の持続的な成長につながります。
ぜひ本記事を参考に、自社に最適な施策を取り入れ、若者に選ばれる企業を目指してください。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...