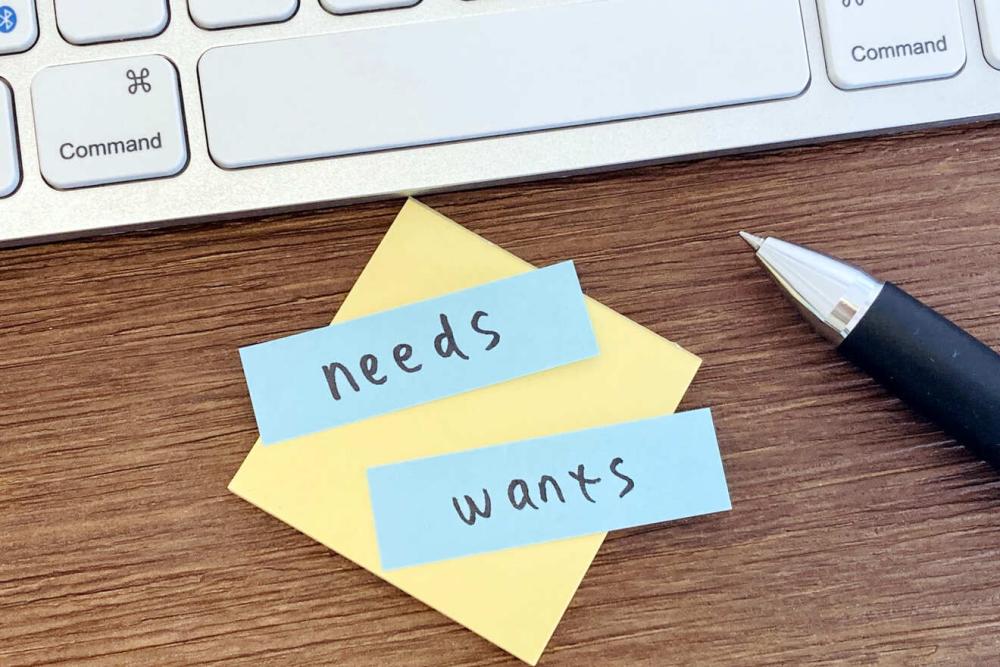1年で10人辞める会社は異常?退職者が多い原因と改善策を紹介

1年で10人の退職者が出る状況は、経営者にとって大きな問題ですよね。
従業員が次々と去ってしまうと業務の進行が滞り、残った社員の負担も増えます。
できることなら、社員が長く働いてくれる職場を作りたいですよね。
実は、職場環境を工夫することで、離職率を劇的に改善することができます。
職場が居心地の良い場所になれば、社員のモチベーションも向上し、離職されることはありません。
そこで今回は、「1年で10人辞める会社の問題点と改善策」をご紹介します。
退職が常態化しているのであれば、改善に向けた行動を取るようにしましょう。
1年で10人辞める会社は異常なのか

規模や業種によって異なりますが、1年で10人辞める会社は異常な状況と考えられます。
特に中小企業や少人数の職場であれば、これほどの退職者は大きな問題を抱えている可能性が高いです。
職場環境の問題、マネジメントの不備、適切なキャリアパスや成長機会の欠如、労働条件の悪化など、さまざまな原因が考えられます。
このような状況が続くと、企業の評判にも悪影響を与え、採用が難しくなると言わざるを得ません。
1年で10人辞める状況は決して会社にとって良くないため、改善が必要なサインとして捉えるべきでしょう。
1年で10人辞める会社に対する印象

毎年、次々と社員が辞めていく会社は、外部から悪い印象を持たれることが多いです。
退職者が多い会社は、職場環境の悪さや成長機会の欠如など、さまざまな問題を抱えている可能性があるからです。
ここからは、人がどんどん辞める会社に対する、一般的な印象について解説します。
職場環境が悪い
人がどんどん辞めていく会社は、職場環境が悪いと判断されがちです。
多くの従業員が短期間で退職する場合、働きにくい環境があるのではないかと疑われます。
たとえば、「長時間労働が横行している」「人間関係が悪い」「オフィスの設備が古い」などが考えられます。
職場環境が悪いという印象を持たれると、求職者が応募してくれなくなるでしょう。
成長できない
人がすぐに辞めてしまう会社は、個人が成長できない会社だと見なされます。
離職率が高い会社は、従業員の成長をサポートする制度が不十分である可能性が高いと見なされるからです。
具体的には、研修制度がなく、昇進のチャンスも限られている職場では、やる気があっても成長することはできません。
成長の機会がない会社だと見なされれば、優秀な人材を獲得することはできないでしょう。
従業員の評価が低い
頻繁に退職者が出る会社は、従業員の評価が低いと感じさせます。
なぜなら、従業員の評価が高いと退職することはないからです。
頑張って成果を出しても評価や報酬に反映されない会社では、従業員が自分の努力が無駄だと感じ、やる気を失ってしまいます。
従業員の評価が低いという印象を与えると、会社の魅力が大きく損なわれるでしょう。
マネジメントが悪い
退職者が多い会社は、マネジメントが悪いという印象を与えます。
効果的なマネジメントが行われていない会社では、従業員が仕事の方向性や価値を感じられず、結果として離職率が高くなるからです。
たとえば、上司が指示を出すだけでフィードバックがない職場だと、従業員が自分の仕事にやりがいを感じられず、辞めたくなります。
マネジメントの問題は、会社全体の雰囲気を悪化させ、求職者にも悪い印象を与えるでしょう。
倒産のリスクがある
従業員が次々と辞める会社は、倒産のリスクが高いと感じさせます。
特に中小企業では、業績悪化や資金繰りの悪化が直結することが多いため、従業員の流出は危険信号と受け取られやすいです。
仮に、毎年のように大量の人材が辞めていく会社だと、経営に問題があると思われても仕方ありません。
倒産リスクがあると見なされると、求職者は慎重になり、応募をためらうでしょう。
1年で10人辞める会社の特徴

1年で10人辞める会社には、共通するいくつかの特徴があります。
離職率が高い会社は何がいけないのか?退職者が多い原因とはなにか?を考えなくてはいけません。
これらの特徴を理解することで自社の問題点を見つけ、改善の手がかりを得られるでしょう。
人間関係が悪い
1年で10人辞める会社は、人間関係が悪い場合が多いです。
人間関係が良好でない職場では、コミュニケーションが円滑に進まず、ストレスが溜まりやすくなります。
特に、上司と部下の関係が悪化すると、仕事に対するモチベーションが低下し、退職を考えるきっかけとなるのです。
たとえば、職場内で派閥ができていたり、上司がパワハラ的な態度を取っていたりすると、従業員は精神的に追い詰められ、辞めざるを得ない状況になります。
人間関係が悪い職場は、退職者が増える大きな要因となるでしょう。
職場環境が悪い
職場環境が悪い会社では、退職者が増加する傾向があります。
快適でない環境や、働きにくい条件が揃っている職場だと、従業員のストレスが蓄積するからです。
例として、オフィスが狭すぎて個人スペースが確保できなかったり、騒音がひどかったりする環境では、長く働きたいと思えなくなるかもしれません。
働きにくい職場環境は、従業員の離職を加速させるでしょう。
給与や待遇が悪い
1年で10人辞める会社は、給与や待遇が悪い可能性があります。
給与が市場相場より低かったり、福利厚生が不十分であったりする会社では、退職率が高くなるのは避けられません。
具体的には、同じ業界内で他社と比べて給与が低かったり、ボーナスが支給されなかったりする場合、従業員は魅力を感じず、退職を選ぶケースが増えてきます。
給与や待遇が悪い会社では、優秀な人材の流出が止まらないでしょう。
労働時間が長い
労働時間が長い会社は、退職者が増えやすいです。
長時間労働が続くと、従業員の健康に悪影響を与えるだけでなく、私生活にも支障が出ます。
バランスの取れた労働環境がない場合、持続的に働き続けるのが難しくなるのです。
たとえば、残業が常態化しており、有給も取りづらい職場だと、働き続けるのが辛くなります。
長時間労働を強いる会社では、離職率が高まるでしょう。
キャリアパスが不透明
キャリアパスが不透明な会社は、退職者が多くなる傾向があります。
目指すべき目標が見えない場合、長くその会社で働き続けるモチベーションを保てなくなるからです。
仮に、昇進の基準が不明確であったり、研修やスキルアップの機会が提供されなかったりする場合、やりがいを感じられません。
キャリアパスが不透明な会社では、将来に不安を感じた従業員が離れていくでしょう。
会社の将来性が見えない
会社の将来性が見えないと、退職者が増えるリスクがあります。
成長が見込めない企業や、経営に不安がある企業では、従業員が将来を悲観し、早めに次のキャリアを考えるようになるからです。
例として、業績が低迷し続けている、または事業の方向性が定まらない会社だと、従業員が将来に希望を持てず、他社への転職を検討することになります。
会社の将来性が不透明な場合、従業員が早期に見切りをつけるでしょう。
教育制度が整っていない
教育制度が整っていない会社では、退職者が増える傾向があります。
十分な教育や研修が行われない職場では、従業員が自分の成長を感じられず、やりがいや達成感が失われるからです。
たとえば、新人研修が不十分で業務に必要なスキルが身につかない場合、従業員は成長を感じられず、退職を考えやすくなります。
教育制度が整っていない会社では、従業員の成長意欲が低下し、退職者が増えるでしょう。
1年で10人辞める会社の改善策

1年で10人が辞めるような会社では、従業員の定着率を向上させるための改善が急務です。
職場環境やマネジメント、給与・待遇などを見直すことで、社員の満足度を高め、離職率の低下が期待できます。
ここからは、1年で10人辞める会社の改善策について紹介します。
職場環境の改善
職場環境を改善することで、従業員の定着率を高められます。
快適で働きやすい職場環境は、従業員の満足度を向上させ、離職率を下げる重要な要因です。
たとえば、オフィス内のレイアウトを見直し、より広々とした空間を確保することで、従業員がストレスを感じにくくなります。
職場環境の改善により、従業員が働きやすいと感じる職場作りを進めると、離職を防げるでしょう。
マネジメントの改善
マネジメントを改善することが、離職率の低下につながります。
適切なマネジメントは、従業員のモチベーションを高め、チーム全体のパフォーマンスを向上させるからです。
たとえば、定期的なフィードバックや、個々の従業員に対するサポートを強化することで、従業員が自分の成長を実感できるようになります。
マネジメントを改善し、従業員との信頼関係を築くことで、退職者を減らせるでしょう。
給与・待遇の見直し
給与や待遇を見直すことで、従業員の満足度を高められます。
適切な報酬を用意することで、従業員はやりがいを覚えるからです。
具体的には、市場調査を行い、自社の給与が業界平均と比較してどうかを確認してください。
最低でも同業他社と同水準の給与にすることで、福利厚生の充実が図れます。
給与・待遇の見直しは、従業員にとって大きなモチベーションアップとなり、離職を減らす結果につながるでしょう。
労働時間の適正化
労働時間を適正化することで、従業員のワークライフバランスを向上させられます。
長時間労働は、従業員の健康や私生活に悪影響を与え、結果として離職を招くことが多いです。
適正な労働時間を確保することで、従業員の負担を軽減できます。
たとえば、残業時間を削減するために業務プロセスを見直し、効率化を進めることが可能です。
また、有給休暇を積極的に取得させる仕組みを導入することも考えられます。
労働時間の適正化を進めることで、従業員の健康を守り、結果として離職率の低下が期待できるでしょう。
キャリアパスの明確化
キャリアパスを明確化することで、将来への安心感を高められます。
会社の将来像が見えることで、長期的に働きたいという意欲が生まれるからです。
たとえば、昇進の基準やスキルアップの流れを明確に提示することで、従業員が自分の将来に希望を持てることが可能になります。
キャリアパスを明確にすることで、従業員が将来を見据えて安心して働ける環境を作り、離職率の低下が期待できるでしょう。
教育制度の強化
教育制度を強化することで、従業員のスキルアップを促進し、定着率を向上させられます。
従業員が自分の成長を実感できる環境では、モチベーションが高まり、長期的に働き続ける意欲が生まれるからです。
仮に、研修プログラムやオンデマンド学習の機会を提供することで、従業員が常に新しい知識やスキルを習得できるようサポートすることができます。。
教育制度の強化は従業員の成長を促し、即戦力の確保にも繋がるでしょう。
会社のビジョンを提示
会社のビジョンを明確に提示することで、従業員の共感とモチベーションを引き出せます。
ビジョンが明確であることは、従業員が同じ方向を目指して働ける原動力となるからです。
たとえば、定期的にミーティングを開催し、経営陣が会社のビジョンや目標を直接伝えることができます。
会社のビジョンを明確に示し、従業員全体が一体となって働ける環境を整えることで、離職率の改善が期待できるでしょう。
人が辞めない会社もやばいと言われる理由

人が長期間辞めない会社には、一見安定しているように見えるかもしれませんが、実はさまざまなリスクを抱えています。
人材の流動性が欠けると、従業員の不満に気づきにくく、市場の変化にも対応しづらくなる可能性があるのです。
ここからは、人が辞めない会社もやばいと言われる理由について解説します。
組織の成長が停滞する
人が辞めない会社では、組織の成長が停滞するリスクがあります。
同じメンバーが長期間在籍することで、新しい視点やスキルが入りにくくなり、組織の活性化が妨げられるためです。
たとえば、長年変わらないメンバーで構成されたチームでは、新しいアイデアや効率的な方法が提案されにくくなり、業績が頭打ちになることがあります。
組織の成長を促すためには、一定の入れ替わりは必要だといえるでしょう。
イノベーションが生まれない
人が辞めない会社では、イノベーションが生まれにくくなります。
同じメンバーが固定化されることで、新しい発想やチャレンジ精神が失われる可能性が高いからです。
具体的には、ベテラン社員が多い職場では、既存のやり方に固執しがちで、保守的な姿勢が取られます。
イノベーションを促すためには、適度な人材の流動性が重要となるでしょう。
従業員の不満に気づきにくい
人が辞めない会社では、従業員の不満に気づきにくいという問題が発生します。
長期間在籍している社員は、不満があっても現状を受け入れやすく、経営陣が問題に気づかないまま放置されるケースがあるからです。
例として、長年勤務している社員が不満を感じながらも「変えるのは難しい」と諦めてしまい、慢性で仕事をすることがあります。
従業員の不満に気付けないことで、経営にも悪影響を与えるでしょう。
市場の変化に対応しづらい
人が辞めない会社は、市場の変化に対応しづらくなります。
外部の変化に対して柔軟に対応する力が弱まり、新しいトレンドや技術を取り入れにくくなるからです。
仮に、長く同じ体制で運営している企業が、急速に変化する市場環境に遅れを取り、競争力を失ってしまうことがあります。
市場の変化に対応するためには、時として新しい人材が必要になるでしょう。
リーダーシップが育たない
人が辞めない会社では、リーダーシップが育たないことが懸念されます。
長く同じポジションにいる社員が固定化されると、若手がリーダーシップを発揮する機会が減り、組織全体の活力が失われるためです。
たとえば、ベテラン社員が長期間同じ役職にいる場合、新しいリーダー候補が育たず、組織の将来を担う人材が不足することがあります。
リーダーシップを育成するためには、適切な人材の配置と入れ替えが必要になるでしょう。
1年で20人辞める会社は採用に問題がある

1年で20人が辞める会社では、採用プロセスに問題があることが多いです。
企業が求める人物像やスキルが明確でないと、職場とのミスマッチが生じやすくなります。
この結果、短期間での離職が繰り返され、会社全体に悪影響を及ぼす可能性があるのです。
たとえば、業務スキルを重視すべき職場で、意欲や将来性だけを重視して採用する場合、入社後にスキル不足を感じる社員が多くなることがあります。
逆に、スキルばかりを強調しすぎると、協調性や柔軟性が不足した社員が増え、社内の雰囲気が悪化する原因にもなります。
このようなトラブルを防ぐには、採用基準やプロセスを明確にし、職場の実情を伝えることが重要です。
会社の価値観に合った人材を見極め、入社前にお互いの理解を深めることで、離職を減らすことができるでしょう。
毎月必ず人が辞める会社はおかしい?
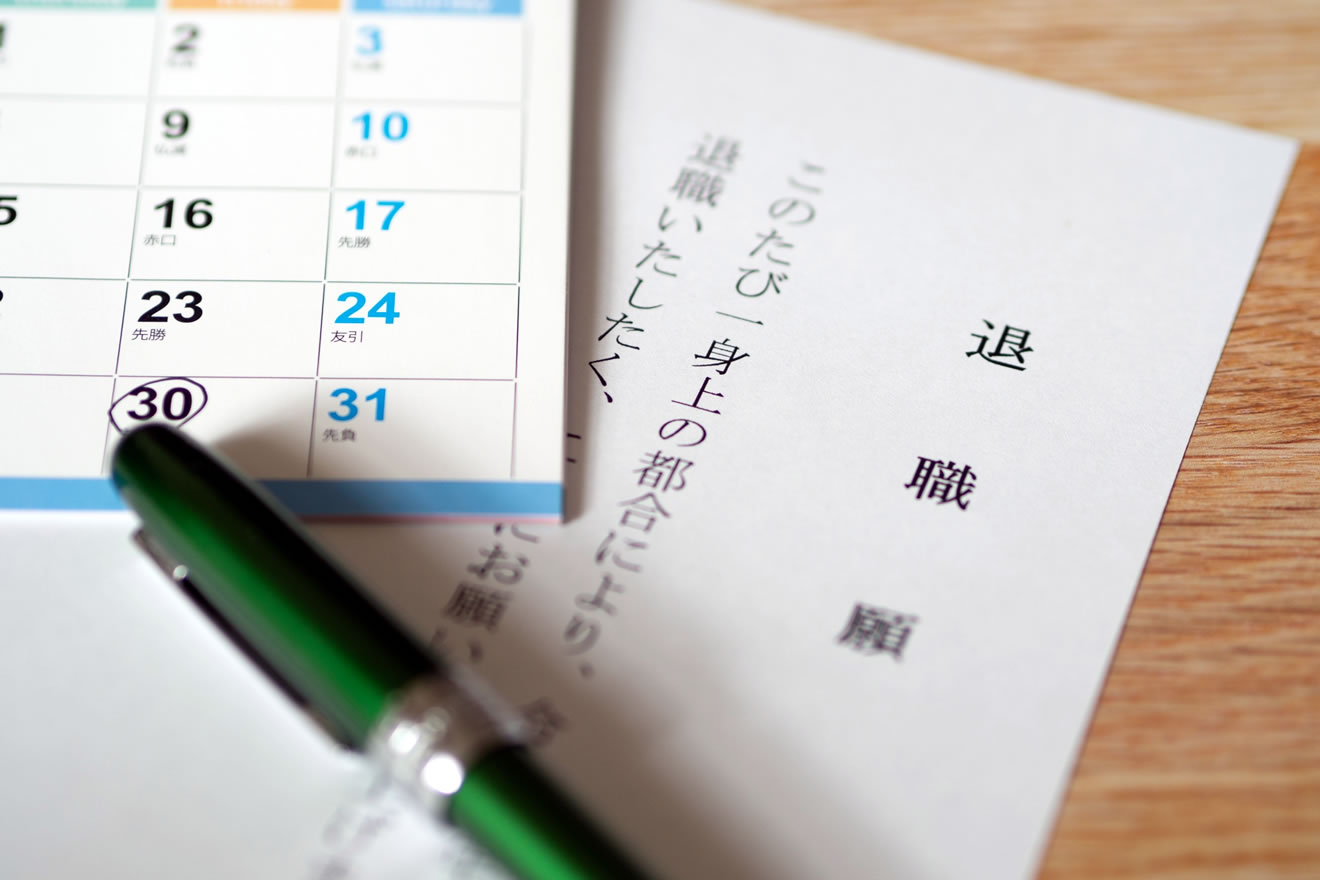
会社の規模にもよりますが、毎月必ず人が辞める会社は「おかしい」と言えます。
離職率が高い会社は、何かしらの構造的な問題を抱えている可能性が高いです。
たとえば、職場環境が悪い、業務量が過剰、採用のミスマッチ、あるいは社員同士のコミュニケーション不足などが原因として考えられます。
また、退職が頻発する会社は、残る社員にも悪影響を及ぼします。
仕事の負担が増え、モチベーションが低下し、さらなる離職を招く悪循環に陥ることも珍しくありません。
このような状況を改善するには、現状を客観的に見直し、問題点を明確にすることが必要です。
職場環境を整え、従業員が働きやすい仕組みを作ることで、離職率を下げることは十分可能です。
離職が「普通」と感じる状態から脱却し、安定した職場づくりを目指しましょう。
まとめ
1年で10人辞める会社の現状は、経営者にとって非常に深刻な問題です。
人がどんどん辞める会社は企業の評判に悪影響を与え、採用が難しくなります。
職場環境が悪いと思われたり、成長できないと思わせるため、優秀な人材が集まりません。
優秀な人材を確保するためにも、職場環境やマネジメントを改善し、給与・待遇を見直したり、労働時間の適正化を図る必要があります。
キャリアパスが明確になり、教育制度を強化し会社のビジョンを定着することで、自然と離職率が改善していくでしょう。
中小企業にとって、1年で10人辞める会社は決して健全とは言えない状態です。
今後採用活動に力を入れていくのであれば、辞めない会社作りを目指すようにしてください。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...