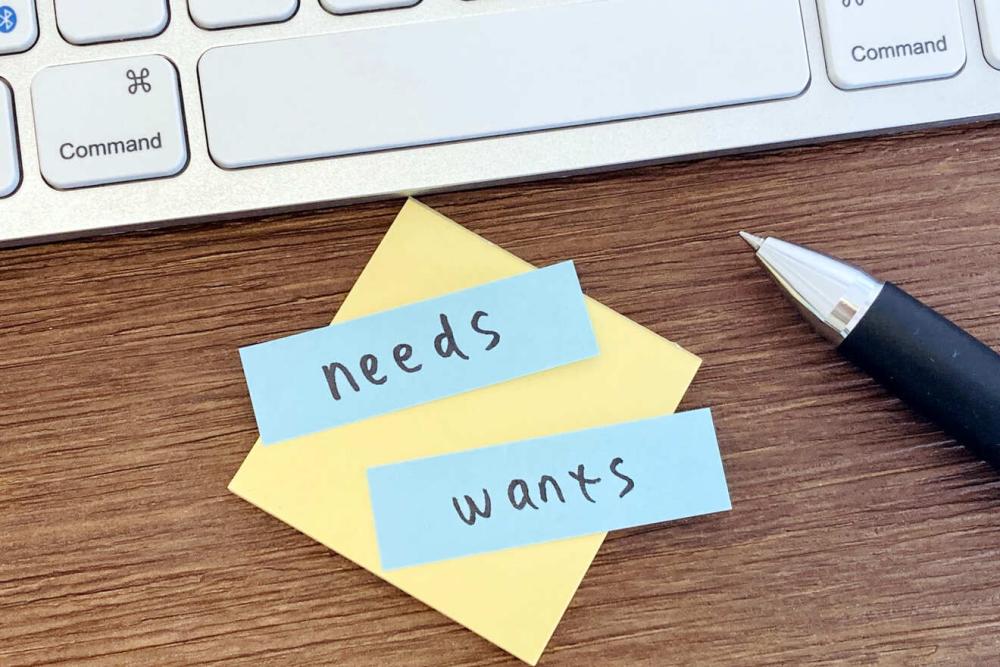「来社お待ちしております」メールの書き方とは?好印象を与える例文

「来社お待ちしております」メール(以下、来社依頼メール)の書き方は、悩ましいですよね。
送るタイミングが遅れると応募者が不安になるし、内容が不十分だと相手に誤解を与えてしまいます。
できることなら、応募者に安心して来社してもらい、スムーズに選考を進めたいですよね。
実は、適切なフォーマットとポイントを押さえるだけで、簡単に来社依頼メールを作成できます。
来社依頼メールがわかりやすい内容になれば、無駄なやり取りは発生しません。
そこで今回は、「応募者に好印象を与える来社依頼メールの書き方と例文」をご紹介します。
適切な来社依頼メールを作成し、スムーズな選考につなげられるようにしましょう。
来社依頼メールの重要性

応募者に来社を依頼するメールは、単なる連絡手段ではなく、企業の姿勢や信頼性を伝える重要な役割を果たします。
適切な表現や配慮のある文章を心がけることで、スムーズな選考プロセスにつながり、応募者の企業に対する印象を向上させることができます。
企業の第一印象を形作る
来社依頼メールは、応募者が企業と直接接触する前に受け取る重要なメッセージです。
相手に与える第一印象は、採用活動の成否を左右する重要な要素だからです。
たとえば、丁寧で簡潔な表現を用いたメールであれば、企業の誠実さや組織の整備が行き届いている印象を与えられます。
応募者に信頼感を持ってもらうためにも、来社依頼メールの内容には十分に気を配りましょう。
コミュニケーションの基盤作り
来社依頼メールは、応募者との円滑なコミュニケーションを築く第一歩となります。
明確で分かりやすい文章を送ることで、スムーズなやり取りの土台を作るためです。
たとえば、日時や場所、持ち物などの情報を整理して伝えることで、応募者が不安なく来社できるようにしてください。
選考をスムーズに進めるためにも、必要な情報を簡潔かつ丁寧に伝えましょう。
相手に対する配慮
来社を依頼する際には、応募者の状況を配慮した文章が求められます。
相手の立場を尊重することで、企業に対する印象が良くなるためです。
たとえば、「ご都合の良い日時をお知らせください」と一言添えるだけでも、気遣いの意思が感じ取れます。
応募者にとって負担の少ないやり取りを心がけることが、良好な関係構築につながるのです。
プロ意識の表現
適切な言葉遣いやフォーマットを守ることで、自社のプロ意識を示すことができます。
ビジネスメールとしての基本を押さえた文章は、企業の信頼性を高めるからです。
たとえば、敬語の使い方に注意し、「ご連絡いたします」や「ご足労おかけします」などの表現を適切に用いることで、礼儀正しさを伝えられます。
社会人としてのマナーを意識し、丁寧で誤解のない文章を作成してください。
後のトラブル防止
来社依頼メールを適切に作成することで、当日の混乱や認識のズレを防ぐことができます。
事前に詳細な情報を伝えることで、応募者との行き違いを避けられるためです。
たとえば、地図のリンクを添付し、訪問先の建物名や受付の場所を具体的に記載すれば、道に迷うリスクを減らせます。
応募者が安心して来社できるように、必要な情報を正確に伝えましょう。
来社依頼メールの書き方

来社依頼メールを作成する際は、応募者にとって分かりやすく、必要な情報が明確に伝わるように工夫することが重要です。
適切な件名や簡潔な文章構成を心がけることで、応募者がスムーズに内容を理解し、必要な対応を取れるようになります。
件名を明確にする
メールの件名は、受信者がすぐに内容を把握できるように、簡潔かつ具体的に記載する必要があります。
明確な件名を設定することで、応募者が見落とさず、スムーズに確認できるからです。
たとえば、「【○○株式会社】面接のご案内(○月○日)」と記載すれば、送信者と目的が一目で分かります。
応募者が迷わずメールを開けるように、簡潔で分かりやすい件名を設定してください。
簡潔で正確な情報提供
来社依頼メールでは、必要な情報を簡潔に伝えることが大切です。
情報が整理されていないと、応募者が混乱し、誤解を招く可能性があるためです。
たとえば、「日時:○月○日(○)○時~」「場所:○○ビル3階 受付」など、箇条書きを活用することで、重要事項を分かりやすく伝えられます。
余計な情報を省き、応募者がすぐに理解できるメールを作成しましょう。
読みやすさを意識する
応募者がストレスなく内容を把握できるよう、メールの文章は読みやすさを意識することが大切です。
適度な改行や箇条書きを活用することで、視認性を高められるからです。
たとえば、「面接当日の流れ」や「持ち物リスト」をリスト形式で示せば、応募者が必要な情報をすぐに確認できます。
視認性を高める工夫を取り入れ、応募者がスムーズに理解できる構成を心がけてください。
アクセス方法を記載
応募者がスムーズに来社できるように、アクセス情報を詳しく記載することが重要です。
事前に詳細な情報を伝えることで、当日の迷いや遅刻を防ぐためです。
たとえば、「最寄駅:○○駅(○○線)」「駅からの道順:東口を出て直進し、○○ビル3階」と案内を付けると、迷う要素を減らせます。
応募者が安心して来社できるよう、道順や建物の特徴などを分かりやすく伝えてください。
返信をお願いする
来社依頼メールを送った後は、応募者からの返信を求めることで、意思確認を円滑に行えます。
返信をもらうことで相手の都合を把握し、必要に応じた調整ができるためです。
たとえば、「本メールを確認されましたら、お手数ですが○月○日までにご返信をお願いいたします」と記載すれば、応募者も対応しやすくなります。
スムーズなやり取りを実現するために、適切な返信依頼を含めるようにしましょう。
来社依頼メールの例文

来社依頼メールを作成する際は、応募者にとって分かりやすく、必要な情報が明確に伝わるように工夫することが重要です。
ここでは、具体的なシチュエーションに応じた来社依頼メールの例文を紹介します。
適切な表現を選び、応募者にとってスムーズな対応ができるよう配慮しましょう。
面接の案内
面接の案内メールは、日時や場所を明確に記載し、応募者が安心して来社できるよう配慮することが重要です。
また、持ち物や面接当日の流れについても簡潔に記載すると親切です。
件名:【◯◯株式会社】面接のご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございます。
書類選考の結果、ぜひ一度お会いしてお話をさせていただきたく、面接のご案内をいたします。
【面接詳細】
■ 日時:○月○日(○)○時~○時
■ 場所:○○株式会社 本社(○○ビル3階 受付)
■ 最寄駅:○○駅(○○線)徒歩○分
■ 持ち物:履歴書、職務経歴書
■ 担当者:○○(採用担当)
当日は受付にて「○○との面接」とお伝えください。
ご都合が合わない場合は、○月○日までにご希望の日時をお知らせいただけますと幸いです。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
それでは、お会いできるのを楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
メール:○○@example.com
電話:○○-○○○○-○○○○
会社見学や施設見学の依頼
会社見学を希望する応募者には、見学の目的や当日の流れを伝え、安心して参加できるように案内しましょう。
件名:【◯◯株式会社】会社見学のご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
弊社では、職場の雰囲気や業務内容について理解を深めていただくために、会社見学を実施しております。ぜひこの機会にご参加いただきたく、以下のとおりご案内申し上げます。
【会社見学の詳細】
■ 日時:○月○日(○)○時~○時
■ 場所:○○株式会社 本社(○○ビル3階 受付)
■ 内容:オフィス見学、業務説明、質疑応答
■ 持ち物:特に必要ありません
ご参加いただける場合は、○月○日までにご返信をお願いいたします。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
試験や実技テストの案内
筆記試験や実技試験を実施する場合は、試験の内容や持ち物を明確に伝え、当日の準備をしやすくしましょう。
件名:【◯◯株式会社】筆記試験のご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の選考にご応募いただき、誠にありがとうございます。
書類選考を通過されましたので、次の選考ステップとして試験を実施いたします。詳細は以下のとおりです。
【試験の詳細】
■ 日時:○月○日(○)○時~○時
■ 場所:○○株式会社 本社(○○ビル3階 受付)
■ 内容:筆記試験・適性検査(所要時間 約○時間)
■ 持ち物:筆記用具、身分証明書
ご都合が合わない場合は、○月○日までにご希望の日時をお知らせください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
採用プロセスの一環として
企業によっては、面接だけでなくオフィスでの簡単な業務体験やディスカッションを採用プロセスに取り入れることがあります。
その際の案内は、目的を明確に記載しましょう。
件名:【◯◯株式会社】選考に関するご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の選考にご参加いただき、誠にありがとうございます。
次のステップとして、より当社の業務内容をご理解いただくためのプログラムをご用意いたしました。
【プログラムの詳細】
■ 日時:○月○日(○)○時~○時
■ 場所:○○株式会社 本社(○○ビル3階 受付)
■ 内容:業務体験・グループディスカッション・面談
■ 持ち物:筆記用具、身分証明書
参加の可否を○月○日までにご返信いただけますと幸いです。
ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
インターンシップの案内
インターンシップの案内メールでは、プログラムの目的や実施期間、対象者の条件などを詳しく説明し、応募者が参加しやすいようにしましょう。
件名:【◯◯株式会社】インターンシップのご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたび、当社の業務をより深く理解していただく機会として、インターンシップを開催することとなりました。つきましては、以下のとおりご案内いたします。
【インターンシップの詳細】
■ 期間:○月○日(○)~○月○日(○)
■ 場所:○○株式会社 本社(○○ビル3階 受付)
■ 内容:業務体験、社員との交流会、プレゼンテーション
■ 応募条件:○○分野に関心のある方、○○大学の学生(学年不問)
参加をご希望の方は、○月○日までにご返信をお願いいたします。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
来社日程調整メールの例文

応募者とのスムーズな日程調整は、採用活動の効率化につながります。
相手が返信しやすいように、候補日を明示し、必要な情報を整理したうえでメールを作成しましょう。
ここでは、状況ごとに適した日程調整メールの例文を紹介します。
面接の日程調整
面接の日程調整メールでは、複数の候補日を提示し、応募者の都合に合わせられるよう配慮しましょう。
件名:【◯◯株式会社】面接日程の調整について
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございます。
面接の日程について、以下の候補日よりご都合のよろしい日時をお知らせください。
【面接候補日】
① ○月○日(○)○時~○時
② ○月○日(○)○時~○時
③ ○月○日(○)○時~○時
面接場所は○○株式会社本社(○○ビル3階 受付)となります。
ご希望の日時を○月○日までにご返信いただけますと幸いです。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
試験や実技テストの日程調整
試験や実技テストの日程調整では、試験の所要時間や持ち物についても明記し、応募者が準備しやすいようにしましょう。
件名:【◯◯株式会社】試験日程の調整について
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の選考にご参加いただき、ありがとうございます。
試験の日程について、以下の候補日よりご都合のよろしい日時をお知らせください。
【試験候補日】
① ○月○日(○)○時~○時
② ○月○日(○)○時~○時
③ ○月○日(○)○時~○時
【試験内容】
筆記試験・適性検査(所要時間:約○時間)
【持ち物】
筆記用具、身分証明書
ご希望の日時を○月○日までにご返信いただけますと幸いです。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
雇用契約に関する日程調整
内定者と雇用契約を結ぶ際は、契約手続きにかかる時間や必要書類を明確にし、スムーズに進められるよう配慮しましょう。
件名:【◯◯株式会社】雇用契約手続きの日程調整について
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは、当社の内定をお受けいただき、誠にありがとうございます。
雇用契約手続きのため、ご来社いただきたく、以下の候補日からご都合のよろしい日時をお知らせください。
【候補日】
① ○月○日(○)○時~○時
② ○月○日(○)○時~○時
③ ○月○日(○)○時~○時
【手続き内容】
雇用契約の締結・就業条件の説明(所要時間:約○時間)
【持ち物】
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・銀行口座情報(給与振込用)
ご希望の日時を○月○日までにご返信いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
候補日が決まっていない場合
応募者のスケジュールに柔軟に対応する場合は、相手に希望日を尋ねる形でメールを作成しましょう。
件名:【◯◯株式会社】面接日程のご相談
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の求人にご応募いただき、ありがとうございます。
面接の日程について、ご都合の良い日時をお伺いしたく存じます。
○月○日以降でご希望の日時をいくつかお知らせいただけますでしょうか。
弊社の対応可能な時間帯は、平日○時~○時となっております。
ご希望に沿えるよう調整いたしますので、○月○日までにご返信いただけますと幸いです。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
候補日が1日しかない場合
企業のスケジュールの都合上、特定の1日しか対応できない場合は、応募者が都合をつけやすいように丁寧に伝えましょう。
件名:【◯◯株式会社】面接日程のご案内
本文:
○○様
お世話になっております。○○株式会社 採用担当の○○です。
このたびは当社の求人にご応募いただき、ありがとうございます。
面接の日程につきまして、弊社のスケジュール上、以下の日程での実施をお願いしたく存じます。
【面接日時】
■ ○月○日(○)○時~○時
ご都合がつかない場合は、可能な範囲で調整いたしますので、○月○日までにご相談ください。
当日は受付にて「○○との面接」とお伝えください。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
――――
○○株式会社
採用担当 ○○
来社依頼メールのよくある疑問

来社依頼メールを送る際には、適切なタイミングや表現について疑問を持つ採用担当者も多いです。
ここでは、よくある質問とその回答を紹介し、正しいメール作成のポイントを解説します。
Q. 来社依頼メールを送るタイミングは?
来社依頼メールは、応募者がスケジュールを調整しやすいよう、できるだけ早めに送ることが重要です。
一般的には、面接や試験の5~7日前に送るのが適切です。
早すぎると忘れられる可能性があり、遅すぎると応募者の予定が埋まってしまうためです。
たとえば、面接を○月○日に実施予定の場合、○月○日~○月○日までにメールを送ると、相手が余裕を持って対応できます。
来社依頼メールは、面接や試験の5~7日前に送るのが望ましいでしょう。
Q.「当日お待ちしております」メールは必要?
来社依頼メールを送った後、面接当日にリマインドとして「お待ちしております」というメールを送るべきか悩むことがあります。
結論として、必須ではありませんが、送ることで応募者の安心感につながるため、推奨されます。
特に、1週間以上前に来社依頼メールを送った場合や、応募者が遠方から来る場合は、前日にリマインドメールを送ると親切です。
たとえば、「明日はどうぞお気をつけてお越しください」と一言添えると、応募者に安心感を与えられます。
前日にリマインドメールを送ると、応募者が安心して来社できるでしょう。
Q.「当日のお越しをお待ちしております」は変?
「当日のお越しをお待ちしております」という表現は、やや不自然に感じられる場合があります。
「お越し」は「来ること」を丁寧に表した言葉ですが、「当日のお越し」とすると、直訳すると「当日の来ること」となり、不自然な日本語になるからです。
たとえば、「当日はお待ちしております」や「当日はどうぞお気をつけてお越しください」などの表現がより適切です。
また、「当日のお越しをお待ちしております」の代わりに、「当日はお会いできるのを楽しみにしております」とすると、より自然な表現になるでしょう。
「当日のお越しをお待ちしております」よりも、「当日はお待ちしております」などの表現が自然です。
Q.「ご来訪お待ちしております」メールは必要?
「ご来訪お待ちしております」というメールを送る必要があるかどうかは、状況によります。
一般的に、来社依頼メールで日時や場所を明確に伝えていれば、追加で送る必要はありません。
ただし、直前にリマインドメールを送りたい場合や、応募者が不安に思っている可能性がある場合は、送ると親切になります。
たとえば、前日に「明日はどうぞお気をつけてお越しください」と一言添えておくと、応募者に安心感を与えられます。
基本的には不要ですが、リマインドとして送るのは有効といえるでしょう。
Q.「ご足労おかけします」の正しい使い方は?
「ご足労おかけします」は、相手がわざわざ足を運んでくれることに対する敬意を示す表現です。
ただし、応募者に対して使う場合は注意が必要です。
一般的に「ご足労」は目上の人に対して使うため、面接に来る応募者に使うのは不適切とされる場合があるからです。
たとえば、「遠方からお越しいただきありがとうございます」といった表現のほうが、応募者に対して適切になります。
「ご足労おかけします」は目上の人向けの表現のため、応募者には「お越しいただきありがとうございます」としましょう。
採用管理システムで来社依頼メールを効率的に

採用活動において、応募者への来社依頼メールを適切に管理することは重要です。
しかし、手作業での対応ではミスが発生しやすく、送信漏れや二重送信といったトラブルにつながる可能性があります。
そこで役立つのが採用管理システムです。
採用管理システムを活用すれば、メールのテンプレート化や自動送信機能により、業務の効率化と一貫性のある対応が可能になります。
また、応募者ごとの進捗状況を一元管理できるため、適切なタイミングでのメール送信がしやすくなります。
応募者とのスムーズなコミュニケーションを実現し、採用活動全体の質を向上させるために、採用管理システムを活用した来社依頼メールの運用を検討しましょう。
まとめ
来社依頼メールは、応募者との最初の重要な接点となるため、適切な内容とタイミングで送ることが大切です。
企業の第一印象を良くし、スムーズなコミュニケーションの基盤を作るためにも、明確で配慮のある文章を心がけてください。
件名をわかりやすくし、簡潔で正確な情報を伝え、読みやすいフォーマットを意識することで、応募者にとって分かりやすいメールになります。
また、アクセス方法や返信依頼を明記することで、当日のトラブルを防ぐことも可能です。
さらに、採用管理システムを活用すれば、来社依頼メールの送信を効率化し、ミスを防ぐことができます。
適切なメールを適切なタイミングで送ることで、応募者の不安を解消し、企業の信頼度を高めることができるのです。
応募者が安心して来社できるように、この記事で紹介したポイントを活用し、円滑な採用活動を実現してください。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...