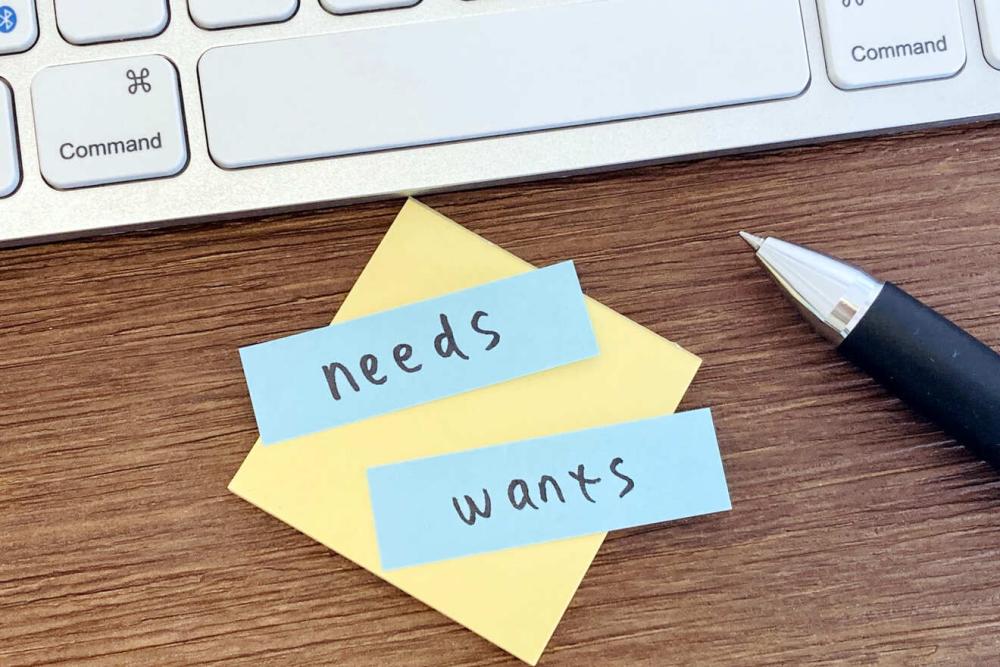何度も応募してくる人に困ったら?心理から断り方まで採用業務のヒントを紹介

不採用にしたのに、何度も応募してくる人がいると困りますよね。
断っても繰り返し応募されると、「どうにか穏便に解決したい」と思う気持ちわかります。
できることなら、ストレスなく採用業務を進めたいですよね。
実は、しつこい応募者への対応は、適切な方法を知ることで解決できます。
対応方法を間違わなければ、相手とトラブルになることもありません。
そこで今回は、「何度も応募してくる人の心理と対処法」について解説します。
採用業務がスムーズに進むように、的確な対応で負担を減らしてください。
何度も応募してくる人の心理

繰り返し応募する人の行動には、さまざまな心理的背景があります。
その理由を理解することで、適切な対応が可能になるのです。
そこで、何度も応募してくる人の心理について解説します。
どうしても入社したい
応募者が同じ企業に固執する理由は、強い思い入れがあるからです。
企業の理念やブランドに深く共感していたり、憧れの業界で働きたいという願望が強い場合があります。
特に大手企業や人気の業界では、この傾向が顕著です。
たとえば、「この会社で働くことが目標だった」と考えている応募者は、不採用の結果に納得せず、何度もチャレンジしようとします。
また、自分の熱意が伝われば結果が変わると信じている場合も多いです。
就活が上手くいっていない
就職活動や転職活動が長引くと、選択肢が限られ、同じ企業への応募が繰り返されることがあります。
他の求人に応募できない事情や、スキル不足が原因である場合が多いです。
特に競争率の高い職種では、候補者が選べる求人が少ないことが問題になります。
具体的には、地域や業界に特化した求職者が、「この企業しかない」と考え、繰り返し応募するケースがあります。
希望の仕事を得るために必死になっているため、諦めきれないのでしょう。
企業に対する理解不足
企業について十分に理解しないまま応募してくる人もいます。
企業の求めるスキルや業務内容を把握せずに、自分の経歴が適していると思い込んでいるケースです。
例として、応募資格に特定の経験やスキルが必要と記載されているのに、それを満たしていない人が「面接を受けられるはず」と誤解して応募を続ける場合が挙げられます。
こうした誤解を防ぐためには、採用情報を分かりやすく提示し、基準を明確に伝える努力が求められるでしょう。
不採用理由に気づいていない
不採用の理由が明確でない場合、応募者は改善点に気づかずに再応募を続ける場合があります。
不採用のフィードバックがなかったり、曖昧な理由で断られたと感じた場合、まだ可能性があると思い込むからです。
たとえば、履歴書に問題があるのに、それが原因だと気づかず、「面接まで進めばチャンスがある」と考えて再応募するケースがあります。
この場合、自己評価と企業の評価にギャップが生じているのでしょう。
不採用を受け入れられない
採用結果を感情的に受け止め、不採用を認めたくないと感じる人もいます。
この心理の背景には、自尊心を守りたい気持ちや、断られたことへの反発心があるのです。
具体的には、「どうしても納得できない」と何度も再応募してくる人や、不採用の理由を問いただす行動に出る人がいます。
感情的な心理が原因で冷静さを失い、行動がエスカレートするので注意しなければいけません。
何度も応募してくる人への断り方

応募者に対して適切な断り方を実践することで、双方が納得しやすい結果を得られます。
ここからは、何度も応募してくる人への断り方について解説します。
丁寧にお断りする
応募者には、丁寧かつ誠実に断りの意向を伝えることが基本です。
どのような理由であっても、応募者が企業に時間を割いている点を尊重し、適切な言葉遣いを心がけてください。
たとえば、「ご応募ありがとうございます」という感謝の言葉から始め、選考基準に基づき慎重に判断した結果、不採用となった旨を伝えます。
丁寧な対応を心がけることで、応募者が納得しやすく、再応募のリスクを低減できるでしょう。
具体的にアドバイスする
応募者に不採用を理解してもらうために、具体的なアドバイスを伝えてください。
不採用理由をただ伝えるのではなく、次回に向けての改善点を示すことで、応募者にとって有益な情報を提供できます。
たとえば、「当社が求める条件である◯◯と一致しなかったため」など理由を明示します。
「〇〇スキルをさらに磨くと良い結果につながる可能性があります」といったフィードバックを添えるとわかりやすいです。
前向きなアドバイスを伝えることで、応募者が自身を見直す機会を得るでしょう。
企業の方針を伝える
企業としての採用方針や基準を明確に伝えることも有効な対応策です。
応募者に対して、公平で客観的な基準に基づいて選考していることを理解してもらうことで、不必要なトラブルを回避できます。
具体的には、「現在の採用方針では、即戦力のある方を優先しています」と伝えることで、応募者は企業の状況や方針を理解しやすくなります。
また、他の応募者との比較ではなく、基準に基づいて判断したことを説明するのも効果的です。
明確な説明を行うことで、応募者が納得する可能性が高まるでしょう。
応募資格を再確認する
応募条件や資格を再度伝えることで、不要な再応募を防ぐことができます。
採用基準を明確に記載していても、応募者がそれを十分に理解していない場合があるからです。
具体例として、「応募資格に5年以上の実務経験が必要としています。今回はそれに該当しないため選考が難しい状況です」と伝えるとします。
事前に応募資格をしっかり共有することで、無駄な応募を減らすことができるでしょう。
専門機関への相談を勧める
応募者が自社に固執してくる場合、専門機関への相談を勧めることも一つの選択肢です。
第三者の意見を聞くように促すことで、客観的な視点で見るように誘導します。
具体的には、「転職エージェントに相談されてはいかがでしょうか?」などと言って、外部リソースを案内するようにしてください。
応募者に必要なサービスを案内することで、他の可能性を見つける手助けとなるでしょう。
再応募お断りメール例文
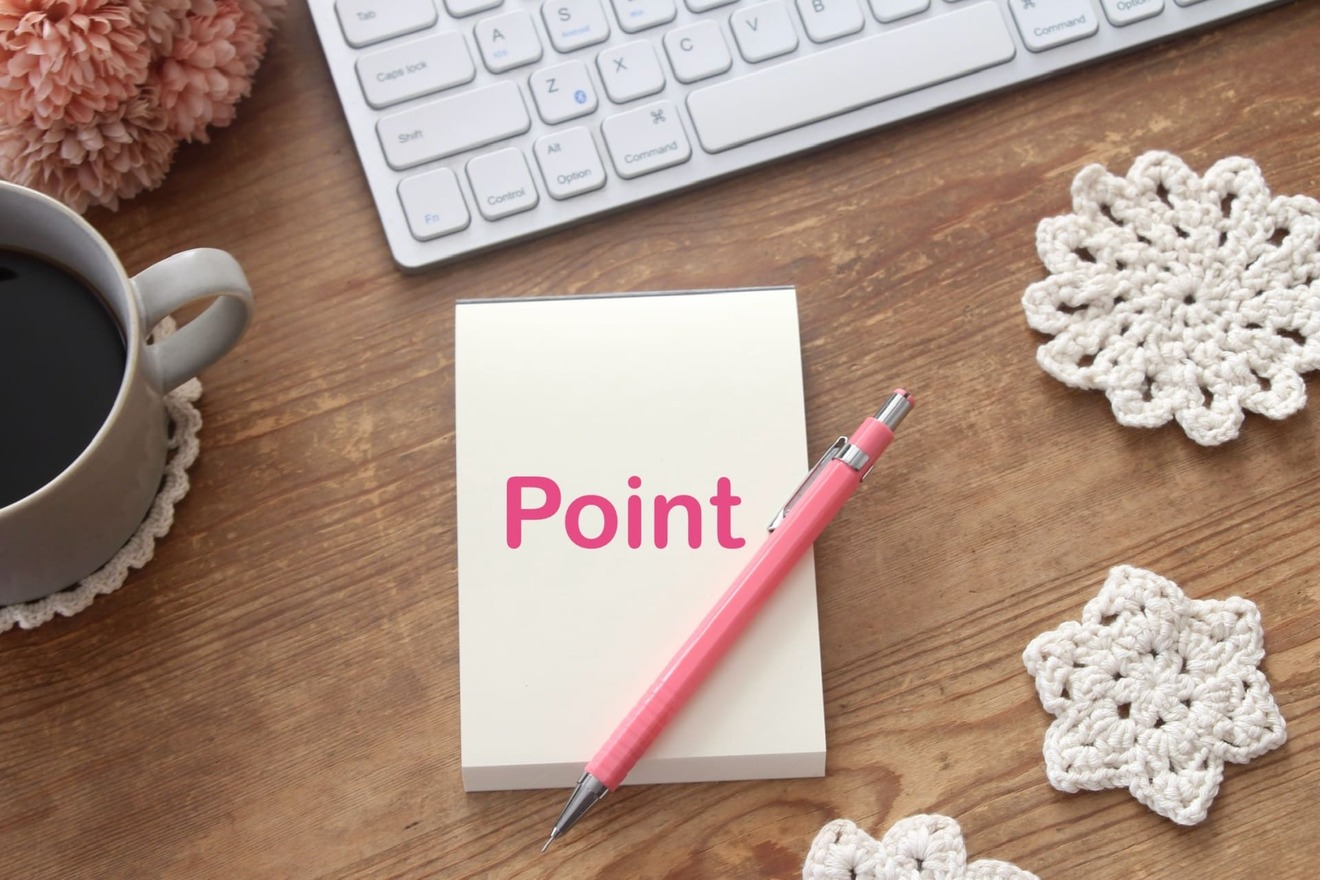
再応募に対する断り方は、応募者の状況や理由に応じて適切に対応することが求められます。
以下に、具体的なシチュエーションに合わせた断り方とメール例文を紹介します。
前回の結果を踏まえた断り方
応募者が前回の選考結果を受けて再度応募してきた場合、過去の結果を踏まえた断り方が必要です。
この場合、過去の選考内容を尊重しつつ、現在の状況では選考を進めることが難しい旨を伝えると良いでしょう。
メール例文)
件名:ご応募についてのお知らせ
〇〇様
平素よりお世話になっております。
このたびは再度当社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございます。
前回の選考において慎重に検討させていただいた結果、残念ながら採用を見送らせていただいた経緯がございます。
現在も同様の選考基準を適用しておりますため、今回の再応募においても選考を進めることが難しい状況でございます。
貴意に沿えず恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
引き続き、〇〇様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具
株式会社〇〇
採用担当:△△
複数回の応募に対するな断り方
同じ応募者から複数回にわたり応募がある場合、企業の採用方針を明確に伝えつつ、再応募を控えるようお願いすることが適切です。
メール例文)
件名:ご応募についてのお願い
〇〇様
平素より当社にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
このたび、再度当社にご応募いただきました件について、慎重に検討を行った結果、前回と同様、採用を見送らせていただくこととなりました。
当社では、選考基準に基づき、応募者の皆様を公平に評価しておりますが、今回の結果も同基準に基づくものでございます。
また、誠に恐縮ではございますが、現状ではこれ以上の再応募についてはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
〇〇様の今後のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
敬具
株式会社〇〇
採用担当:△△
応募資格を満たしていない場合
応募者が応募要件を満たしていない場合には、要件を明確に伝えたうえで、選考が難しいことを通知します。
応募者に対して公平性を保つためにも、具体的な理由を提示することが重要です。
メール例文)
件名:応募資格に関するお知らせ
〇〇様
このたびは、当社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございます。
お送りいただいた履歴書や職務経歴書を拝見いたしましたが、誠に残念ながら、今回の募集における応募資格に合致しないため、選考を進めることが難しい状況でございます。
具体的には、今回のポジションでは〇〇の経験(例:業界経験3年以上)が必要とされており、現時点で条件を満たしていないことが確認されました。
貴意に沿えず誠に申し訳ございませんが、今後も〇〇様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具
株式会社〇〇
採用担当:△△
しつこい応募者への対応方法

繰り返し応募を続ける人や粘り強く連絡を取ろうとする応募者には、適切な対応が必要です。
状況に応じた対策を講じることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
毅然とした態度をとる
応募者の行動がしつこい場合は、毅然とした態度で対応することが大切です。
曖昧な返答や弱い姿勢を見せると、応募者がさらに行動をエスカレートさせる可能性があります。
たとえば、「ご応募いただきましたが、採用基準に合致しないため、これ以上の選考は難しいです」と端的に伝えることが挙げられます。
毅然とした態度を示すことで、相手にこれ以上の連絡は控えるべきだと認識させることができるでしょう。
書面で不採用通知を送る
しつこい応募者には、正式な書面で不採用通知を送ることが有効です。
口頭やメールでは曖昧さが残りやすいですが、正式な文書で通知を行うことで、不採用の意図をしっかり伝えられます。
具体的には、「先日の応募に関する選考結果について正式にお知らせいたします」という文面で始め、不採用の理由と今後の対応方針を記載した書類を送付します。
書面での通知は、法的トラブルを防ぐための証拠としても活用できるでしょう。
緊急連絡先に相談する
忠告しても理解してくれない応募者には、緊急連絡先に相談してください。
多くの応募者は親を緊急連絡先にしているため、事態を適切に収束させることが可能です。
緊急連絡先に電話して経緯を説明すれば、応募者を諌めてもらうことができます。
第三者の力を借りることで、自社の負担を軽減できるでしょう。
返信しない(無視する)
しつこい連絡には、返信を控えるのも時には必要です。
返信を続けると相手の行動を助長する恐れがあるため、一定の段階で連絡を控える判断をしてください。
たとえば、複数回のメールや電話があった場合、「これ以上の対応は控えさせていただきます」という最後通告を行い、それ以降は完全に無視します。
適切なタイミングで連絡を止めることで、事態のエスカレートを防げるでしょう。
着信拒否やメールブロック
連絡が止まらない場合は、着信拒否やメールのブロックを実施してください。
こうした措置は、企業側のリソースを守るためにも必要な対応です。
相手からの連絡を物理的に遮断することで、問題の長期化を防ぎます。
具体的には、応募者の電話番号やメールアドレスを登録しているシステムで「拒否設定」を行い、企業へのアクセスを制限します。
着信拒否やブロックは、しつこい連絡を確実に止める手段となるでしょう。
何度も応募してくる人への疑問

繰り返し応募してくる人に対して、企業側が抱く疑問は多岐にわたります。
その心理や行動の背景を知り、適切に対応するための理解を深めることが大切です。
Q.何度も応募してくる人の真意は?
何度も応募してくる人の真意は、企業に強い興味がある場合や個人的な執着が理由であることが多いです。
特定の企業に強く惹かれている場合、応募者は「どうしても入社したい」という気持ちを持っています。
一方で、不採用の理由を理解できず、試行錯誤を重ねている可能性も考えられます。
真意を理解することで、適切な対応を取りやすくなるでしょう。
Q.面接で問題があるから何度も応募してくる?
面接の結果が芳しくなかった場合、応募者はそれを改善しようと再挑戦する場合があります。
面接におけるコミュニケーションやスキル不足が原因で不採用となる場合、応募者はその問題点を認識して改善を試みるからです。
しかし、十分な準備ができていないまま再応募を繰り返す人も少なくありません。
具体的には、「前回の面接では緊張して本来の自分を伝えられなかったため、再度チャンスが欲しい」といった理由を述べてくる場合があります。
このようなケースでは、改善の具体性を見極める必要があるでしょう。
Q.応募の時点で不採用にするのはあり?
応募の時点で不採用にすることは、慎重な判断が求められます。
なぜなら、面接もせずに不採用にすることで、不満を増長させる可能性があるからです。
そのため、断りのメールなどで、具体的に不採用の理由を伝える必要があります。
たとえば、「実務経験が5年以上の方を対象としています」と説明すれば、面接に至らなかった理由が理解できます。
単に再応募だから断るのではなく、明確な理由を持って不採用にしてください。
Q.不採用が法律的に問題になる可能性はある?
日本の労働法では、採用の自由が認められているため、企業が採用・不採用を判断する権利があります。
しかし、差別的な理由や応募者のプライバシーを侵害する行為は違法となるため、注意が必要です。
具体例として、年齢や性別、出身地を理由に不採用を決めた場合、応募者から訴えられる可能性があります。
また、不採用理由を説明せずに簡素な断り方をすると、粗暴な態度としてネットで晒されるかもしれません。
企業ブランドを守るためにも、公平かつ透明性のある対応を心がけるようにしましょう。
Q.応募者の行動がエスカレートしてきたら?
応募者の行動がエスカレートした場合、早急に対策を講じる必要があります。
過度な連絡や直接訪問などの行為がある場合、専門機関や警察への相談も視野に入れるべきです。
たとえば、応募者が電話やメールを繰り返すだけでなく、採用担当者を待ち伏せするような場合、即座に警察に通報してください。
エスカレートした行動には、迅速かつ専門的な対応が必要になるでしょう。
採用管理システムでしつこい応募者を避ける

しつこい応募者への対応を効率化するには、採用管理システムの活用が有効です。
応募情報を一元管理し、過去の応募履歴や不採用理由を即座に確認できるため、繰り返し応募する人を簡単に特定できます。
また、特定の条件を満たさない応募を自動的にフィルタリングしたり、不採用通知をテンプレートで迅速に送信できるシステムもあります。
採用をシステム管理することで、採用担当者の負担を軽減し、対応漏れやミスを防ぐことが可能です。
特に中小企業では、限られたリソースを有効活用するために、こうしたツールを導入することで業務効率を大幅に向上させられるでしょう。
当サイトでは、100以上の機能が実装された採用管理システムを提供しています。
しつこい応募者を避けるためにも、ぜひ導入をご検討ください。
まとめ
「何度も応募してくる人」への対応は、採用担当者にとって頭を悩ませる課題の一つです。
しかし、その心理を理解し、適切な対応を行うことで、企業としての信頼感を高めることができます。
繰り返し応募してくる人の背景には、「どうしても入社したい」という熱意や、「就職活動がうまくいかない」という現状があります。
これらを踏まえた丁寧な断り方やアドバイスを心がけることで、円滑なコミュニケーションが可能になるでしょう。
また、採用管理システムの導入は、しつこい応募者の対応を効率化し、トラブルを防ぐための強力な手段です。
さらに、法律的なリスクを考慮しつつ、お断りメールを送信することで、採用業務をよりスムーズに進めることができます。
何度も応募してくる人への対応は難しいですが、自社の方針をしっかりと伝えながらも、公平で透明性のある対応を心がけてください。
このような工夫を取り入れることで、採用活動がより前向きで効果的なものになるでしょう。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...