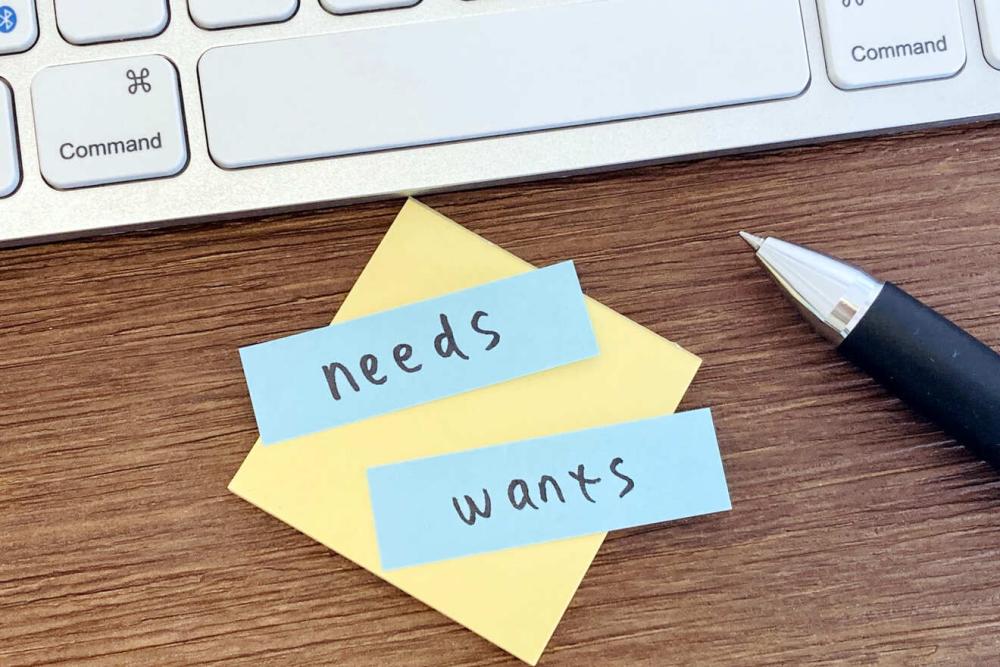書類選考のやり方とは?採用成功のポイントと具体的な手順

書類選考のやり方は、意外と難しいですよね。
応募者の経歴をしっかり見極めなければならないのに、何を基準に判断すればよいのか迷ってしまう気持ちわかります。
できることなら、効率的に良い人材を見極めて、スムーズに選考を進めたいですよね。
実は、明確な基準と手順に沿って進めることで、選考の精度を高めながら負担を軽減できます。
書類選考がスムーズになれば、無駄な面接が減り、採用のミスマッチは起こりません。
そこで今回は、「効果的な書類選考のやり方」についてご紹介します。
書類選考の方法が明確になれば、より優秀な人材を見極められるようになるでしょう。
書類選考の必要性
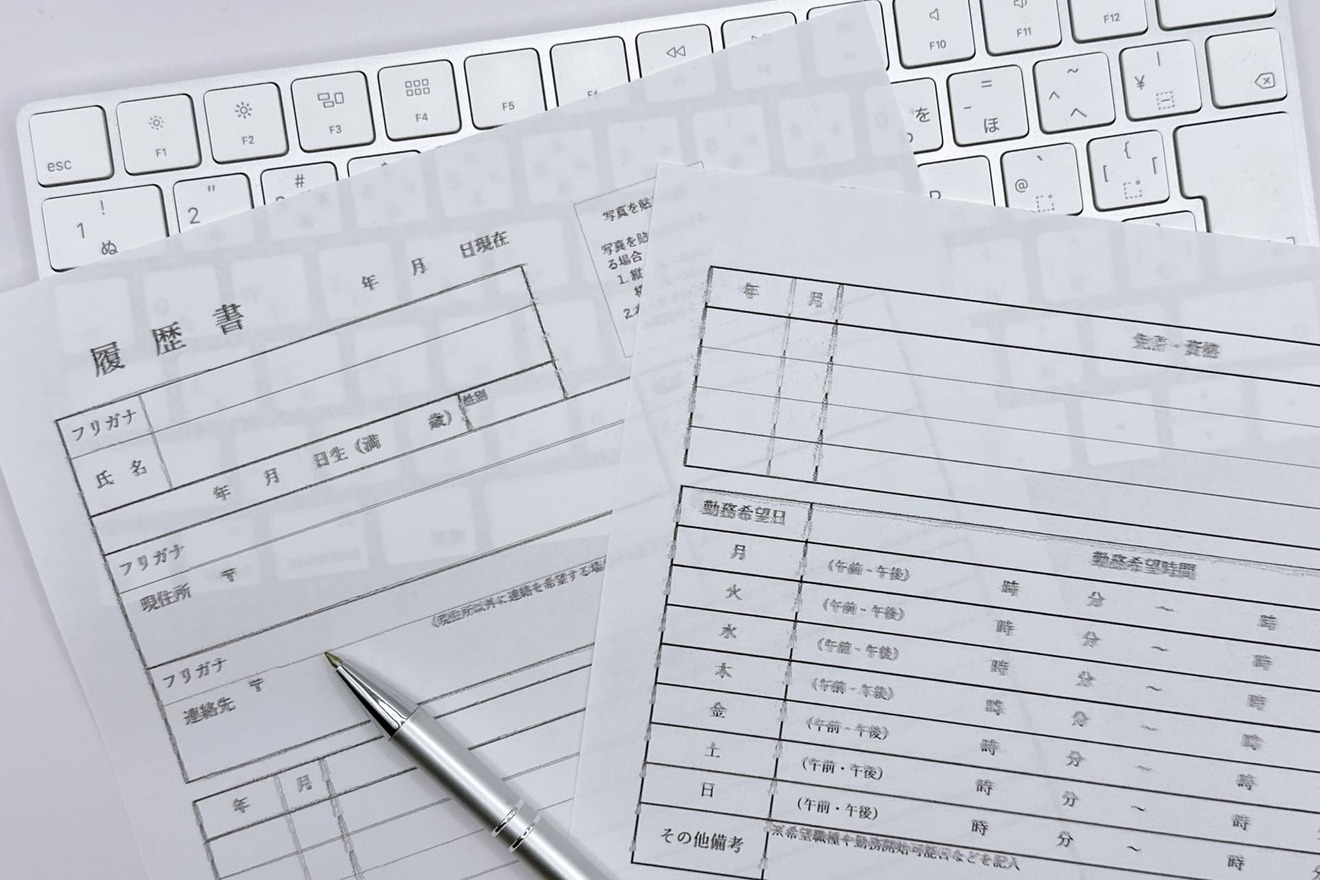
採用活動において、書類選考は欠かせないステップです。
適切な書類選考を行うことで、効率的に候補者を選び、企業にとって最適な人材を見極めることができます。
限られた時間とリソースの中で、より精度の高い選考を実施するためにも、書類選考の役割を正しく理解することが重要です。
応募者を絞り込むため
多くの応募者の中から、自社の求める基準に合った人材を選別することが必要です。
書類選考を行うことで、必要なスキルや経験を持つ応募者を選び、不適格な候補者を除外できるためです。
たとえば、特定の資格や業務経験が必須の職種では、応募者の職務経歴書を確認することで、基準を満たしているか判断できます。
適切な絞り込みを行うことで、採用のミスマッチを減らし、効率的な選考を進められるでしょう。
無駄な面接を防ぐ
事前に応募書類を確認することで、面接の手間を減らし、選考の効率を向上させることができます。
書類選考を実施しないと、明らかに要件を満たさない応募者との面接が発生し、時間と労力を無駄にする可能性があるためです。
たとえば、英語力が必須のポジションにもかかわらず、書類で英語スキルの確認をせずに面接を行うと、不適切な応募者に時間を割くことになります。
面接を有意義な時間にするためにも、書類選考を適切に実施してください。
応募者のスキルを把握
書類選考を通じて、応募者が持つスキルのレベルや適性を事前に確認することが可能です。
応募書類には職務経歴や資格が記載されており、それらを精査することで、応募者の実力を判断できるためです。
例として、プログラマーの採用では、履歴書や職務経歴書に記載されたプログラミング言語の経験年数や、過去のプロジェクト内容を確認することで、スキルの妥当性を見極められます。
事前にスキルを把握することで、自社の求めるレベルに合った人材を選びやすくなるでしょう。
文化フィットを見極める
企業文化に合った人材を選ぶためにも、書類選考は重要な役割を果たします。
スキルや経験だけでなく、応募者の価値観や働き方が企業の方針に適しているかを判断する必要があるためです。
具体的には、チームワークを重視する会社であれば、応募者の職務経歴書や自己PR欄から、チームでの業務経験や協調性を示す記述があるかを確認することができます。
企業文化に合う人材を選ぶことで、入社後の定着率やパフォーマンスの向上につながるでしょう。
選考プロセスを効率化
書類選考を適切に行うことで、採用活動全体のスムーズな進行が可能になります。
候補者を事前に絞り込むことで、面接や最終選考の負担を軽減し、採用の質を向上させられるからです。
大量の応募がある場合でも、書類選考の段階で適格な候補者を抽出すれば、面接官の負担を減らし、スピーディーな採用決定が可能になります。
効率的な選考プロセスを構築することで、採用担当者の業務負担を軽減できるでしょう。
書類選考の具体的な手順

書類選考をスムーズに進めるためには、明確な手順を定めることが重要です。
応募書類の受付から社内共有までの流れを標準化することで、判断のブレを防ぎ、採用の精度を向上させることができます。
ここでは、書類選考を適切に行うための具体的なステップを解説します。
応募書類の受付
応募書類を適切に管理し、選考プロセスを円滑に進めるための準備を行います。
書類の受け取りが適切に行われないと、紛失や確認漏れが発生し、候補者に不利益を与える可能性があるためです。
具体的には、応募があった際に、履歴書・職務経歴書をデータベースに保存し、応募者ごとに整理することで、後の選考がスムーズになります。
応募書類を正確に管理し、選考漏れがないように注意してください。
応募者の基本情報確認
応募者の名前、連絡先、学歴、職歴などの基本情報をチェックします。
基本情報に誤りがあると、連絡ミスや選考の混乱を招く恐れがあるためです。
たとえば、履歴書に記載されたメールアドレスや電話番号が正しいかを確認し、必要に応じて候補者に修正を依頼することで、円滑なやり取りが可能になります。
最初の確認作業を徹底することで、スムーズな選考につなげましょう。
スキルと経験の照合
応募者のスキルや職務経験が、採用ポジションの要件に合致しているかを確認します。
必要なスキルを満たしていない応募者を選考に進めると、後の面接でミスマッチが発生する可能性が高いためです。
たとえば、プログラマーの採用では、職務経歴書に記載されたプログラミング言語や開発経験の有無を確認し、求めるスキルと一致しているか判断します。
適切なスクリーニングを行うことで、より精度の高い選考ができるでしょう。
志望動機・自己PRの評価
応募者の志望動機や自己PRが、自社の求める人材像と合致しているかを見極めます。
志望動機や自己PRが不明瞭な場合、入社後の定着率が低くなる可能性があるためです。
例として、「貴社の理念に共感し、成長できる環境で働きたい」と記載があれば、企業文化への適応度を評価できます。
応募者の熱意や価値観を確認し、適切な候補者を選びましょう。
不明点や疑問点の整理
書類選考の段階で疑問点を洗い出し、面接で確認すべき事項を整理します。
応募書類だけでは判断できない情報がある場合、そのまま進めると適切な評価が難しくなるためです。
たとえば、職務経歴書にブランク期間がある場合、その理由や当時の状況について面接で質問できるようにメモを残しておきます。
事前に疑問点を明確にすることで、面接をより有意義なものにできるでしょう。
書類選考結果の通知
合格・不合格の結果を応募者に速やかに連絡します。
通知が遅れると、応募者の不安が高まり、企業の信頼にも影響を与えるためです。
たとえば、選考結果をメールで通知する場合、テンプレートを用意しておくと迅速な対応が可能になります。
応募者に対して誠実な対応を心がけ、選考結果を適切に伝えてください。
選考結果を社内で共有
書類選考の結果や評価ポイントを社内で共有し、次の選考に備えます。
社内での情報共有が不足すると、面接官ごとに評価基準が異なり、公平な選考が難しくなるためです。
具体的には、選考結果を採用管理システムに記録し、採用チーム全体が確認できるようにすることで、一貫性のある評価が可能になります。
選考プロセスの透明性を高め、より良い採用判断につなげましょう。
書類選考を成功させるためのポイント

書類選考の精度を高めることで、採用の成功率を向上させることができます。
基準を明確にし、応募書類を丁寧に確認することで、適切な人材を見極められます。
また、スキルや実績だけでなく、志望動機や企業文化との相性も考慮することが重要です。
ここでは、書類選考を成功させるための具体的なポイントを解説します。
選考基準を明確にする
採用する人材の要件を具体的に定め、選考のブレを防ぐことが重要です。
選考基準が曖昧だと、評価が担当者ごとに異なり、公平な選考ができなくなるためです。
たとえば、「3年以上の実務経験」「特定の資格保有」「チームでの業務経験があること」など、数値や具体的な条件を設定すると、一貫した評価が可能になります。
明確な基準を設定することで、効率的かつ公平な選考ができるでしょう。
応募書類を丁寧に確認
書類の細部まで目を通し、重要な情報の見落としを防ぎます。
表面的なチェックだけでは、応募者の強みや適性を正しく判断できないためです。
具体的には、職務経歴書の業務内容を細かく確認することで、応募者のスキルや経験の深さを把握できます。
書類を丁寧に精査することで、優秀な人材を見逃すリスクを減らせるでしょう。
重要なスキルに注目
職種ごとに必要なスキルを明確にし、応募者の能力が要件を満たしているか確認します。
求めるスキルを正しく評価できないと、採用後のミスマッチにつながるためです。
例として、エンジニア職であれば、プログラミング言語の習熟度やプロジェクト経験、営業職であれば顧客対応の実績などを重点的にチェックします。
必要なスキルに注目することで、即戦力となる人材を見極められるでしょう。
志望動機を重視する
応募者の志望動機を確認し、入社後の定着度や意欲を見極めます。
志望動機が不明確な場合、入社後にモチベーションが低下し、早期離職のリスクが高まるためです。
たとえば、「企業理念に共感している」「特定の業務に強い関心を持っている」など、具体的な理由が記載されている応募者は、長く活躍する可能性が高いと判断できます。
志望動機をしっかり評価し、意欲の高い人材を採用しましょう。
過去の実績を確認する
応募者のこれまでの成果や貢献度をチェックし、実力を評価します。
過去の実績を確認せずに採用すると、期待したパフォーマンスが得られない可能性があるためです。
たとえば、「売上を○%向上させた」「○件のプロジェクトを成功させた」など、具体的な成果が書かれているかを確認すると、実力を適切に判断できます。
実績を重視することで、即戦力となる人材を選びやすくなるでしょう。
自社の文化に合うか評価
スキルや経験だけでなく、企業文化や価値観に合う人材かどうかを見極めます。
文化に合わない人材を採用すると、チームの調和が乱れ、早期退職につながる可能性があるためです。
たとえば、「挑戦を重視する企業」なら、応募者が過去に新しい業務に積極的に取り組んだ経験があるかを確認すると、適性が判断しやすくなります。
企業文化との適合性を評価することで、長く活躍できる人材を採用しやすくなるでしょう。
フィードバックと改善
選考の過程を振り返り、より良い評価基準やプロセスを確立していきます。
改善を行わなければ、非効率な選考が続き、優秀な人材を見逃すリスクが高まるためです。
たとえば、過去の選考で「書類で見抜けなかったポイント」があれば、評価項目を追加したり、質問内容を変更したりすることで、選考の精度を高められます。
継続的な改善を行うことで、より効果的な採用活動が実現できるでしょう。
書類選考で避けるべきNG行動
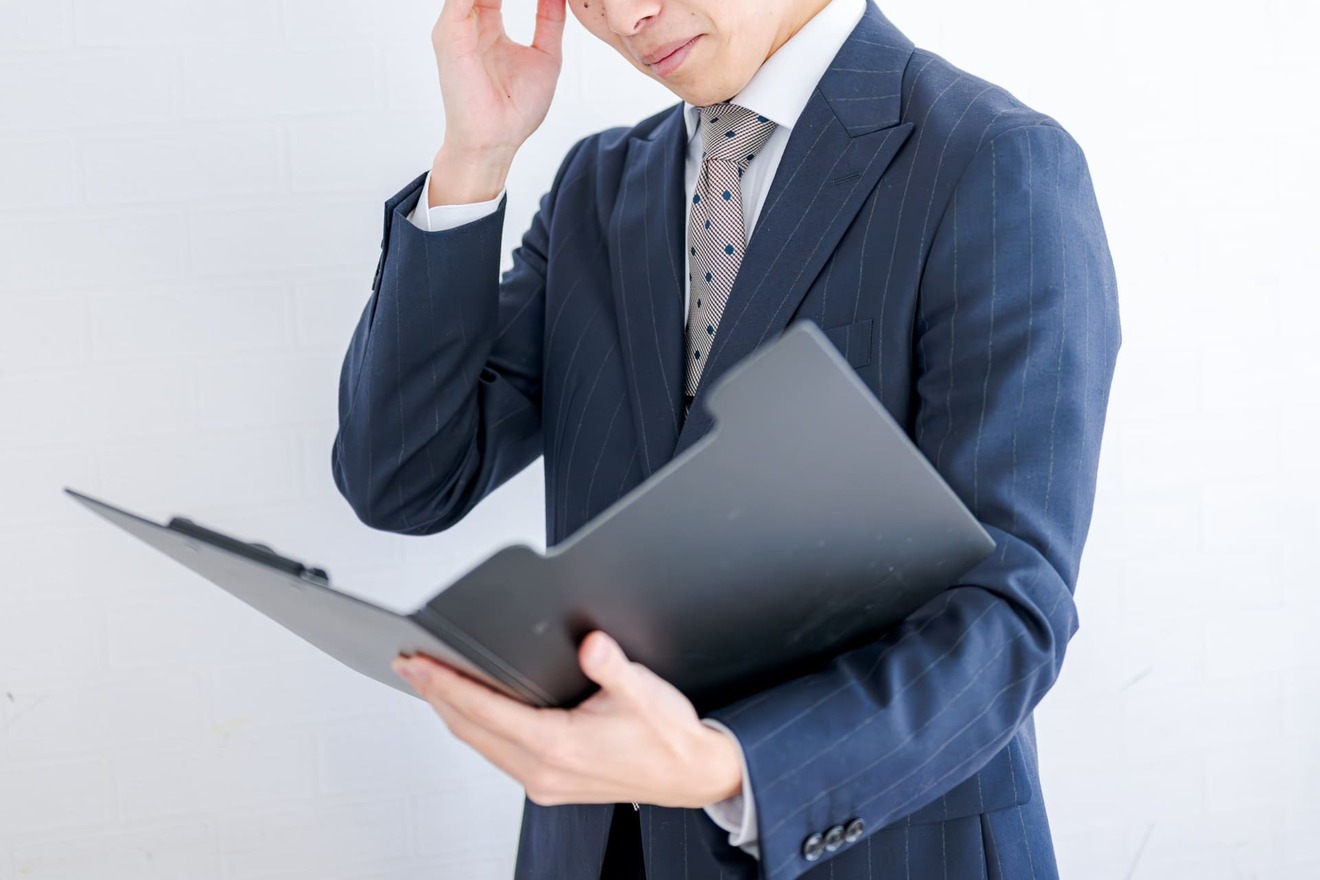
書類選考の段階でミスをすると、不適切な応募者を面接に進めてしまったり、優秀な人材を逃してしまったりする可能性があります。
特に、不完全な書類の見落としや評価基準のズレなどは、採用の質を大きく左右します。
ここでは、採用担当者が注意すべきNG行動について解説します。
不完全な書類を見逃す
記入漏れや必要書類の不足がある応募をそのまま選考に進めると、後の手続きで問題が発生する可能性があります。
応募者が提出すべき情報が揃っていないと、正確な評価ができず、適切な人材を選びにくくなるためです。
たとえば、履歴書に連絡先が記載されていなかったり、職務経歴書が添付されていなかったりする場合、それを見落とすとスムーズな採用プロセスが進められません。
応募書類の不備を見逃さないよう、チェックリストを活用して確認することが重要です。
誤字や不適切な表現
応募書類の誤字や不適切な表現を軽視すると、応募者の細部への注意力やビジネスマナーを見落とすことになります。
誤字や表現ミスが多い応募者は、業務においても同様のミスをする可能性が高いためです。
例として、履歴書や職務経歴書に誤字脱字が多い場合、細かい作業を丁寧に行う能力が不足している可能性が考えられます。
文章の正確さや適切な表現を重視し、応募者のビジネススキルを慎重に評価しましょう。
評価基準の不一致
採用担当者ごとに評価基準が異なると、公平な書類選考ができなくなります。
選考基準が統一されていないと、採用の方向性がブレてしまうためです。
たとえば、ある担当者は学歴を重視し、別の担当者は実務経験を重視すると、一貫性のない評価になり、適切な人材選びが難しくなります。
評価基準を事前に明確にし、採用チーム全体で共有することで、公平な選考が実施できるでしょう。
面接に進ませすぎる
十分な書類選考を行わず、多くの応募者を面接に進めると、採用プロセスが非効率になります。
面接の負担が増えることで、採用担当者のリソースが圧迫され、重要な応募者を見極める時間が減るためです。
たとえば、スキルや経験が明らかに不足している応募者を面接に進めると、面接時間が無駄になり、結果的に採用の質が低下する可能性があります。
書類選考の段階で適切な選別を行い、本当に面接が必要な応募者だけを進めることが重要です。
応募者への連絡が遅れる
書類選考の結果を応募者に伝えるのが遅れると、採用の機会を逃してしまう可能性があります。
応募者は複数の企業に応募していることが多く、選考結果の通知が遅いと、他社へ流れてしまうためです。
仮に、書類選考に2週間以上かかると、優秀な人材はすでに他の企業から内定を得ている可能性が高くなります。
迅速な連絡を心がけることで、採用の機会損失を防ぎ、スムーズな採用活動を進められるでしょう。
書類選考のやり方に関する疑問

書類選考を進めるうえで、多くの採用担当者が疑問に思うポイントがあります。
特に、応募者が多い場合の対応や、履歴書と職務経歴書の優先度、見落としがちなポイントなどは、適切に判断することが重要です。
ここでは、よくある疑問について詳しく解説します。
Q.応募者が多いときはどのように効率化する?
応募者が多い場合、書類選考の負担が増し、時間がかかりすぎることがあります。
しかし、選考の基準を明確にし、優先順位をつけることで、効率的に進めることができるのです。
たとえば、学歴や経験年数などの最低基準を設定し、それを満たさない応募者を最初に除外することで、残りの候補者に集中できます。
採用管理システムを活用し、自動スクリーニングやキーワード検索を利用すると、選考作業の負担を大幅に軽減できるでしょう。
Q.履歴書と職務経歴書どちらを優先すべき?
履歴書と職務経歴書は、それぞれ異なる情報を提供するため、どちらか一方だけを優先するのは適切ではありません。
履歴書は基本情報や志望動機、職務経歴書は具体的な業務経験を示しており、両方を総合的に判断することが重要なためです。
たとえば、履歴書の志望動機が企業の方向性と一致していても、職務経歴書の実績が不足している場合、採用には適さない可能性があります。
応募者の適性を正しく判断するために、履歴書と職務経歴書の両方をバランスよく確認しましょう。
Q.書類選考で見落としがちな重要項目は?
応募者の経歴を評価する際、実績やスキルに注目しすぎると、他の重要な要素を見落とす可能性があります。
特に、応募者の「仕事に対する姿勢」や「企業文化との適合性」は、長期的な活躍に大きく影響するからです。
具体的には、これまでの業務経験が豊富でも、チームワークを重視する企業に対して協調性が欠ける応募者では、組織に馴染めないことがあります。
スキルだけでなく、志望動機や自己PRを確認し、応募者の価値観や働き方のスタイルも総合的に評価することが大切です。
Q.不合格者にはどこまで伝えるべき?
書類選考で不採用となった応募者には、どの程度の情報を伝えるべきか迷うことがあります。
詳細なフィードバックを行う義務はありませんが、適切な対応をすることで企業の印象を良くできるためです。
例として、「今回は他の応募者との比較の結果、不採用となりました」と伝えるだけでも、応募者に対して誠実な対応になります。
不採用理由を細かく伝える必要はありませんが、簡潔で丁寧な連絡を心がけることで、自社の信頼を維持できるでしょう。
Q.書類選考でリファレンスチェックは必要?
書類選考の段階でリファレンスチェックを行うかどうかは、採用方針や企業の文化によります。
リファレンスチェックを活用すると、応募者の実際の働きぶりや人物像をより正確に把握できるのです。
たとえば、前職の上司や同僚から「業務遂行能力は高いが、チームワークに難がある」といったフィードバックを得ることで、採用リスクを減らせます。
リファレンスチェックを実施する場合は、応募者の同意を得たうえで、適切な範囲で情報収集を行うことが望ましいです。
採用管理システムで書類選考を効率化

書類選考は採用プロセスの中でも時間と労力がかかる工程の一つですが、採用管理システム(ATS)を活用することで、大幅な効率化が可能です。
応募者のデータ管理や書類の自動スクリーニング、選考状況の共有などがシステム上で一元化されるため、手作業による負担を減らし、迅速な選考が実現できます。
また、応募者の情報を蓄積・分析することで、より精度の高い人材選定が可能になり、採用の質を向上させることにもつながります。
特に、応募者が多い場合や採用基準が複雑な場合には、採用管理システムを導入することで、選考の公平性を保ちつつ、スムーズな採用活動を進められるでしょう。
まとめ
書類選考は、応募者を適切に絞り込み、無駄な面接を防ぎながら、スキルや文化フィットを見極めるために重要なプロセスです。
適切な手順を踏むことで、より精度の高い選考が可能になります。
応募書類の受付から基本情報の確認、スキル・経験の照合、志望動機の評価、不明点の整理、結果通知、社内共有までをスムーズに進めることが、効率的な採用につながるでしょう。
また、書類選考を成功させるためには、選考基準を明確にし、応募書類を丁寧に確認しながら、重要なスキルや過去の実績、文化フィットを重視することが大切です。
さらに、フィードバックを取り入れて選考プロセスを改善することで、より良い人材を見極めることができます。
一方で、不完全な書類の見逃しや評価基準の不一致、応募者への連絡の遅れなどは、選考の質を低下させる原因となるため注意が必要です。
特に、採用管理システムを活用することで、選考のスピードと精度を向上させることができます。
書類選考のやり方を見直し、効果的なプロセスを確立することで、自社にとって最適な人材を採用できるようにしましょう。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...