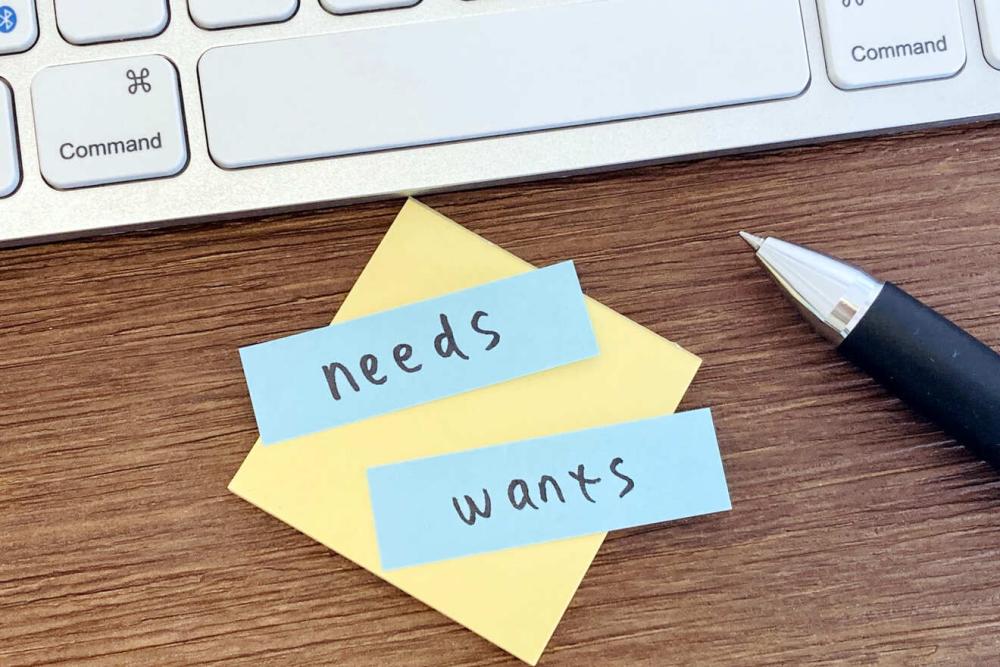応募の断り方で好印象を与える!企業側が実践したい例文とコツ

採用活動において、応募を断るのは気が重い作業ですよね。
相手に悪い印象を与えないか気になってしまうし、応募者の期待に応えられなかったことに対する申し訳なさを感じる気持ちわかります。
できることなら、企業イメージを損なわず、円満に断りたいですよね。
実は、ポイントを抑えた断り方をすることで、応募者に納得してもらうことができます。
応募者に不満を持たれなければ、企業イメージを損ねることはありません。
今回は、不採用にしたい企業向けに「応募の断り方」について例文を交えながら解説します。
好印象を与える断り方をして、選考を前に進めてください。
応募を断る理由とその背景

採用担当者が応募を断る際には、適切な理由と丁寧な対応が求められます。
応募者との信頼関係を保ちながら、採用基準に沿った選考を行うための背景を詳しく解説します。
求めるスキルや経験が合わない
多くの企業は、採用するポジションに対して具体的なスキルや経験を求めています。
この基準を満たしていない場合、採用を見送ることが一般的です。
たとえば、専門的な技術や資格が求められる役職で、応募者がそれに必要な実務経験や資格を持たない場合、即戦力として期待できません。
教育に時間とコストを割けない場合、必要な能力を満たしていないと採用につながりにくいでしょう。
他の応募者がより適している
複数の応募者がいる場合、そのポジションに最も適切な人材を選ばなければいけません。
たとえスキルや経験が似通っていても、他の応募者がより適していると判断した場合、不採用にします。
たとえば、あるスキルに特化したポジションで、同じスキルセットを持つ応募者が複数いる場合、業界経験や実績が優れている方を選ぶのは当然です。
このような判断は、チームの価値を最大化するために行われるものであり、応募者の問題と言うよりも、適性の違いからくる決定といえます。
企業文化に合わないと感じた
応募者が自社の文化と合わないと感じた場合、採用を見送ります。
企業の理念や方針と合わない場合、入社後に摩擦が生じる可能性が高いと判断できるからです。
たとえば、チームワークを重視する会社で協調性に欠ける人が来ると、業務に支障をきたしてしまいます。
企業文化の不一致が理由で、不採用にするケースも珍しくありません。
応募者にやる気を感じない
面接をして応募者にやる気を感じないと、不採用にしたくなります。
やる気や意欲が感じられない場合、採用したいと思えなくて当然です。
たとえば、面接での態度が消極的であったり、なぜこの会社で働きたいのかという志望動機が曖昧だったりする場合、採用することはできません。
企業は成長意欲があり、積極的に仕事に取り組む人材を求めているため、やる気がない人は断りたくなるでしょう。
希望する給与や待遇が合わない
応募者が求める給与や待遇が提示する条件を上回っている場合、不採用にしたくなります。
特に中小企業では予算が限られているため、高額な報酬を提示することが難しいからです。
たとえば、同じポジションの他の従業員と比べて大幅に高い給与を希望されると、予算のバランスが崩れる可能性があるため、行為するのが難しくなります。
こうした理由から、待遇の条件が合わない場合、不採用となることがあるのです。
選考内容が期待に届かなかった
選考内容が自社の思惑と異なる場合、採用を見送る可能性が高いです。
応募者が求めるパフォーマンスに達していない場合も、採用しても働けるかわかりません。
たとえば、適性テストや技術テストで十分なスコアが得られなかったりすると、必要な能力を備えていないと判断できます。
選考内容が期待に届かなかった人物がいると、不採用にしたくなるでしょう。
募集が定員に達した
応募者のスキルや経験に問題がなくても、募集定員に達している場合は採用を見送ることがあります。
中小企業では特に人員数が限られていることもあり、必要以上の人材を確保することは難しいからです。
たとえば、同じ部署の中で既に必要な人数が揃っている場合、新たに採用を行う余地がありません。
これ以上雇うことはできないとなれば、断らざるを得なくなるでしょう。
募集してないのに応募されるワケ

まれに、自社で求人していないにもかかわらず、応募される場合があります。
なぜ募集してないのに応募されるのでしょうか?よくある理由を見ていきましょう。
過去の求人情報が残っている
過去の求人情報がネット上に残っていると、応募される可能性があります。
これは、採用終了後も求人ページがネット上に表示され続けるために発生する問題です。
たとえば、求人サイトに掲載したまま放置した場合、求職者はその情報を見て応募を検討してしまいます。
情報が残っていると応募者に誤解を与え、企業の管理体制に疑問を持たれる可能性もあるため、募集終了後はすみやかに削除してください。
採用ニーズや募集条件が不明確
採用ニーズや条件が不明確だと、自社の期待に合わない応募が増える原因となります。
正確に応募者に伝わっていないため、誤解を招くのが原因です。
たとえば、必要なスキルや経験年数が記載されていない募集要項は、多様な候補者からの応募を引き寄せてしまい、実際のニーズにそぐわない人材が集まることがあります。
採用ニーズや募集条件が不明確なことで、意図しない応募を招いてしまうでしょう。
採用プロセスがわかりづらい
採用プロセスが分かりづらいと、現在の選考状況を理解できないまま応募を続けることがあります。
応募フローや選考スケジュールが曖昧だと、応募者にとって状況が見えづらくなるためです。
たとえば、選考スケジュールが記載されていない募集では、応募者がどの段階で連絡を待つべきかが分からず、複数回応募してしまうことも考えられます。
採用フローをわかりやすく記載することで、応募者の混乱を防ぎ、応募の管理もしやすくなるでしょう。
仕事内容に魅力を感じている
仕事内容に魅力を感じている応募者は、募集していない状況でも応募を試みることがあります。
これは、企業の持つ専門性や仕事のやりがいに惹かれているためです。
たとえば、技術力が高い企業や業界で評価されている企業では、将来働きたいと感じる人材が自主的に応募してくるケースが見られます。
このような応募に対しては、丁寧に対応して募集時期を伝えることで、将来的に優秀な人材を確保するきっかけにできるでしょう。
スカウトやSNSの活用
スカウトやSNSを活用している企業は、応募者からの直接のアプローチが増える傾向にあります。
SNSで企業の情報を発信することで、応募者が興味を持ちやすくなるためです。
たとえば、自社の公式SNSで社員インタビューや仕事内容を公開することで、企業に関心を持った求職者が自発的に応募を試みるケースがあります。
企業にとってSNSはブランディングの一環ですが、適切な応募窓口を示しておくことで、応募管理がスムーズに進み、採用活動にも有効に働くでしょう。
好印象を与える断り方の心理的配慮

応募を断る場面でも、企業の印象を左右する大切な機会となります。
単なる不採用通知ではなく、応募者の気持ちに寄り添った対応を心がけることで、企業の信頼性や誠実さが伝わります。
たとえ今回は縁がなかったとしても、未来の応募や紹介につながる可能性を残せる対応を意識しましょう。
応募者が覚えているのは「対応の質」
選考結果そのものよりも、どのように伝えられたかが印象に残ります。
それは、対応の温度感や言葉選びが応募者の感情に強く影響するためです。
たとえば、結果通知が淡泊すぎると「軽く扱われた」と感じる人もいます。
逆に丁寧な言葉で誠実に伝えれば、「きちんと見てくれていた」と好印象に変わります。
結果の内容以上に伝え方の工夫が評価されることを意識してください。
伝わる断り方の3要素:感謝・誠実・未来志向
相手の気持ちに配慮した断り方には、感謝・誠実・未来志向の3つが大切です。
これは、応募者との関係性を丁寧に終わらせるための基本要素です。
具体的には、「ご応募いただきありがとうございます」と感謝を伝え、「選考の結果、今回はご期待に添えませんでした」と誠実に理由を述べ、「またの機会があれば幸いです」と未来への可能性を示します。
これらの一言が信頼感を築く鍵となるでしょう。
再応募につなげる断り文の工夫
今回の応募が不採用であっても、将来のご縁を大切にしたい場合は、文面に工夫が必要です。
なぜなら、断り方次第で「もう応募したくない」と思わせてしまうリスクがあるからです。
例として、「今後、別のポジションでご活躍いただける可能性があると感じました」などの前向きな表現を加えると、応募者の希望を完全には閉ざしません。
未来に向けた余白を残すことで、良い関係性が維持されるでしょう。
納得されやすい理由の伝え方
選考結果に納得してもらうには、理由を明確に、かつ配慮ある言葉で伝えることが大切です。
これは、応募者の疑問や不満を和らげるためです。
たとえば、「今回は、特定分野での実務経験が必要なため、より要件に合致した方を選考させていただきました」と伝えると、個人攻撃と受け取られずに済みます。
相手に誠実さが伝わる表現を選ぶことが、信頼感を保つコツでしょう。
テンプレ文の一言アレンジ術
テンプレートをそのまま使うと、機械的な印象を与えてしまいがちです。
なぜなら、多くの応募者は「自分だけに送られたのか」と敏感に受け取るためです。
例として、「ご経歴の中で特に印象に残った◯◯のご経験は、当社でも非常に重要と考えております」といった一文を加えるだけで、個別に見てくれていたという印象を与えられます。
わずかな工夫で、心に残る断り方ができるでしょう。
応募を断る際の適切な言い回しと例文

応募を断る際には、相手に配慮しながらも誤解を避け、スムーズに納得してもらうことが重要です。
適切な言い回しと例文を使い、企業イメージを損ねずに対応する方法を解説します。
応募者がスキル不足である場合
応募者のスキルが基準に達していない場合、丁寧に伝えることで失礼のない対応ができます。
応募者の気持ちに配慮しつつ、直接的な言い方は避けてください。
例として「現時点でのご経験が当社の求める要件を満たないため、今回は採用を見送らせていただきます」と伝えることで、応募者にスキル不足を柔らかく示すことができます。
このような断り方は、応募者の今後の成長を期待していることも伝わるため、印象を悪くしないでしょう。
他の候補者がより適している場合
他の候補者がより適している場合は、応募者に対して前向きな印象を残しつつ丁寧に断ることが大切です。
応募者のプライドを傷つけずに、不採用を伝える工夫が必要になります。
たとえば、「厳正な選考の結果、今回は他の候補者を採用させていただく運びとなりました」と伝えると、候補者間での比較が行われたことが明示されます。
断る理由を適切に示すことで、応募者に納得感を与えるでしょう。
企業文化に合わない場合
企業文化とのミスマッチがある場合、相手に配慮しつつ断る表現が重要です。
自社の環境が応募者に適してないことを、それとなく伝えなければいけません。
例として、「当社の企業文化や価値観を考慮した結果、今回は他の候補者を選ばせていただくこととなりました」といった言い回しを使えば、企業独自の判断基準であることが伝わります。
企業文化のミスマッチを理由にする断り方は、企業らしさを示す手段としても有効です。
選考内容が期待に届かなかった
選考の結果、応募者が期待に届かなかった場合も、相手に敬意を払いながら断る必要があります。
率直に「期待外れ」と伝えてしまうと、トラブルになる可能性があるからです。
例として、「選考過程での結果を踏まえ、今回は別の方を採用させていただくことに決定いたしました」と述べれば、応募者に対して選考基準を満たさなかった旨が伝わりやすく、誠実な印象を与えます。
このような言い回しは、選考の公正さを示し、応募者の努力に敬意を表する効果もあるでしょう。
募集していなかった場合
企業が募集していない状況で応募が寄せられた場合も、丁寧な対応が求められます。
意欲的に応募してくれた人材を無視するのではなく、適切な対応をすることで良い印象を残せます。
具体的には、「現在は新規採用を行っていないため、今回の応募は見送らせていただきます」と伝えることで、現状の採用活動をはっきりと示せます。
将来的に募集の可能性があれば、その旨を付け加えることで、関係性を保ちながら断ることができるでしょう。
中小企業が応募を断る際のNG対応とは

応募を断る際の対応次第で、企業に対する印象は大きく変わります。
適切でない断り方は企業イメージを損ない、信頼を失うリスクがあるからです。
そこで、中小企業向けに応募を断る際のNG対応をご紹介します。
理由を説明しない
応募を断る際に理由を伝えないと、応募者に不信感を与えます。
応募者は、選考結果について何かしらのフィードバックを期待しているため、理由が伝えられないと不満が残りやすくなるからです。
たとえば、「今回はご縁がありませんでした」という曖昧な返答では納得しづらくなり、企業への不信感を抱きかねません。
理由を簡潔にでも伝えることで、応募者が納得しやすくなり、企業の信頼感も保たれるでしょう。
応募者を批判する
応募者に対して批判的なフィードバックをするのは、避けるべきNG対応です。
評価基準を満たさなかった場合でも、応募者の人柄や能力を批判するような表現は、深い傷を与えかねません。
例として、「あなたの経験不足が原因で採用には至りませんでした」といった直接的な言葉は、応募者に不快感を与えるだけでなく、企業の対応が冷淡と受け取られる可能性があります。
配慮を欠いた対応は炎上のきっかけにもなるため、丁寧で配慮ある表現が求められるでしょう。
冷たく無愛想な対応
冷たく無愛想な対応は、「配慮が欠けている会社」といった印象を与えます。
場合によっては幼いイメージを与え、企業としての信頼を大きく損なうのです。
単に「採用できません」といった返信をすると、応募者が企業全体を否定的に捉える要因となりかねません。
応募者の努力を評価し、丁寧な対応を心がけることで、応募を断る場合でも誠実な企業の印象を残せるでしょう。
失礼な言い回しを使う
応募者に対して失礼な言い回しを使用することは、企業のイメージを損ねる大きなNG対応です。
言葉遣いに配慮が欠けると、応募者に不快感を与え、企業の信用も大きく失墜します。
たとえば、「どう考えてもスキルが足りません」などの失礼な表現は、応募者が企業に対して不信感や反発を抱く原因となります。
丁寧で適切な言葉遣いを徹底することで、誠実な企業としての信頼感を守れるでしょう。
応募を無視する
応募に対して返信をしない、あるいは長期間放置するのもNG対応です。
採用基準に満たなかったとしても、応募を無視すると無責任な印象を与えるのです。
応募後の通知が何も届かず、一切のアクションを起こさない状況だと、応募者はどうしたら良いかわかりません。
たとえ書類選考で不採用にする場合でも、必ず返信をするようにしてください。
応募の断り方に関するよくある疑問

応募を断る際のマナーや対応については、採用担当者の悩みの種でもあります。
採用担当者の振る舞い方次第で、企業イメージが良くなったり悪くなったりするからです。
そこで、応募の断り方に関するよくある疑問について回答します。
Q. 不採用通知はどのタイミングで送るべき?
不採用通知は、選考が終了したらできるだけ早めに送るのが理想的です。
通知を遅らせると、応募者は長い間不安な状態に置かれ、企業への不信感が生まれる恐れがあります。
たとえば、面接から1週間以内に通知を送ることで、応募者に誠意が伝わりやすくなります。
迅速な対応は企業の印象を向上させ、たとえ不採用でも好意的に受け止められるでしょう。
Q. どこまで詳細に理由を伝えるべきか?
不採用理由は、応募者に誤解を与えない範囲で簡潔に伝えるのがベストです。
過度に詳細な説明をすると、応募者を傷つける可能性があり、トラブルにもつながりかねません。
具体例としては、「今回は他の候補者を採用することに決定いたしました」といった、候補者間の比較に触れる表現であれば、応募者も納得しやすくなります。
応募者が適度に理解できる程度に理由を伝えることが、円滑なコミュニケーションの鍵となるでしょう。
Q. 断り方における言葉遣いの注意点は?
不採用通知の言葉遣いには、応募者に対する敬意や配慮が求められます。
断りの連絡が雑だと、応募者に不快な印象を与え、企業評価にも悪影響を及ぼします。
たとえば、「お忙しい中、選考にご応募いただきありがとうございました。誠に残念ではございますが、今回はご期待に沿えない結果となりました」という表現は、応募者に対する敬意が伝わりやすく、好印象を与えます。
丁寧な言葉遣いを心がけることで、応募者との良好な関係を維持しやすくなるでしょう。
Q. 応募者からの問い合わせにはどのように対応する?
不採用通知後の問い合わせには、迅速かつ誠実に対応することが重要です。
応募者は結果に疑問や不安を抱える場合があるため、その声に応えることで企業への信頼が高まります。
たとえば、「お問合せありがとうございます。採用選考は厳正に行った結果であり、再検討は難しい旨をご理解いただければ幸いです」といった丁寧な返信を行うと、応募者にも誠意が伝わります。
真摯な対応は、企業の信頼性を高める手段としても有効となるでしょう。
Q. 応募者が再応募してきた場合、どう対応するべき?
過去に不採用となった応募者が再応募してきた場合、前回の結果に固執せず柔軟に対応することが大切です。
応募者もその間に成長している可能性があり、新たなスキルや経験を積んでいることも考えられます。
具体例として、「前回の選考結果には影響せず、公平に再度選考させていただきます」と伝えることで、応募者にチャンスがあることを示せます。
再応募への前向きな姿勢が、企業の開かれた姿勢として評価されるでしょう。
採用管理システムなら応募の断り方も簡単!

採用管理システムを導入すると、応募者への対応が効率化され、不採用通知も簡便かつ円滑に行えるようになります。
なぜなら、手作業での管理やメール対応は時間がかかり、担当者の負担も大きくなるからです。
一方で、採用管理システムを利用すれば、不採用通知の送信が短時間で完了し、送信日時の調整や文面のテンプレート化も可能になります。
また、応募者ごとのステータス管理も容易になり、選考状況を一目で把握できるため、誤送信や対応漏れといったミスの防止にも役立ちます。
企業のイメージ向上や業務の効率化を目指す中小企業にとって、採用管理システムの導入は、応募者への誠実で迅速な対応をサポートするでしょう。
まとめ
応募を断る際には、企業イメージを損ねず、応募者に配慮した対応が必要です。
選考結果を円満に伝えるためには、理由をしっかりと伝え、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がけるようにしてください。
また、応募者に対する批判や失礼な言い回し、冷たい対応は避け、企業の誠実な姿勢を示すことが求められます。
加えて、応募者からの問い合わせには迅速かつ誠実に対応し、再応募があった場合には柔軟に対応することで、企業の信頼を築くことができます。
たとえ募集していない状況で応募があったとしても、無視してはいけません。
丁寧に募集していない事実を伝え、なるべく穏便に拒否するようにしてください。
せっかく応募してくれた候補者を断るのは気が引けますが、断り方次第で企業イメージが向上する場合もあります。
今回ご紹介した方法を参考に、企業としての誠実さを示し、応募者にとっても納得できる断り方を実現していきましょう。
関連記事
-

求める人物像はどう書く?採用サイトに適した書き方と事例
採用サイトに掲載する「求める人物像」。どう書けば良いか難しいですよね。抽象的すぎたら伝わらないし、具体的にしすぎると人が来なくなりそうです。そこで、「採用サイト...
-

退職代行を使われたショックをチャンスに変える!中小企業の採用戦略
これまで一緒に働いてきたのに、社員に退職代行を使われるとショックですよね。しかし、退職代行を使われるような状況をチャンスに変えることができます。職場環境を見直す...
-

採用サイトのアクセス数を増やす方法とは?中小企業向け完全ガイド
採用サイトを作っても、アクセス数が思うように伸びないと悩みますよね。アクセスが少ないと応募が増えないし、モチベーションが下がる気持ちわかります。今回は中小企業向...
-

採用活動のKPIとは?中小企業向けの立て方と活用法を徹底解説
-

新入社員が辞める兆候は?よくあるサインと定着率を高める施策
新入社員がすぐ辞めてしまうのは、経営者として本当に頭の痛い問題ですよね。採用や育成に時間とコストをかけたのに、すぐに辞められてしまうとガッカリする気持ちわかりま...